「服のタグがチクチクして嫌がる」「大きな音に驚きやすい」「痛みに鈍感でケガに気づかない」
子どものこうした反応に戸惑ったことはありませんか?
これは、感覚の「敏感さ」や「鈍感さ」によるものかもしれません。
子どもによって感じ方はさまざまで、日常生活に影響を与えることもあるでしょう。
本記事では、子どもの敏感さの特徴や影響を解説し、チェックリストを通じて特性を理解する方法を紹介します。
- 子どもの「敏感さ」に悩んでいる共働きの親御さん
- 子どもの育てにくさを感じている保護者や支援者
- 子どもの発達特性を理解し、よりよい接し方を知りたい方
 ゆう
ゆうお子さんに合ったサポートのヒントを見つけてみましょう。
子どもの「敏感さ」とは?


まずは、子どもの敏感さがどのようなものかを理解し、それが日常生活にどんな影響を与えるのかを解説します。
子どもの特性を知ることで、「どう接すればよいのか?」のヒントを見つけていきましょう。
子どもの「敏感さ」とは?
子どもの「敏感さ」とは、外部からの刺激に対する感じ方の違いを指します。
多くの人は一定の範囲内で刺激を受け止めますが、一部の子どもはとても敏感に反応したり、逆に鈍感だったりします。
例えば、聴覚が敏感な子は少しの物音でも不快に感じる一方、鈍感な子は大きな声を出しても気づかないことがあります。
触覚に敏感な子は特定の衣類を嫌がりますが、鈍感な子は痛みや寒さをあまり感じません。
このように、敏感さには「過敏」と「鈍感」の両面があり、それぞれの特性を理解することが大切です。
「敏感さ」が日常生活に与える影響
子どもの敏感さは、日常生活のさまざまな場面に影響を及ぼします。
例えば、聴覚が敏感な子どもは教室のざわめきが気になり、授業に集中できないことがあります。
逆に鈍感な子どもは、先生の指示を聞き逃しやすいこともあります。
また、触覚が過敏な子は制服や靴下を嫌がるため、登校時にストレスを感じることがあります。
一方で、鈍感な子は転んでも痛みに気づかず、ケガをしても気にしない場合があります。
こうした特性が、学習の困難さや対人関係のすれ違いにつながることがあるため、適切なサポートが求められます。
成長とともに変化する「敏感さ」の捉え方
子どもの敏感さは、成長とともに変化することがあります。
小さい頃は音や肌触りに敏感だった子が、年齢を重ねるにつれて気にならなくなることもあれば、逆に環境の変化によって過敏さが強まることもあります。
また、鈍感な子どもも、経験を積むことで少しずつ感覚が研ぎ澄まされることがあります。
大切なのは、「敏感だからダメ」「鈍感だから心配」と決めつけず、子どもの特性を受け入れながら、その時々の成長に合わせた対応をすることです。
親や周囲の理解とサポートがあれば、子どもは自分の特性とうまく付き合いながら成長していけるでしょう。
子どもの「敏感さ」の分析のための8つのチェックリスト
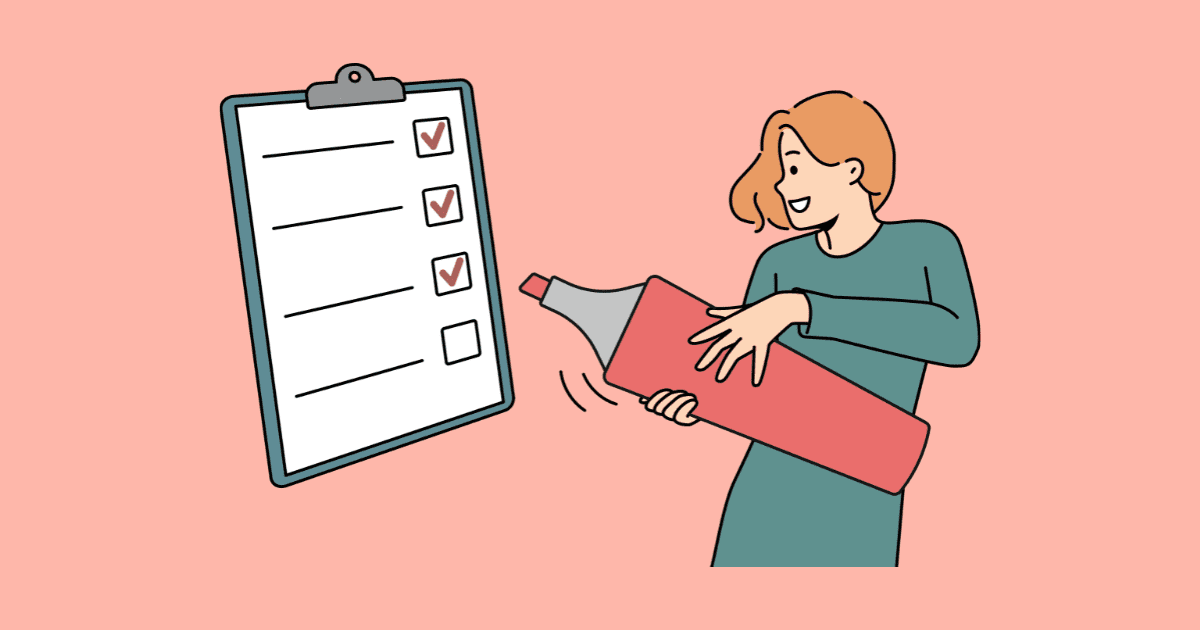
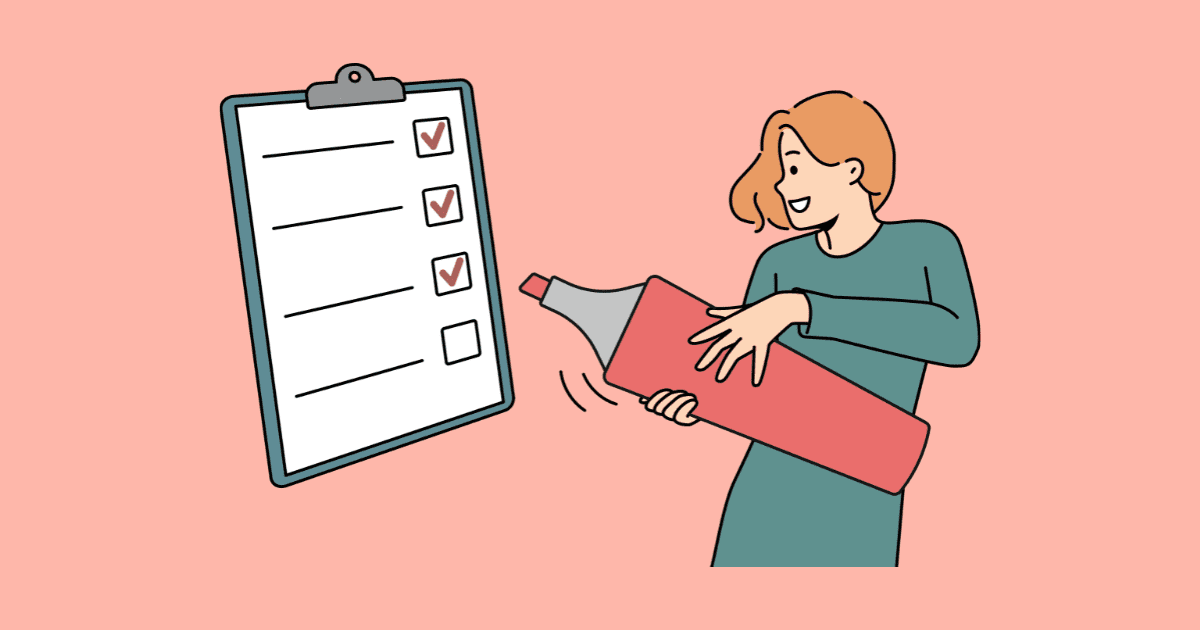
子どもの過敏さを分析するためのチェックリストについて紹介していきます。
このチェックリストは、発達障害を専門とする精神科医の岡田尊司先生の書籍「過敏で傷つきやすい人たち HSPの真実と克服への道」を参考としています。
8つのチェックリストは次のとおりです。
- 感覚過敏
- 順化抵抗
- 愛着不安
- 心の傷
- 身体化
- 妄想傾向
- 回避傾向
- 低登録
このチェックリストの各該当項目については次のようにカウントします。
- 0〜1個:「その傾向があまりない」
- 2〜3個:「その傾向がややある」
- 4〜5個:「その傾向がかなり強い」
このチェックリストの詳細な分析を知りたい方は、ぜひ以下の書籍を手に取って読んでいただければと思います。



お子さんやご自身の過敏さで悩んでいる人におすすめの本です。
感覚過敏
| ⬜︎ | 大きな音が苦手で、突然の物音に過剰に驚いてしまう。 |
| ⬜︎ | 人混みやがやがやして騒々しい場所が苦手で、極度に疲れてしまう。 |
| ⬜︎ | 匂いや味、間食などに敏感で、苦手な匂いや食べられないものが多い。 |
| ⬜︎ | 目を合わせてしゃべることや、過度に接近されるのは苦手である。 |
| ⬜︎ | 人の話し声やBGMの音があると、集中が妨げられてしまう。 |
感覚過敏があると音や匂い、味といったことに極端な反応をしやすくなります。
感覚過敏は、遺伝的、発達的要因がかなり強く影響されるとされます。



不登校や適応障害の方にも、しばしば感覚過敏が認められます。
順化抵抗
| ⬜︎ | 寝る場所や枕が変わると、なかなか寝付けない。 |
| ⬜︎ | 時計の秒針の音や通りの音が気になって眠れないことがある。 |
| ⬜︎ | 新しい環境や人に馴れるのに、だいぶ時間がかかる方だ。 |
| ⬜︎ | いつ来るかわからない電話やメールを待つのは、とてもストレスである。 |
| ⬜︎ | 予定外のことや期待と違うことが起きると、怒りを覚えたりパニックになりやすい。 |
順化抵抗は、馴れにくさのことです。
過敏さのない人では、新しい刺激をむしろ心地よく感じる人もいますし、少し苦痛な刺激であっても、2、3度経験するだけで、あまり気にならなくなる人もいます。



過敏な人では、刺激への順化(刺激への馴れ)が生じにくいです。
新しい刺激や環境に馴れにくい傾向は、心理社会的な過敏性にも大きく関与しています。
愛着不安
| ⬜︎ | 自分が一人でいることが不安で、いつも誰かに頼りたくなる。 |
| ⬜︎ | 人にどう思われているか顔色に敏感で、悪く思われていると感じると、気もそぞろになる。 |
| ⬜︎ | 自分が相手に不快な思いをさせていないか、いつも気にしてしまう。 |
| ⬜︎ | 些細な相手の素振りにも、自分が嫌われていないか不安になる。 |
| ⬜︎ | 間違いを指摘されたり、欠点を非難されると、落ち込んだり、逆にキレたりしやすい。 |
愛着不安とは、愛着している存在に見捨てられるとか、拒否されるといった不安を抱きやすい傾向です。
愛着不安の由来は、幼い頃母親から離れることに対して抱いた分離不安にまで遡ると考えられています。
愛着不安が強い人では、愛着している存在はもちろん、それ以外の他者からも嫌われたり拒否されていないか、過度に敏感になり過剰反応しやすいです。
心の傷
| ⬜︎ | 人から言われた言葉に傷つきやすい。 |
| ⬜︎ | 嫌なことがあると、長く引きずる方だ。 |
| ⬜︎ | 昔の嫌な場面の記憶がよくよみがえってくる。 |
| ⬜︎ | 苦手な話題に触れられると、動揺したり取り乱したりする。 |
| ⬜︎ | 一度嫌なことがあると、その相手や場所を避けてしまう。 |
未解決な心の傷を抱えている人は、傷つきやすく、新たにダメージを受けやすいだけでなく、ダメージを受けたときに、回復に時間がかかる傾向が見られます。
また、過去の不快な体験がフラッシュバックしたり、いつまでも否定的な体験にとらわれることが多いと言えます。



愛着の問題とも結びつきやすいものです。
身体化
| ⬜︎ | 緊張すると声や手が震え、人前で話すのが苦手である。 |
| ⬜︎ | 不安になると、動悸や息苦しさを感じやすい。 |
| ⬜︎ | 体がいつも緊張していて、肩こりや頭痛が多い。 |
| ⬜︎ | 本番が近づくと、お腹が痛くなったり、具合が悪くなったりしやすい。 |
| ⬜︎ | ストレスで胃が痛くなったり、熱が出たりしやすい。 |
不安やストレスを感じていても、それが自律神経の乱れとなって体の症状として出やすい人と、あまり出ない人がいます。
過敏な人では、ストレスや不安の身体化が起きやすく、その程度は人によって異なります。
妄想傾向
| ⬜︎ | ひそひそ話が聞こえてくると、自分の悪口を言われているように思ってしまう。 |
| ⬜︎ | 自分のことが何もかも知られているように感じることがある。 |
| ⬜︎ | 人の視線が気になって、外出しづらい。 |
| ⬜︎ | 人が信じられず、相手の言葉の裏を考えてしまう。 |
| ⬜︎ | 周囲が自分のことを貶めようとしていると感じることがある。 |
妄想とは、現実ではないことを真実だと思いことですが、妄想にもさまざまなタイプがあります。
過敏性ともっとも関係が深いのは、現実の出来事を被害的に解釈してしまう、いわゆる「被害妄想」です。
ここでは「妄想傾向」を図っていて、本当の妄想ではありませんが、だからと言って安心というわけではありません。
過敏性がかなり高い状態に伴いやすく、精神病状態やその兆候を示すサインであることも多いです。
回避傾向
| ⬜︎ | 馴れたものしか食べない。 |
| ⬜︎ | 体を触られるのは好まない。 |
| ⬜︎ | 他人が近づきすぎると離れたくなる。 |
| ⬜︎ | べたべたするのは苦手である。 |
| ⬜︎ | 人前に出るのは、できるだけ避けたい。 |
回避的な傾向を持つ人では、次の3つの特徴があります。
- 人との距離の近い関係を避けようとし、身体的な接触をしたり親密な関係になるのを好まない。
- 自分の内面や気持ちを語りたがらない。
- 新奇な体験へのチャレンジを避けようとする。



回避傾向は、社会適応の悪さや生きづらさに結びつきやすいようです。
低登録
| ⬜︎ | 相手の言葉が聞き取れず、よく聞き返す。 |
| ⬜︎ | 冗談やギャグが、すぐにわからないときがある。 |
| ⬜︎ | ものによくぶつかったり、つまずいたりする。 |
| ⬜︎ | 顔や手が汚れていても気づかないことがある。 |
| ⬜︎ | 標識や案内板を見落としやすい。 |
低登録とは、弱い刺激では反応しにくい傾向で、五感だけでなく、聞き取りや社会的認知の鈍さも含んでいます。
過敏さに直接関係するわけではありませんが、低登録の傾向は敏感さや傷つきやすさと同居していることも多いです。
HSP による生きづらさについての記事がありますので、併せてご覧ください。
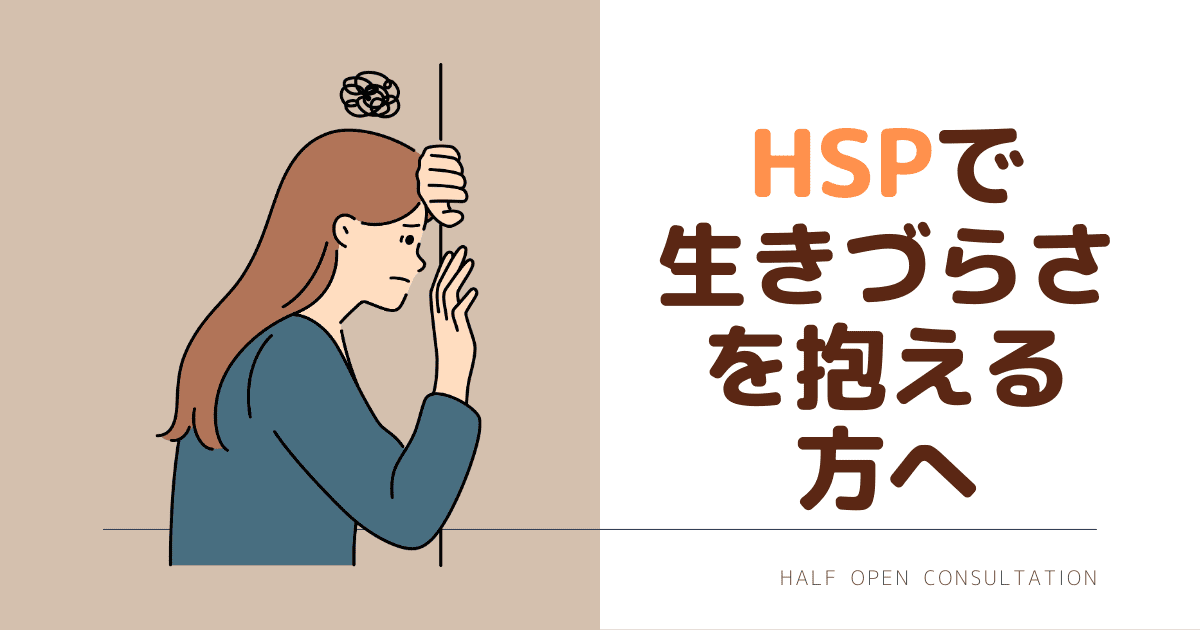
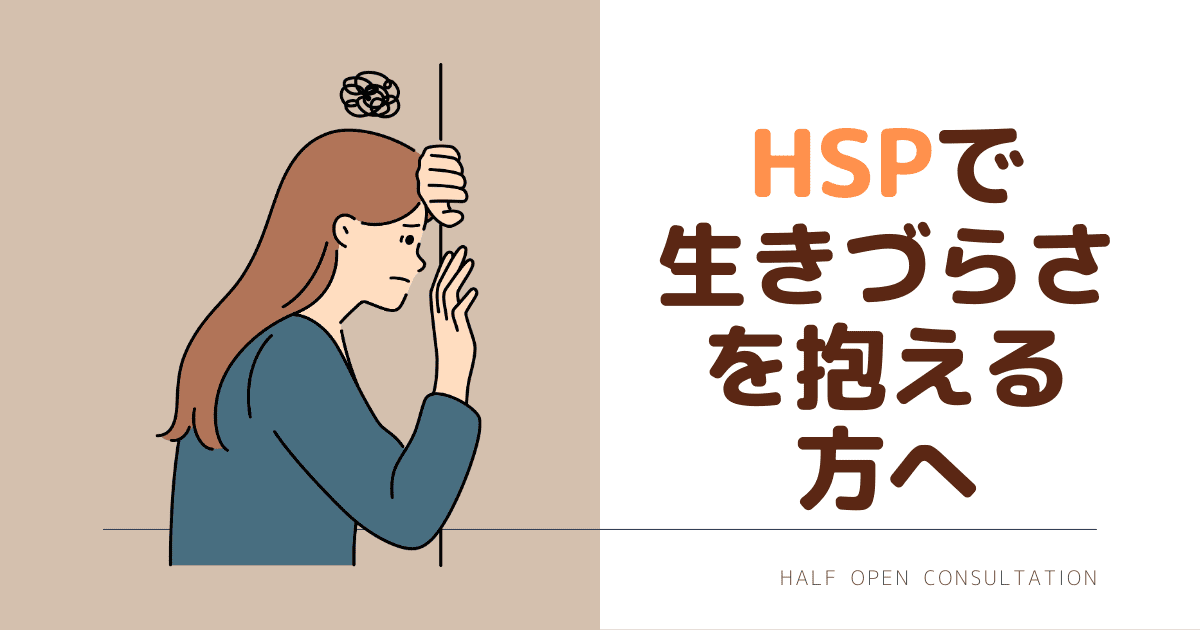
まとめ
本記事では、子どもの敏感さの特徴や影響を解説し、チェックリストを通じて特性を理解する方法を紹介しました。
子どもの敏感さは一人ひとり異なり、成長とともに変化することもあります。
大切なのは、「なぜ苦手なのか?」を理解し、無理のない環境を整えることです。
チェックリストを活用し、お子さんの特性を知ることで、より適切なサポートが可能になります。
敏感さは個性の一つ。親や周囲の理解があれば、子どもは安心して成長できます。
お子さんの感じ方に寄り添いながら、心地よく過ごせる工夫をしていきましょう。
子どもの感覚過敏について支援の方法を解説した記事もありますので、併せてご覧ください。
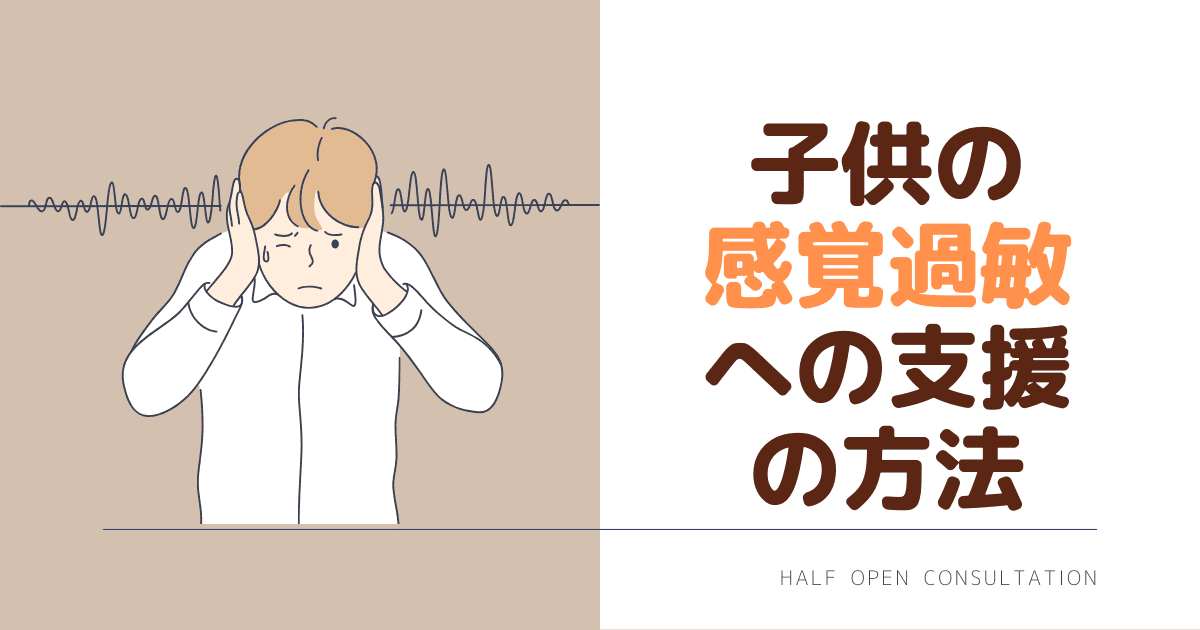
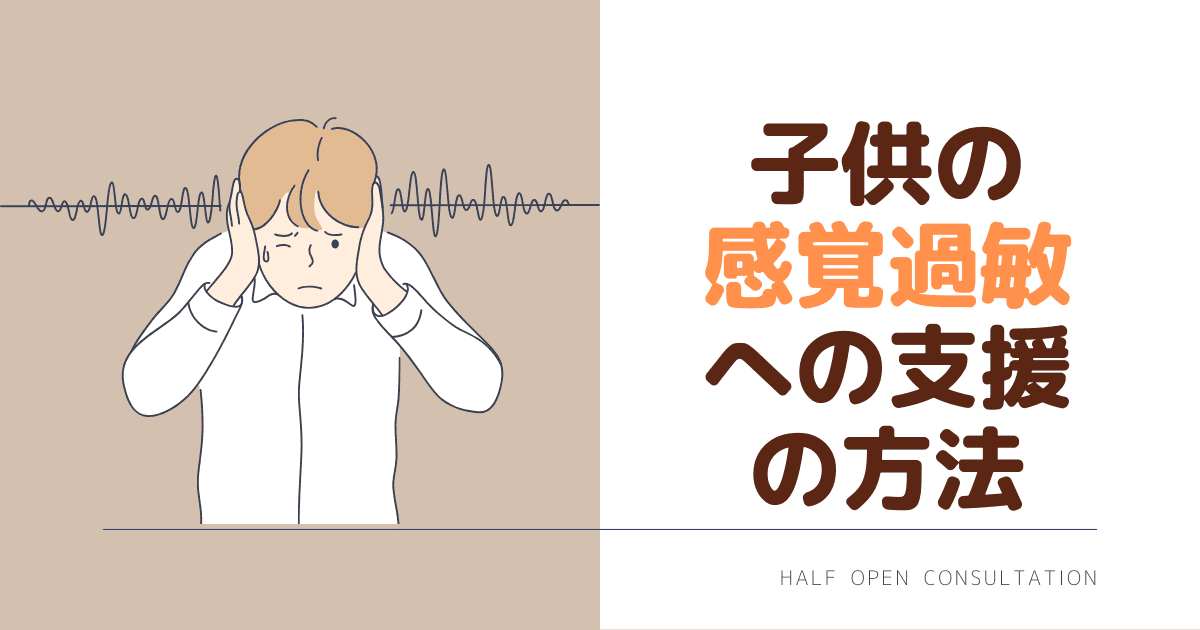
ご相談やご質問がある場合は、こちらにご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村
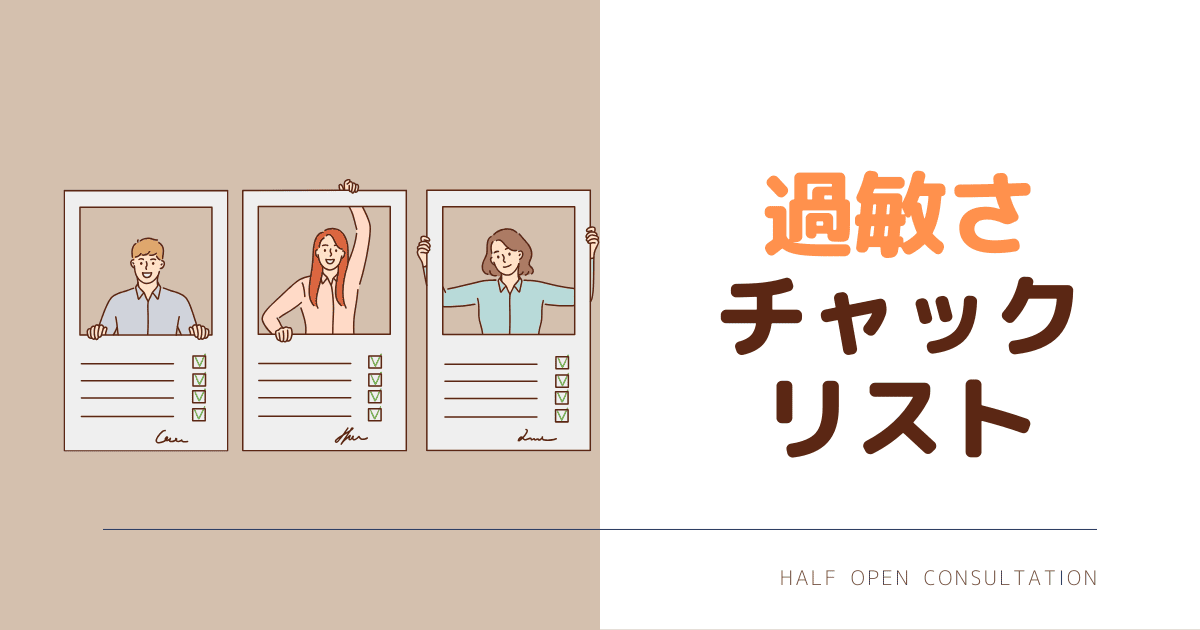

コメント