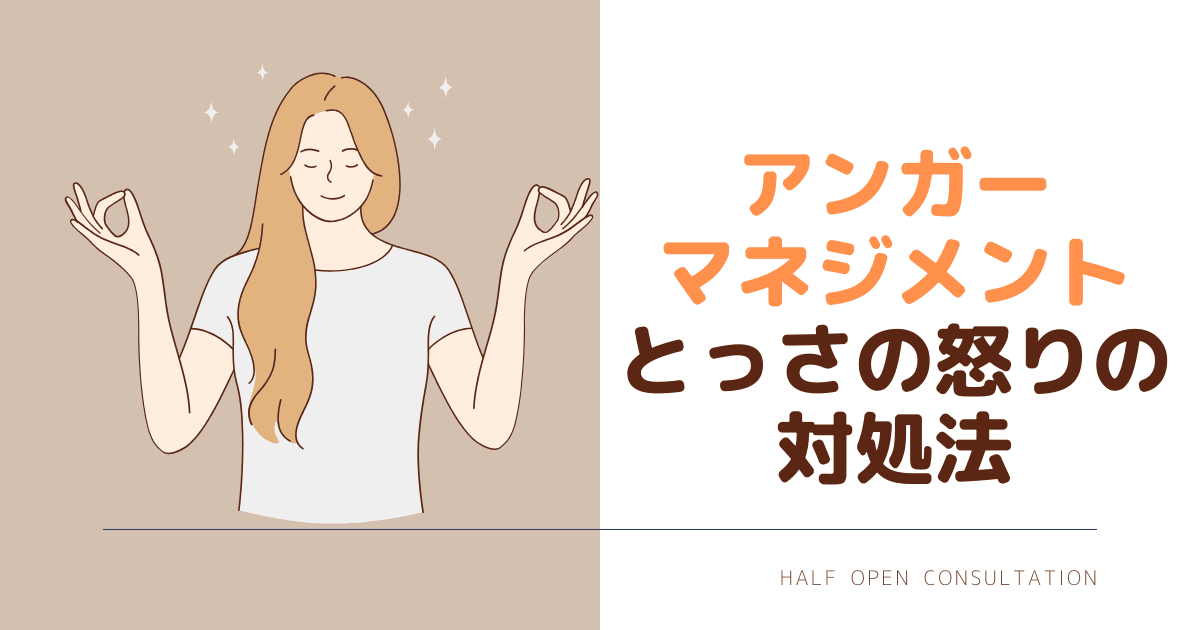この記事では、
アンガーマネジメントで「とっさの怒り」に対処する方法
について詳しく説明していきます。
子どもがわがままを言ったり、親の言うことを聞かなかったりして、とっさに怒りやイライラが高まってしまうことがありませんか?
怒りに任せて怒鳴ったり、イライラをぶつけたりしてしまうと、子どもの心の成長に傷を負わせてしまう可能性があります。
子どもは親の言動をよくみているので、同じように怒りの感情を抑えられなくなってしまうかもしれません。
子どもが怒りの感情をコントロールできるようになるためには、まずは親ができるようになる必要があります。
そこで、今回は、
- アンガーマネジメントって何?
- とっさの怒りに利くアンガーマネジメントスキルを知りたい!
- 子どもの前ですぐに怒らない親になりたい!
といった疑問や悩みに答えていきます。
 ゆう
ゆう誰でも簡単にできる方法を紹介します。
この記事では、アンガーマネジメント協会代表理事の安藤俊介監修の漫画「もう怒らない本」を参考にしています。
アンガーマネジメントとは


「アンガーマネジメント」とは、怒りなどの感情を上手にコントロールしたり、適切な方法で表現できたりするようになるためのスキルです。
怒りなどの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングです。
自分の怒りの感情と上手に付き合い、人前で怒りの感情を上手に出せるようになったり、必要のないときには出さないようにしたりできるようになることを目的としています。
とっさに利くアンガーマネジメントスキル
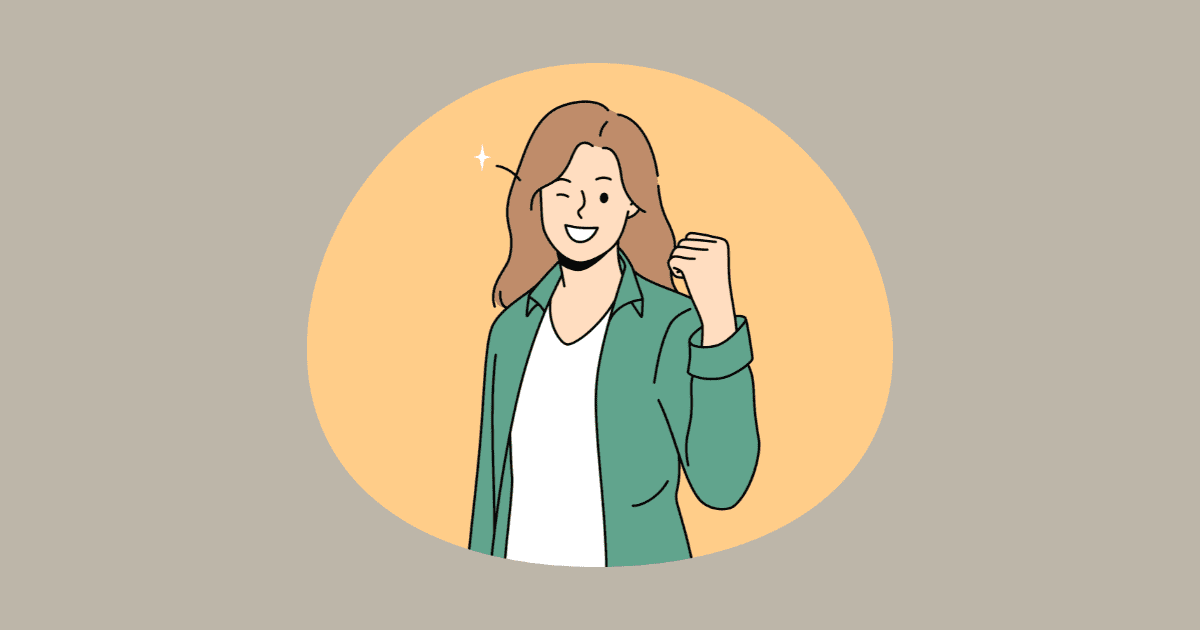
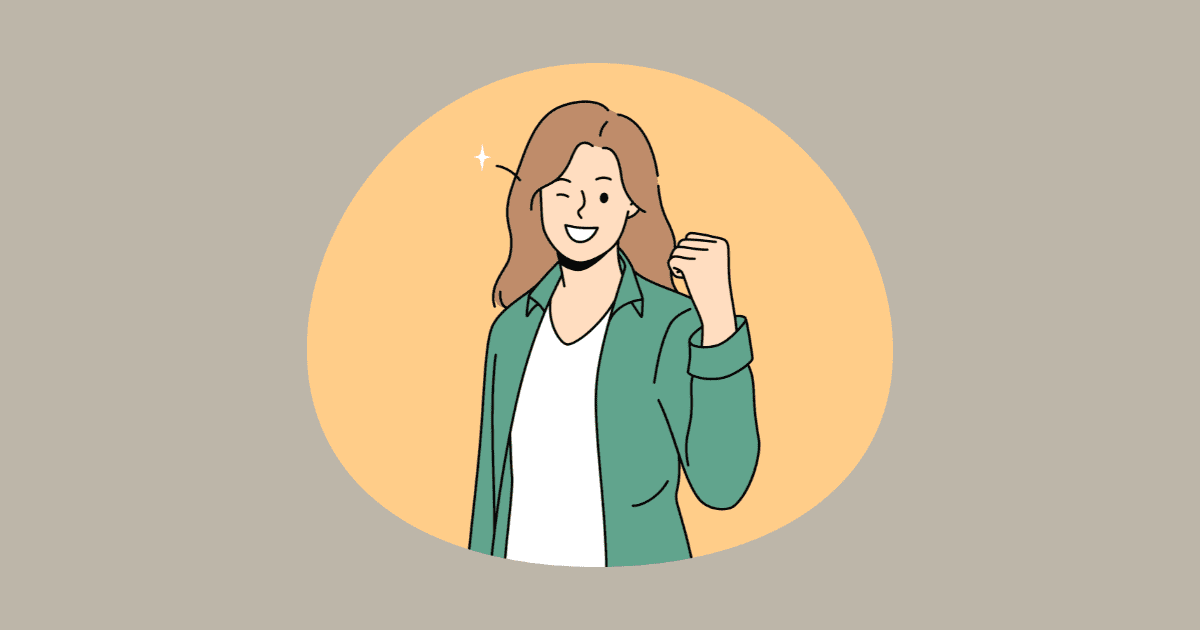
とっさに利くアンガーマネジメントスキルを説明します。
とっさに高まった怒りを爆発させてしまって、後で後悔した経験は誰にでもあると思います。
カッとなったときに怒りを爆発させないことが、何よりも大切です。
怒りをその場で静めたいときに力を発揮する、7つのテクニックを紹介します。
- まずは6秒数える
- 怒りを数値化する
- 魔法の言葉を唱える
- イメージの力を活用する
- タイムアウトを取る
- 気持ちいい瞬間を想像する
- 「今ここ」に集中する



どれもすぐに使えるものばかりです!
まずは6秒数える
1つ目は、「まずは6秒数える」方法です。
諸説ありますが、怒りが発生してからピークを過ぎるまでの時間は、およそ6秒だと言われています。
このたった6秒の間に、人は反射的に暴言を吐いたり、モノや人に当たったりしてしまいます。
つまり、怒りのピークの6秒間をやり過ごせれば、気持ちが落ち着いて、反射的な言動による失敗を防ぐことができると言うことです。
とっさの怒りを抑えるには、怒りを感じたらとにかく6秒数えることを習慣にすると良いです。
怒りをぶつけたくなるのをグッと堪えて、心の中でゆっくり「1、2、3、4、5、6」と数えてみてください。
その間に、少しずつ怒りが静まって、落ち着きが戻ってきます。



ただし、6秒過ぎれば怒りがなくなるというわけではないので、その点は注意しましょう。
怒りを感じてからの6秒間の過ごし方は、数字を数えるほかに次のような方法がおすすめです。
- わざと英語で「ワン、ツー、スリー・・・」と数える。
- 100から3ずつ引く
- ゆっくり目一杯深呼吸する
- 目の前のモノをじっくりと観察する
- 心の中で歌を歌う
怒りを数値化する
2つ目は、「怒りを数値化する」方法です。
人は、怒りを感じると、一方的に「許せない!」と思いがちです。
まるで弱点を突かれたかのように、ムキになって反撃しようとしてしまいます。
「怒りで熱くなった」などと言うことがありますが、人は自分の怒りを、過大評価することがあります。
自分が怒りの感情に流されそうだと感じたら、その「怒りの温度」がどれくらいなのかを考えて数値化してみましょう。



「今、この怒りはどれくらい強いものかな?」といった感じです。
数値化してみると、多くの場合「実は大したことなかった」と気づくことができます。
数値化しようと考えるだけで理性が働き、怒りを静める効果もあります。
こうしたテクニックを「スケールテクニック」と言います。
- レベル0:怒りを感じない状態
- レベル1〜3:「まぁいいか」と流すことのできる、軽い怒り
- レベル4〜6:平静を装ってもモヤモヤが残る、少し強い怒り
- レベル7〜9:カーッと憤りを感じる、かなり強い怒り
- レベル10:最大級の怒り。普通の生活をしていたら感じない強さ
魔法の言葉を唱える
3つ目は、「魔法の言葉を唱える」方法です。
気が立って仕方がないときに、身近な人から「大丈夫だと」などと声をかけてもらって、落ち着くといった経験をしたことがある人はいると思います。
理不尽な扱いに憤慨している時も、誰かに理解してもらえたと感じたら、冷静さを取り戻すことができます。
誰かから「あなたは悪くない」と言ってもらえると、すーっと楽になるものです。
実は、これは、他人からの言葉に限りません。
自分自身に言葉をかけても、心を落ち着かせることが可能です。
自分にとって、怒りを静めるのに有効そうだと思える「魔法の言葉」を、いくつか用意しておきましょう。
そして怒りの火が燃え始めたときには、それらの言葉を自分に言い聞かせて「消化活動」をしてください。



自分を落ち着かせる「魔法の言葉」は自由ですが、いくつか例を紹介します。
- 「まぁ、明日には忘れているから、気にしない!」
- 「大したことないや」
- 「ドンマイ、ドンマイ」
- 「大丈夫、大丈夫」
- 「どうでもいい、どうでもいい」
自分に合った言葉を見つけておきましょう。
ただ、一つだけ気をつけてほしいことは、怒りの相手に対する悪口になってしまうようなものは使わないようにしましょう。
もっと怒りが増してしまいます。
イメージの力を活用する
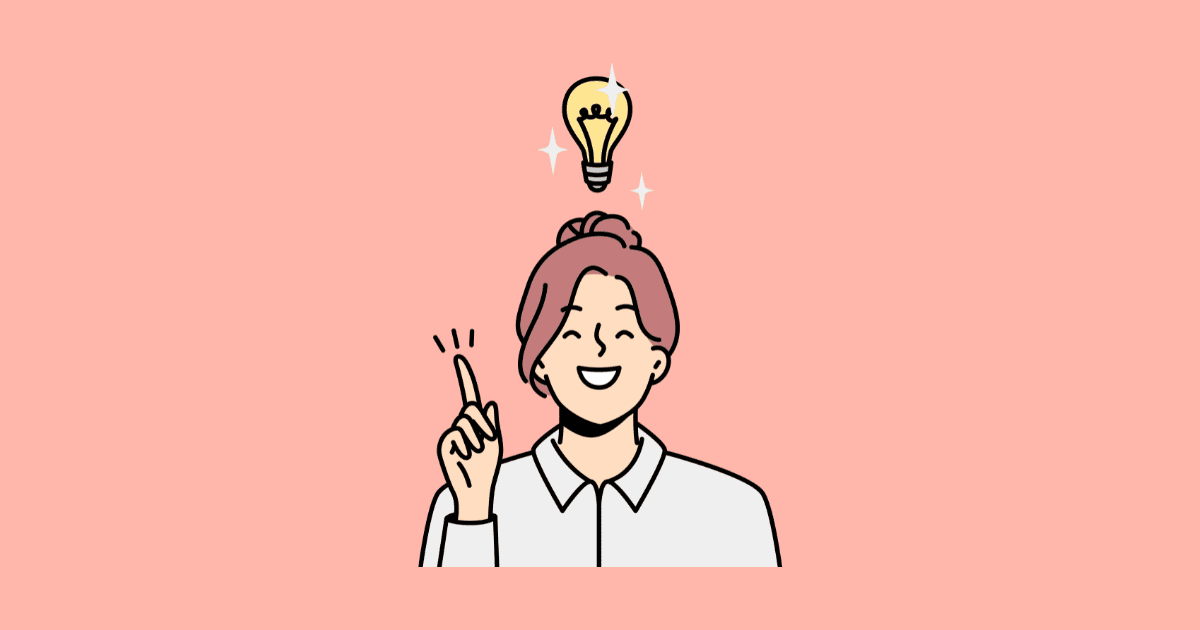
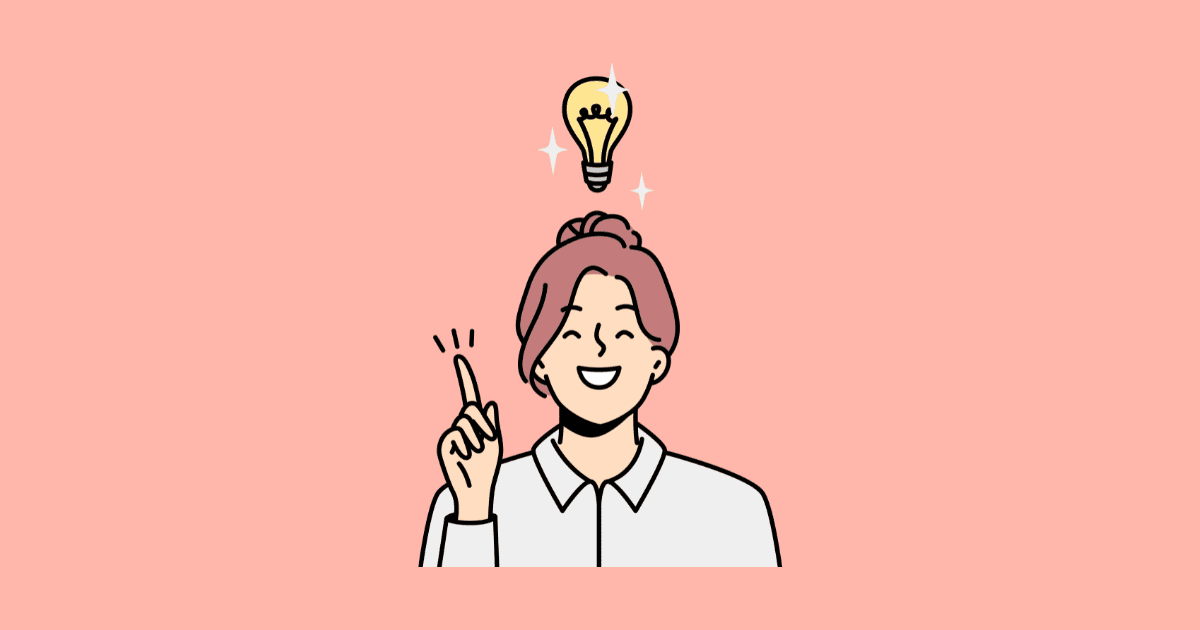
4つ目は、「イメージの力を活用する」方法です。
怒りは、生理的な反応のように即座に起こるものではありません。
怒りは、思考によって出来事を「意味づけ」したときに生まれるものです。
したがって、いったん思考を止め、ネガティブな「意味づけ」ができない状態を作れば、怒りの爆発を防ぐことができます。
強い怒りを感じたら、とにかく頭の中で「ストップ」と叫んでみましょう。
そして頭を空っぽにするために、白い紙をイメージしましょう。
このときのコツは、怒りの原因や問題を分析しないで、解決方法なども一切考えないことです。
そうすることで、思考回路が遮断され、出来事への「意味づけ」が止まります。
「意味づけ」をしなければ、目の前のことは「ただの出来事」に過ぎません。
怒る理由はなくなります。
「出来事→思考→感情」の流れは、認知行動療法の考え方に近いものです。
認知行動療法については、次の記事を参考にしてください。
タイムアウトを取る
5つ目は、「タイムアウトを取る」方法です。
相手に対して強い怒りが生じてしまっているときには、その場をいったん離れるのが得策です。
怒りに火をつけた原因から、とりあえず距離をおきましょう。
ただし、その場を離れるときには相手への配慮をすることが必要です。
突然その場を離れたら相手を傷つけたり、怒らせたりしてしまいます。
タイムアウトを取るときには、そのことを相手にはっきりと伝えましょう。



子どもに怒ったときに離れるときも、きちんと伝えてから離れましょう。
タイムアウト中は、とにかくクールダウンしてリラックスすることが一番です。
気持ちいい瞬間を想像する
6つ目は、「気持ちいい瞬間を想像する」方法です。
しつこい怒りの炎を消すためには、怒りの原因となった出来事や人物を、できるだけ思い出さないようにすることです。
思い出す時間を1分でも1秒でも減らすことを心掛けましょう。
ベストの方法は、怒りとは反対の「最高に気持ちいい瞬間」を思い出すことです。
ボーリングでストライクが決まった瞬間、絶景を見て思わず息を飲んだ瞬間、大好物の味と香りを感じた瞬間などです。
思い出すのは、こうした「瞬間」が良いです。
スッキリした、ハッとした、グッときた「瞬間」を切り取って思い出すことが大切です。
こういうものを思い出すことで、心の中をプラスの感情で埋め尽くせば、マイナスの怒りの感情を追い払えます。



自分にとって「気持ちいい!」瞬間をためておきましょう。
「今ここ」に集中する
例えば、物を食べているときに怒りの気持ちが高まってきたら、目の前の料理を味わうことだけに感覚を集中してみましょう。
今食べようとしているのは料理はなんでしょうか。
箸で掴んだときの重さや感触は、どのような物でしょうか。
口に入れた瞬間、どのような感じがしたでしょうか。
咀嚼したとき、口の中でどのように崩れたでしょうか。
ゆっくりと丁寧に味わいながら、食事をするという動作だけに意識を向けます。
すると、やがて怒りが小さくなっていくのがわかります。
自分がとっている行動を、心の中で「実況中継」するのも効果的です。



「今ここ」に集中すれば、無駄な怒りは減らせます。
「今ここ」に集中する方法としては、マインドフルネスが有名です。
子育ての方向けのマインドフルネスに関しては、次の記事を参考にしてください。
まとめ
今回は、アンガーマネジメントで「とっさの怒り」に対処する方法について説明しました。
アンガーマネジメントスキルを身に付ければ、子どものわがままで怒ったりイライラしたりしても、感情的にならずに上手に接することができるようになります。
今回は主に対処療法としての話でしたが、日頃から怒りにくくするための体質づくりも大切です。
アンガーマネジメントで怒りに流されないコツと習慣を身に付ける方法については、次の記事を参照してください。
また、アンガーマネジメントを子育てに活かす方法については次の記事も参考にしてください。
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
にほんブログ村