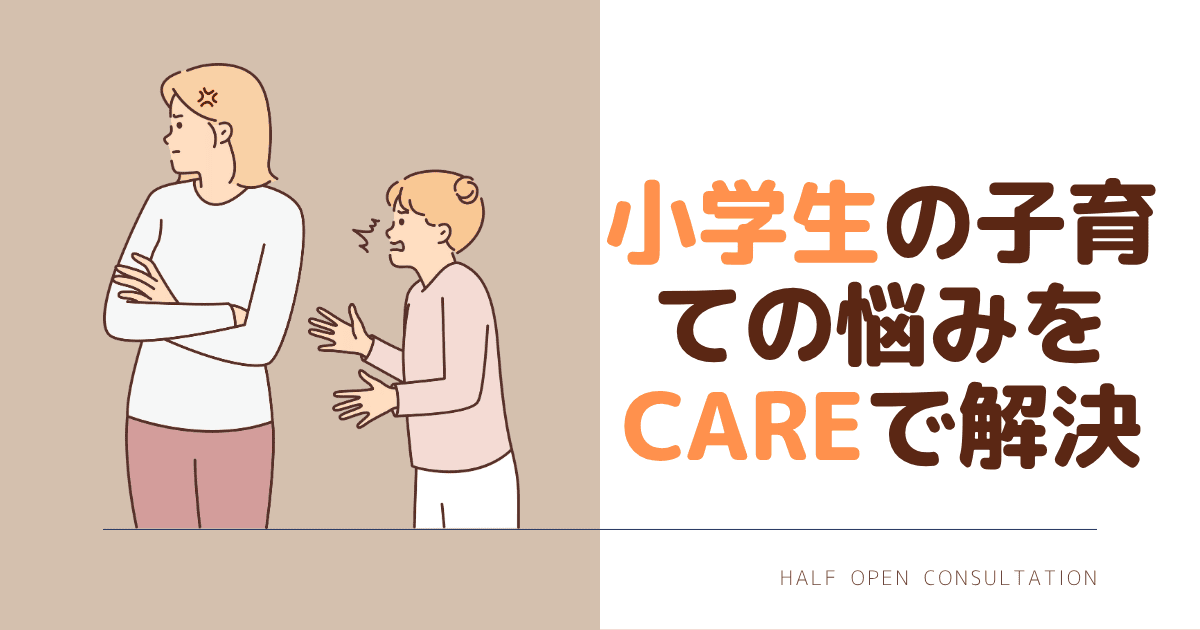お子さんが小学生くらいになると、子育てが難しくなってきたなと感じることありませんか?
「言うことを聞かない」「感情の起伏が激しい」「学校のことを話してくれない」など、小学生になると子どもの行動や心の動きが複雑になり、親としてどう関わればいいのか迷うことが増えてきます。
そんな時に役立つのが、子どもへの接し方のスキルを身につけるための「CARE(ケア)」です。
CAREは、専門的なスキルがなくても取り入れやすく、親の関わり方を少し工夫することで、子どもの安心感や信頼感を育て、問題行動の予防や改善につながります。
この記事では、CAREの基本から、小学生の子育てにどう活かせるのか、具体的な関わり方まで、わかりやすく紹介していきます。
- 小学生の子育てに悩んでいる共働き家庭の親御さん
- 子どもの反抗や問題行動に戸惑っている保護者
- 子どもとの関係を見直したいと感じている方
なぜ小学生の子育ては悩みが増えるのか?
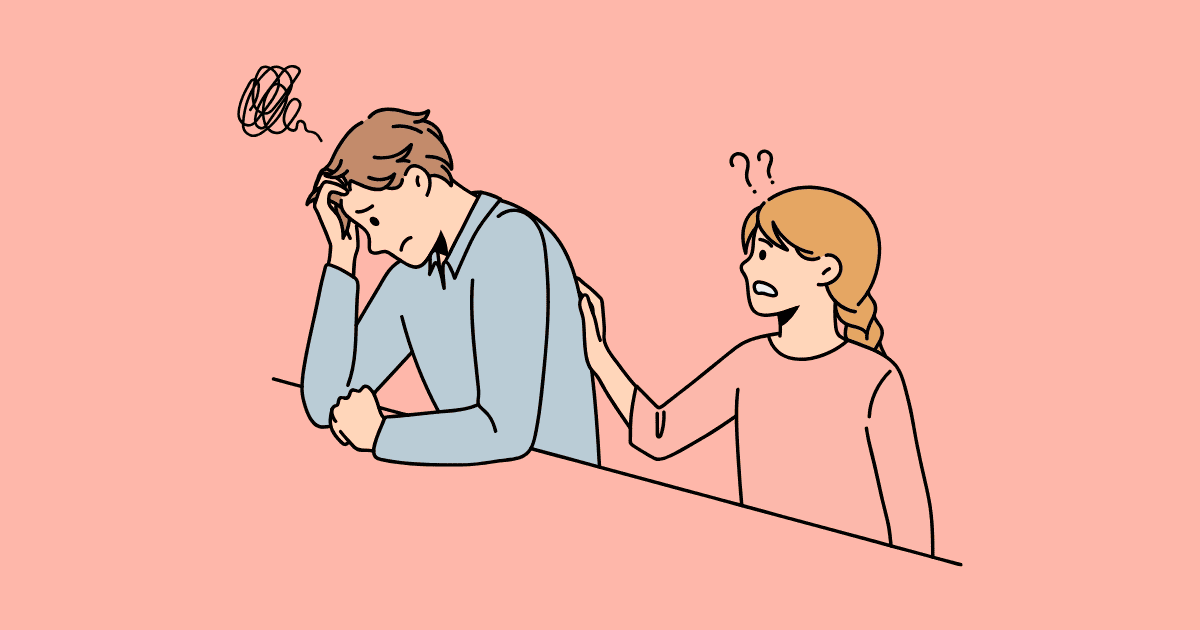
小学生になると、子どもの行動や心の動きが大きく変化します。
「前は素直だったのに…」「なぜ急に反抗的に?」と、戸惑うことも多いのではないでしょうか。
成長に伴って自立心が芽生えたり、学校生活の影響を受けたりして、親子の関係にも新たな課題が生まれてきます。
ここでは、小学生の子育てで悩みが増える背景について、よくある3つの視点から解説します。
■心と行動のギャップに戸惑う親たち
小学生になると、自分の本当の気持ちを隠して、表面的に明るく振る舞うようなことができるようになってきます。
そのため、表面的には楽しそうに振る舞っていても、内面ではイライラや不安があり、ちょっとしたことでイライラした態度を取ったり、きょうだいにあたったりするかもしれません。
こうした“心と行動のズレ”に対して、親は「子どもの本当の気持ちがわからない」と困惑します。
行動の裏にある子どもの気持ちを汲み取ることができなければ、親は子どもに対して適切な対応ができなくなってしまいます。
■親の期待と現実のズレ
親として「きちんと勉強してほしい」「友達とうまくやってほしい」という願いは自然なことです。
しかし、子どもが思いどおりに動かない現実に直面すると、イライラしたり不安になったりしてしまいます。
さらに「○○くんはできているのに…」と他の子と比べてしまうと、親の期待がプレッシャーとなり、子どもが自信を失うこともあります。
子どものペースや得意・不得意を受け入れ、成長を見守る姿勢が重要になります。
■学校生活がもたらすストレス
小学生になると、家庭では見えにくい学校生活のストレスを抱えるようになります。
友達とのトラブル、先生との相性、宿題の多さや授業の難しさなど、子どもなりの“社会生活”が始まるのです。
しかし、子どもはそれをうまく言葉にできず、態度や行動で表現することが多いため、親には「わがまま」「反抗的」に見えることもあります。
子どもの不調サインに気づき、「安心して話せる時間と場」を作ることができるかどうかが鍵となります。
CAREとは何か?子育てにどう活かせる?
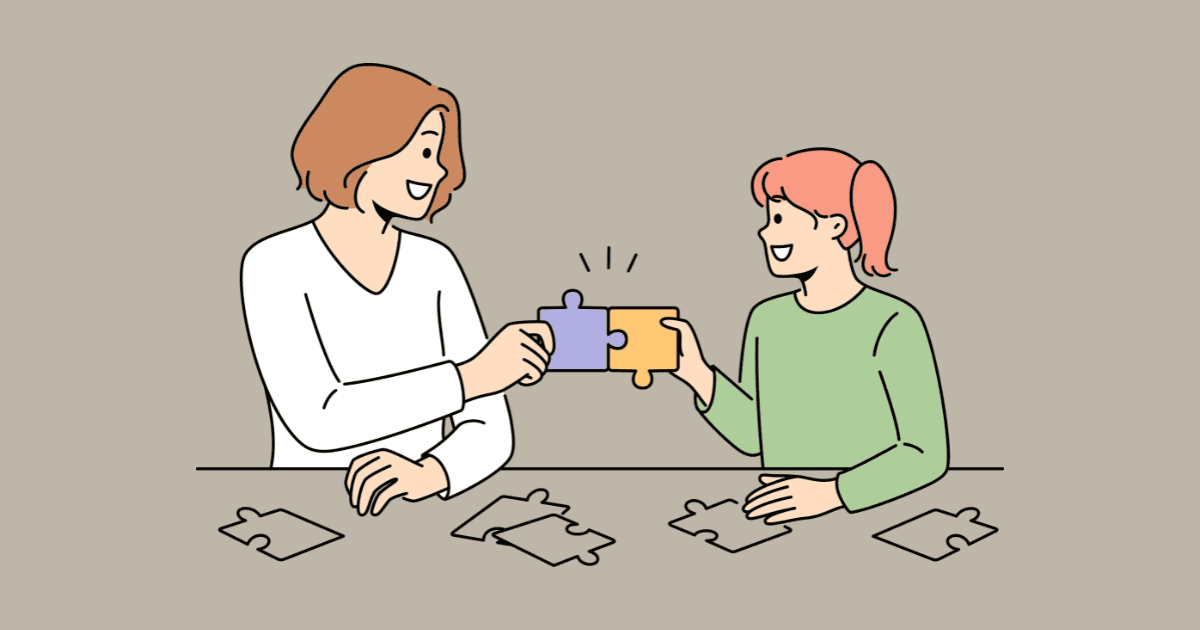
「怒りたくないのに、つい叱ってしまう…」「子どもとの関係がギクシャクしている」そんなときに役立つのが、親子関係を深める心理的アプローチ「CARE」です。
CAREは、特別な資格や専門知識がなくても大丈夫。
日常の関わりの中で取り入れることができる関係性中心の支援方法です。
この章では、CAREの基本的な考え方や、なぜ小学生の子育てに適しているのかをご紹介します。
CAREの基本理念を知ろう
CARE(Child-Adult Relationship Enhancement)とは、
「親子の絆を強めること」
を目的とした心理的アプローチです。
アメリカの心理士によって開発されたものです。
子どもの行動を変えるのではなく、「大人の関わり方を変える」ことを重視しています。
具体的には、子どもの気持ちに寄り添い、共感しながら関係性を築くことで、子ども自身が安心感を持ち、自然と落ち着いていくことを目指します。
親子の信頼関係が深まることで、行動や感情にも良い変化が見られるようになります。
親の接し方が子どもの心に与える影響
親の声かけや態度は、子どもの自己評価や感情の安定に大きな影響を与えます。
「なんでできないの?」「早くして!」といった言葉がけは、ときに子どもの気持ちを傷つけてしまいます。
一方で、「よく頑張ったね」「うまくいかなくても大丈夫だよ」といった肯定的な声掛けは、子どもの安心感や自己肯定感を高めます。
CAREは、親が子どもの内面に目を向け、否定よりも肯定を大切にする関わり方を具体的に学ぶことができます。
小学生の子育てに適している理由
小学生は、思春期の入り口に向かう大事な時期です。
言葉では「大丈夫」と言っても、内心では不安や混乱を抱えていることも多くあります。
そんな時期の子どもには、「言葉で説明しよう」とするよりも、「気持ちをわかってくれる大人」がそばにいることが大切です。
CAREは、共感や受容を通して子どもの心を支える関わり方なので、感情が不安定になりやすい小学生期にぴったりのアプローチです。
親子関係の土台づくりとしても効果的です。
CAREを使った実践的コミュニケーション術
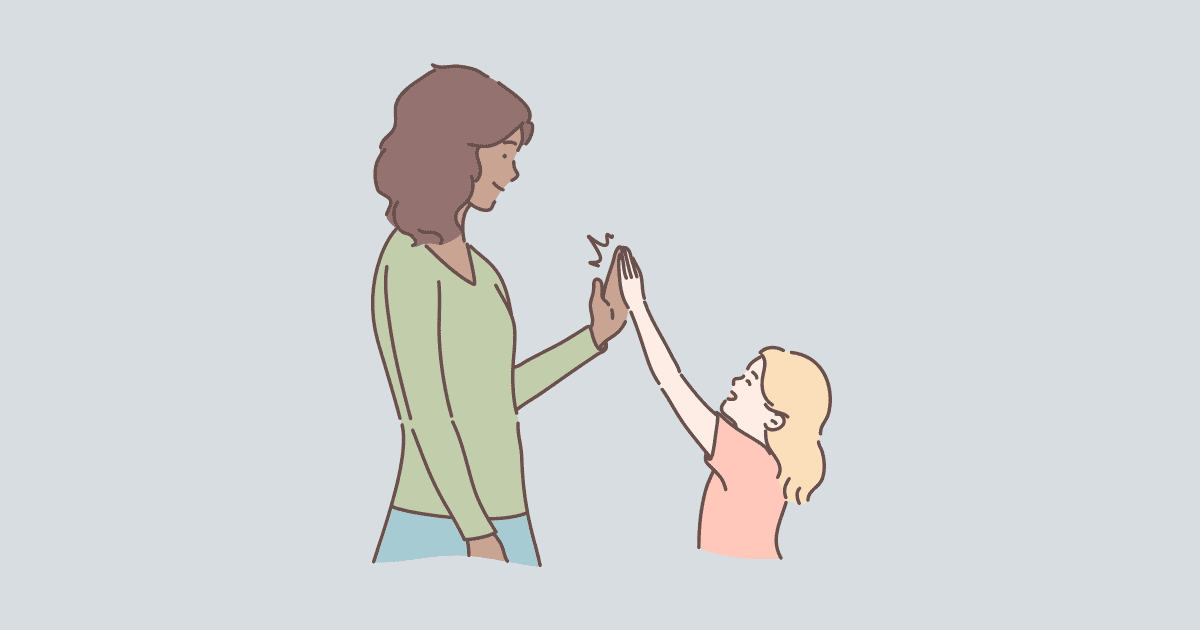
CAREの考え方を理解したら、次は日常の中でどう活かすかがポイントです。
難しいことをしなくても、声かけや聞き方を少し変えるだけで、子どもとの関係がぐっと良くなります。
こでは、CAREで大切にされている「観察」「共感」「肯定的な関わり方」などをもとに、今日から実践できるコミュニケーションのコツを紹介します。
イライラを減らし、親子の信頼関係を育むためのヒントをぜひ取り入れてみてください。
「観察」と「共感」の力を高める方法
CAREでは、まず子どもを「よく観る」ことが大切だとされています。
例えば、子どもが何らかの問題行動を起こしたときには、今どんな気持ちでその行動をしているのかを見極めることで、感情的な対応を防ぐことができます。
その際、否定的な言葉かけをグッと堪えて、子どもの気持ちに寄り添って「どうしたのかな?」「ちょっと疲れてる?」といった声かけをすることで、子どもは「わかってくれてる」と安心できます。
子どもの表情や態度から気持ちをくみ取る力は、練習によって少しずつ身につけることができます。
観察と共感は、CAREの土台と言えます。
褒め方のコツと注意点
褒めることは子育てにおいてとても大切ですが、ただ「すごいね」「えらいね」と言うだけでは、うまく伝わらないこともあります。
CAREでは、子どもの行動の「内容」や「努力の過程」に注目して褒めることを大切にしています。
たとえば、「最後までやり切ったね」「自分から始めたのがよかったね」といった具体的な声かけをして褒めることが効果的です。
ポイントは、結果ではなく姿勢や工夫を見つけて伝えること。これが自己肯定感の土台になります。
困った行動への対応の工夫
子どもが癇癪を起こしたり、言うことを聞かなかったりすると、つい大声で叱ってしまいがちです。
しかし、感情的な対応では関係が悪化し、同じ行動が繰り返されることもあります。
CAREでは、まず落ち着いた声で子どもの気持ちに寄り添い、「どうしたのか教えてくれる?」と聞くことが基本です。
そのうえで、望ましい行動を丁寧に伝えることで、子どもは安心し、自分で考えて行動する力を身につけていきます。
叱るより、聞いて次の行動を促す姿勢が大切です。
悩みを抱える前に取り入れたいCARE的習慣
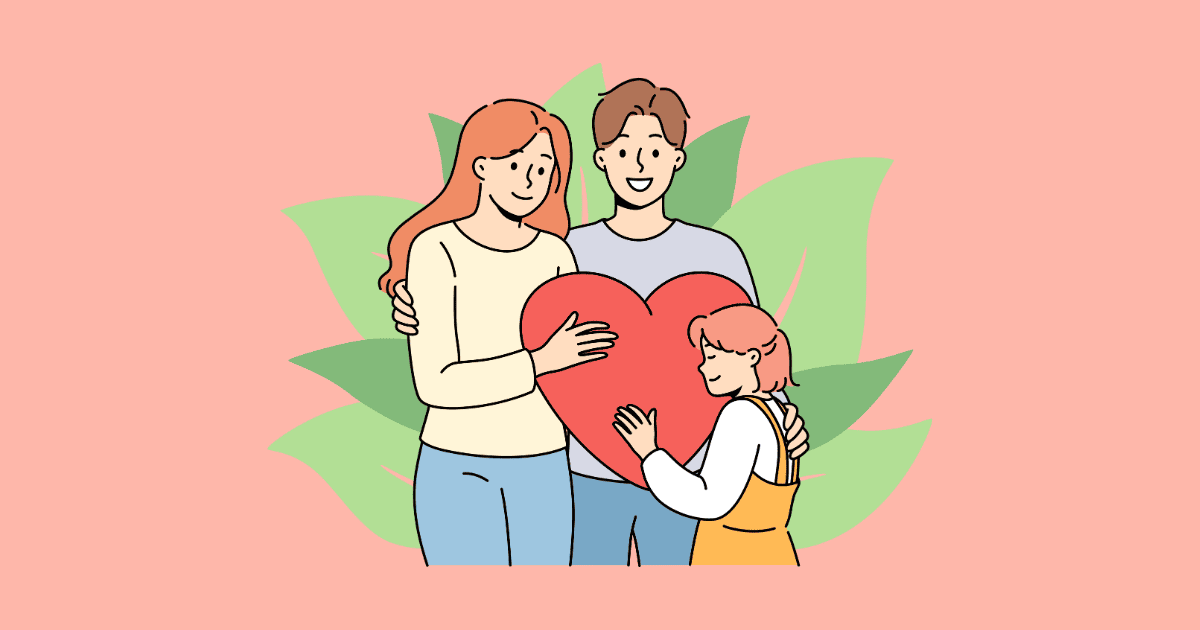
子育ての悩みが大きくなる前に、日常の中でできる「ちょっとした工夫」を取り入れておくことがとても大切です。
CAREの考え方は、特別なときだけでなく、普段の親子の関わりにこそ力を発揮します。
ここでは、親子関係を安定させ、悩みを未然に防ぐためのCARE的な習慣を紹介します。
少しずつでも取り入れることで、子どもが安心できる土台が育ち、親自身もゆとりを持って子育てに向き合えるようになります。
■1日10分のスペシャルタイムをつくる
CAREでは、「親子だけの安心できる時間」(スペシャルタイム)を意識的につくることが勧められています。
1日たった10分でも、テレビやスマホを置いて、子どもと一緒に遊んだり話したりする時間をとることで、子どもは「自分を大切にしてくれている」と感じます。
この時間は指示や注意をするのではなく、子どものやりたいことに寄り添うのがポイントです。
特別なことは必要ありません。
積み重ねることで、信頼関係がぐっと深まります。
親自身の心の余裕を大切にする
子育てがうまくいかないとき、「自分が悪いのでは?」と自分を責めてしまう親は少なくありません。
しかし、親にも感情や気持ちの限界があります。
CAREでは、まず親自身が自分の感情に気づき、無理をしないことが大切だとされています。
- 疲れているときはゆっくり休む
- イライラしたら深呼吸をする
- 誰かに話を聞いてもらう
こうした小さなセルフケアが、子どもと向き合う力になります。「頑張りすぎない」ことも、立派な子育てです。
セルフケアのコツについては次の記事で触れているので参考にしてください。
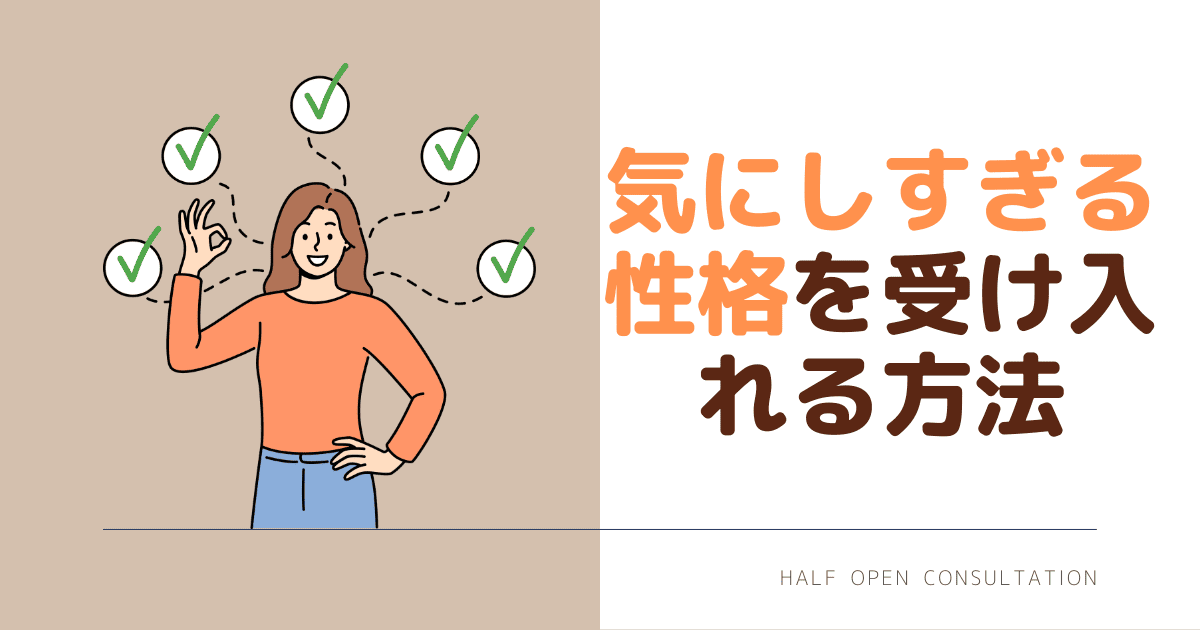
困ったときは相談できる場所を持つ
子育ては一人で抱え込むものではありません。
どうしてもうまくいかないとき、周囲に相談できる場所があることは大きな安心につながります。
CAREはカウンセリングの場でも取り入れられており、オンラインでも気軽に相談できるサービスが増えています。
- ちょっと話を聞いてほしい
- 関わり方のヒントが欲しい
- 誰にも相談できる人がいない
そんなときは、プロの力を借りるのもひとつの選択肢です。
親子関係をよりよくするために、安心して支援を活用していきましょう。
おすすめのオンラインカウンセリングサイトは次の記事を参考にしてください。
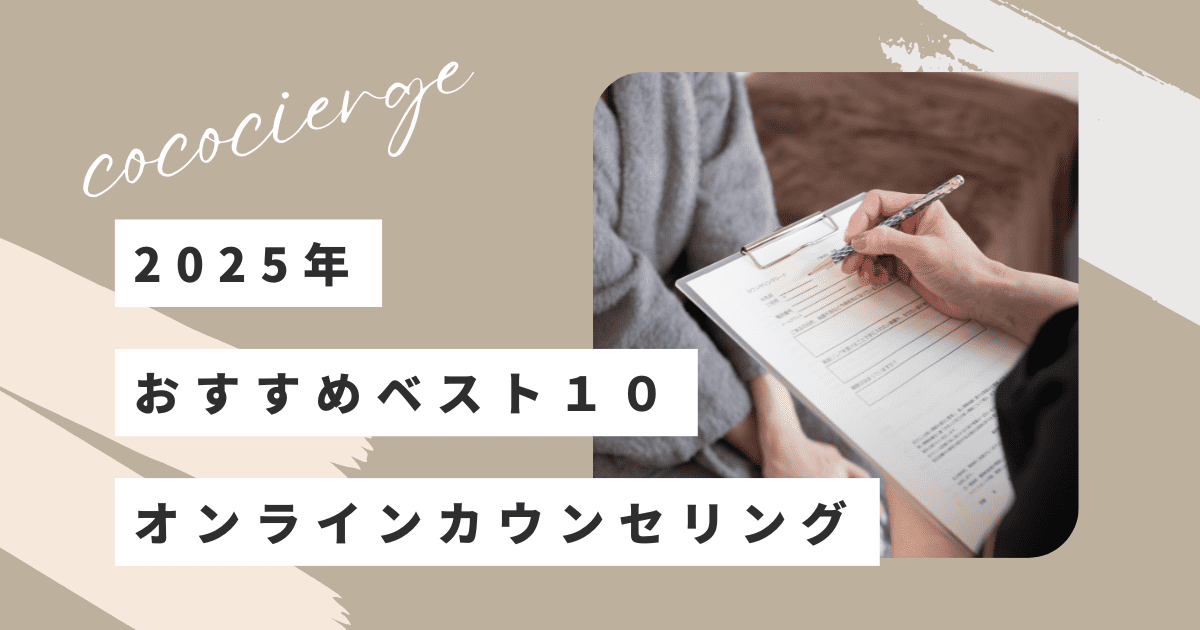
まとめ
今回は、CAREの基本から、小学生の子育てにどう活かせるのか、具体的な関わり方まで解説しました。
子育ては、親にとっても成長の連続です。
小学生になると、子どもは一人の人間としての自我を強め、親の思いどおりには動かなくなってきます。
そんなときこそ、子どもの心に寄り添い、信頼関係を育てる関わりが大切です。
CAREは、親が「何を言うか」よりも「どう関わるか」に焦点を当てたアプローチです。
特別な技術や知識がなくても、日常の中で少し意識を変えるだけで、親子の関係に大きな変化をもたらします。
CAREを通じて、親子の関係を改善しましょう!
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。