「学校に行きたくない」と子どもが言ったとき、親としてどう受け止めるべきか悩んでしまうでしょう?
「甘えているのでは?」「ずるいのでは?」と感じることもあるかもしれません。
しかし、不登校は単なるわがままではなく、子どもなりの理由や背景があります。
本記事では、不登校のきっかけや「ずるい」と感じてしまう親の心理を整理し、どう向き合えばよいのかを解説します。
- 不登校の子どもに「学校に行かないのはずるいのでは?」と感じている方
- 子どもが不登校になり、「どう接したらいいのか」「親として何ができるのか」悩んでいる方
- 不登校の子どもと接する中で、自分の気持ちが揺れ動いてしまい、罪悪感や焦りを感じている方
 ゆう
ゆう親子の関係を大切にしながら、子どもが前を向くためのサポート方法を一緒に考えていきましょう。
不登校のきっかけ


不登校のきっかけは子どもによってさまざまです。
よくある例として、以下のようなものが挙げられます。
- 体調不良や精神的な負担(起立性調節障害、うつ状態、HSP傾向)
- 学校での人間関係の問題(いじめ、友人とのトラブル、教師との相性)
- 学業のプレッシャー(成績不振、勉強についていけない不安)
- 家庭環境の変化(親の離婚、引っ越し、家族との関係の悪化)
こうしたきっかけや出来事があればわかりやすいのですが、そうしたきっかけが思い当たらない場合もあると思います。
そこで、この記事ではきっかけを次の3つに整理して説明します。
- 心理的きっかけ
- 現実的きっかけ
- 意識的きっかけ



この分け方は、丸山康彦氏の書籍「不登校・ひきこもりが終わるとき」を参考にしています。
心理的きっかけ
明確な理由がわからないまま、学校に登校する気力が失われていくものです。
親としては、明確な理由がないため、どのように理解すれば良いのかわからず困惑しがちです。
こうしたお子さんは、後になって不登校をしていたことについて「生き方が変わった」などと述べることも少なくないようです。
「人格形成の一段階」という意味を持っていると理解すると良いかもしれません。
現実的きっかけ
目で見えるものが多く、身近な大人にとって理解しやすいものです。
教室や部活動でのトラブル、いじめや体罰、学業成績の不良などを体験して傷ついたことがきっかけになるものです。
学校だけでなく、家庭環境の変化などもきっかけになります。
「そのような環境からの避難」という意味を持っていると理解することもできます。
意識的きっかけ
学校の雰囲気が合わない、つまり学校そのものへの違和感が意識されたことがきっかけになるものです。
「学校の価値観やシステムに欠けている要素への異議申し立て」あるいは「学校以外の道への渇望」などの意味を持っていると理解することができます。
「ずるい」と感じる親の本音
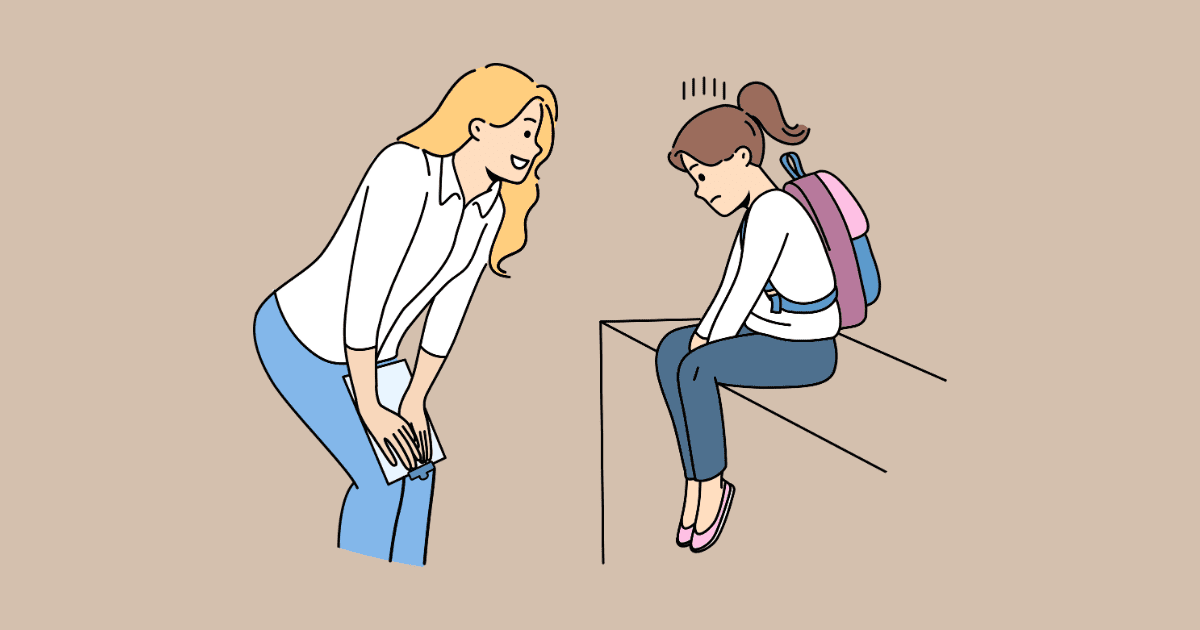
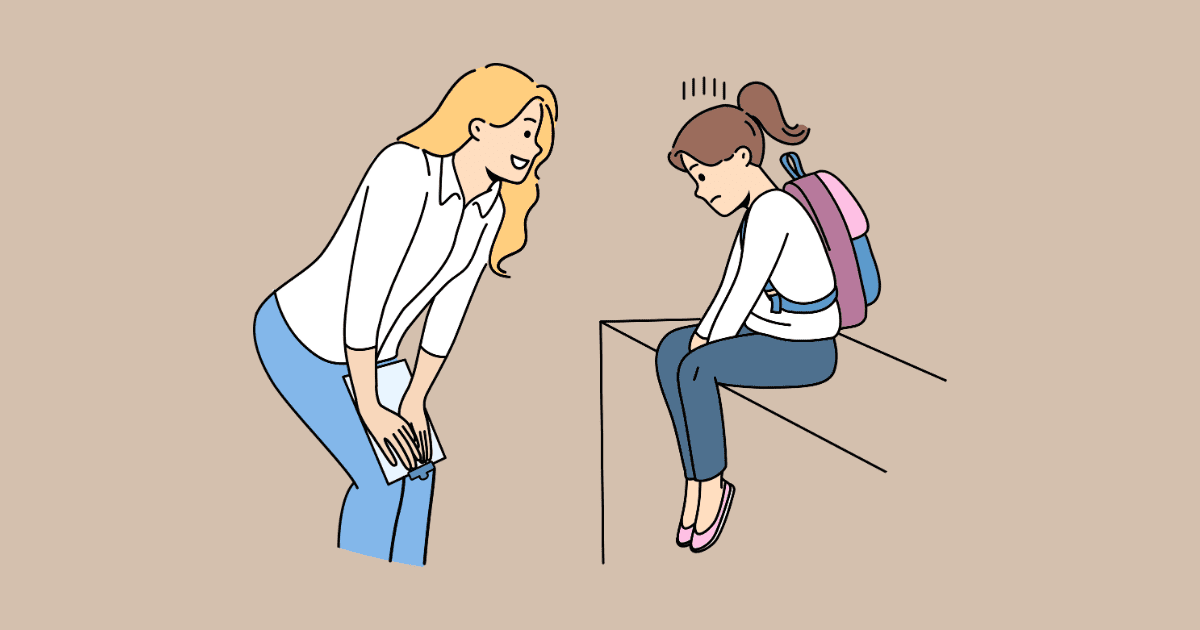
子どもが不登校や登校しぶりになり、時間が経っていくると、徐々に子どもは暇になっていきます。
子どもは、たとえ暇になったとしても勉強するだけの意欲や頑張りは高まらないため、スマホやゲームばかりするようになることが多いです。
すると、親としては次のように感じるかもしれません。
- 「自分はどんなにつらくても学校に行っていたのに…」
- 「このままだと将来が心配…」
- 「他の子は頑張っているのに…」
こうした気持ちの背景には、「学校に行くのが当たり前」という価値観や、子どもの将来への不安があります。
しかし、親が「ずるい」と思うことで、子どもに「自分はダメな人間なんだ」と思わせてしまうこともあります。
まずは、自分の感情を冷静に見つめ、「なぜそう感じるのか」を整理することが大切です。
自分と子どもを比べてしまう
親世代の多くは、「多少つらくても学校には行くべき」という価値観で育っています。
そのため、「自分はどんなに嫌でも学校に行ったのに」「逃げているだけでは?」と考えてしまいがちです。
今は、時代が変わり、学校の環境も子どもたちのストレス要因も多様化しています。
親が「自分の経験」を基準に考えると、子どもの本当の気持ちを見落としてしまいます。
大切なのは、子どもを責めるのではなく、「この子にとって何が必要か」を考えることです。
先の見えない不安
「このまま学校に行かなかったら、将来どうなるの?」という不安は、多くの親が抱えるものです。
勉強の遅れ、進学や就職の問題を考えると、焦りが出るのも無理はありません。
しかし、不登校を経験しても、その後自分に合った道を見つけ、社会で活躍している人はたくさんいます。
今は学校がすべてではなく、フリースクールやオンライン学習など、選択肢も増えています。
短期的に登校を再開することを目指すのではなく、長期的に「子どもが安心して学び、成長できる環境」を考えることが大切です。
兄弟や周囲との比較
きょうだいがいる家庭では、「上の子はちゃんと行っているのに」「この子だけ甘えているのでは?」と思うことがあるかもしれません。
また、親戚やママ友からの目が気になり、「どう説明すればいいのか」と悩むこともあります。
しかし、子ども一人ひとりに個性があり、不登校の背景も異なります。
大切なのは、他人と比較せず、「この子自身がどう感じているのか」に目を向けることです。



周囲の目を気にするよりも、子どもの心に寄り添うことが最優先です。
「ずるい」と言われた子どもの気持ち


ここまで、親が子どもに対して「ずるい」と考えてしまう本音について説明しました。
もしも親が、不登校の子に対してその本音を伝えてしまったら、子どもはどう感じるでしょうか?
子どもは好きで不登校になったわけではありません。
多くの子どもは、学校に行けないことを自分でも責めています。
「ずるい」と言われると、「理解してもらえない」と感じ、親子の信頼関係が損なわれてしまうかもしれません。



子どもの気持ちを想像することで、思わず「ずるい」と言ってしまいたい気持ちを抑えることができます。
「行きたくても行けない」苦しさ
不登校の子どもたちは、不登校になった理由はさまざまなですが、多くの場合「学校に行きたいけれど、どうしても行けない。」と感じています。
しかし、それをうまく言葉にできず、家に閉じこもって、場合によってはスマホやゲームばかりしているため、親からは「怠けている」と誤解されてしまいがちです。



スマホやゲームでつらい気持ちを紛らわしています。いずれ学校に行けるようになるためのエネルギーをためている時期です。
そうしたときに、親から「ずるい」と言われてしまうと、子どもは「自分の気持ちを理解してもらえない」、「親も誰も信じられない」と感じ、ますます孤立してしまいます。
「ダメな子」と思い込んでしまう
子どもは、親から「ずるい」と言われると、「自分は努力していない」、「甘えている」と思い込んでしまう子もいます。
特に、真面目で責任感が強い子ほど、「親をがっかりさせた」と感じて、自信を失ってしまいます。
不登校の原因は決して「怠け」ではなく、心のSOSと理解することが大切です。
信頼関係が壊れるリスク
親から「ずるい」と言われ続けると、子どもは親に本音を話さなくなります。
子どもは本当は助けを求めたいのに、親に対して「どうせ分かってもらえない」と感じてしまうのです。
親から否定的な言葉を言われたら、子どもは親を信用できなくなってしまうのは当然です。
親子の信頼関係を守るためには、子どもの気持ちを尊重して、「あなたの気持ちを大事にしたい」という姿勢を伝えることが重要です。
もしも、家庭内での衝突や暴力が強くなっている場合は、別の視点から整理が必要になることもあります。
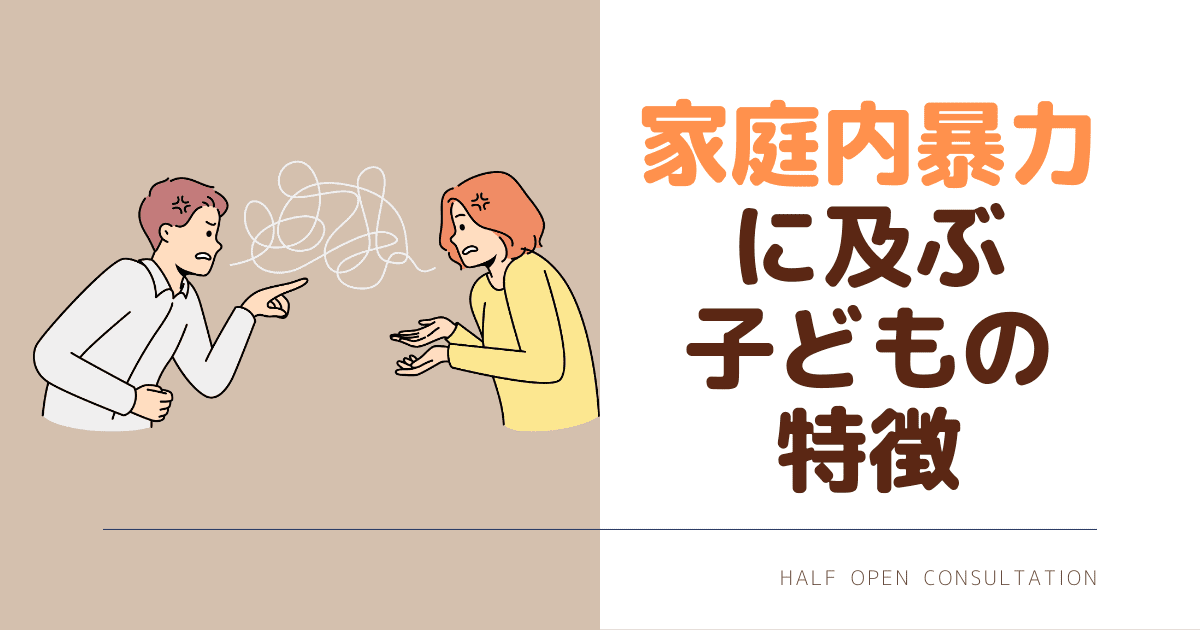
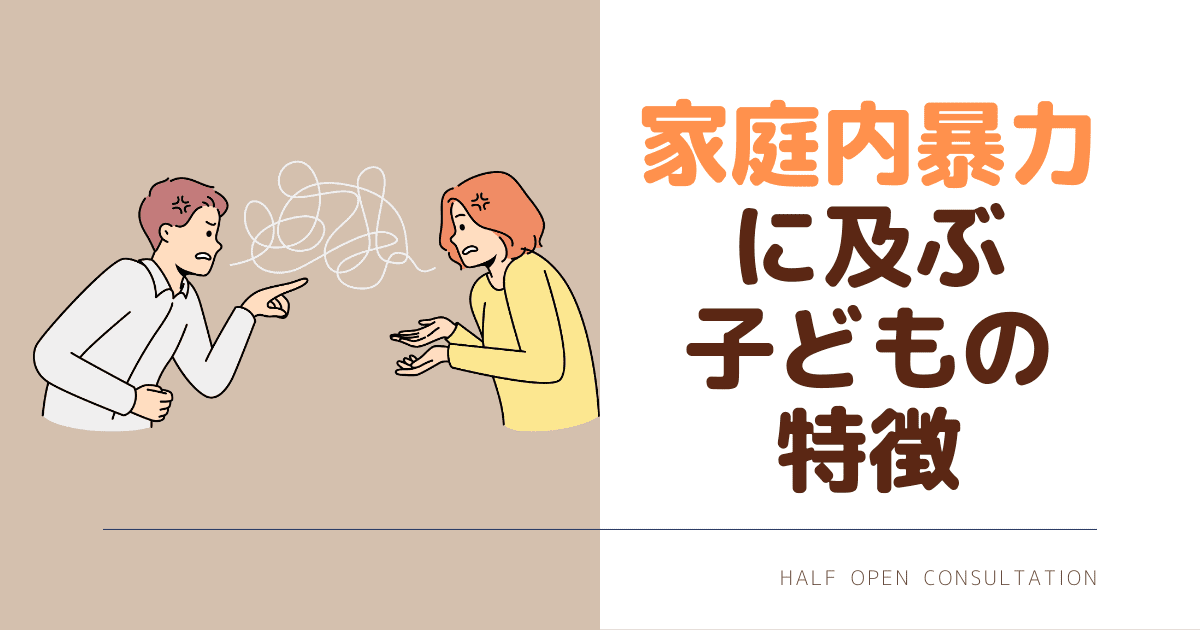
不登校を「ずるい」と思わないために
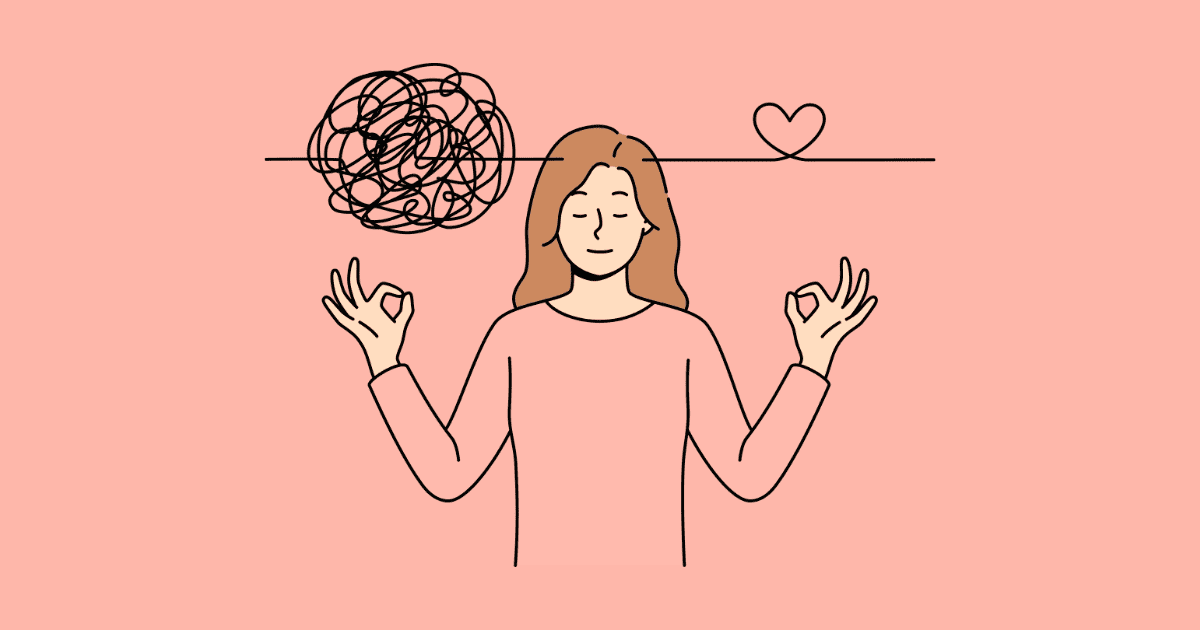
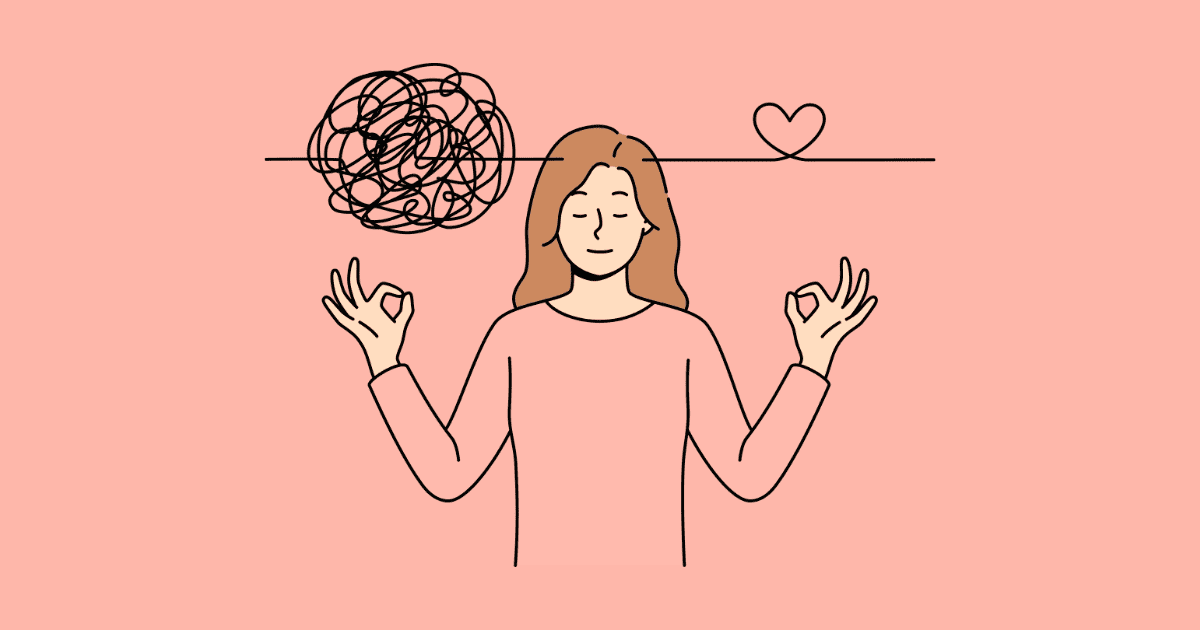
親は子どもの不登校について、「ずるい」と思わないようにするためには、どういう考えや心構えが必要でしょうか?
ポイントとしては、次の3つです。
- 「学校がすべてではない」と考える
- 子どもの気持ちを理解する努力をする
- 親自身の不安を整理し、専門家のサポートを活用する
「学校がすべてではない」と考える
多くの親は「学校に行くのが当たり前」と考えがちです。
しかし、今の時代、学びの場は学校だけではありません。
フリースクール、オンライン学習、ホームスクーリングなど、子どもに合った方法で学ぶことも可能です。
「学校に行けない=人生が終わる」わけではなく、大切なのは「子どもが安心して成長できる環境を見つけること」です。
学校以外の選択肢を知ることで、親自身の気持ちも楽になり、子どもを支える余裕が生まれます。
子どもの気持ちを理解する努力をする
不登校の背景には、子ども自身の複雑な感情が隠れています。
「怠けているわけではなく、何かしらの理由があるはず」と考え、子どもの話に耳を傾けることが大切です。
「どうして行かないの?」と責めるのではなく、「最近どんなことがつらい?」と優しく問いかけるだけでも良いです。
子どもは親に対して「分かってくれようとしている」と感じ、心を開きやすくなります。
親自身の不安を整理し、専門家のサポートを活用する
不登校が長引く子どもに対して、「このままでいいのか」と悩むのは、親として当然のことです。
しかし、その不安を子どもにぶつけてしまうと、逆効果になることも。
親自身もカウンセリングを受けたり、不登校の親の会に参加したりすることで、気持ちを整理し、適切な対応ができるようになります。
「親が笑顔でいること」が、子どもにとって最大の安心材料になります。
不登校の悩み相談については、次の記事が参考になります。


親ができるサポート
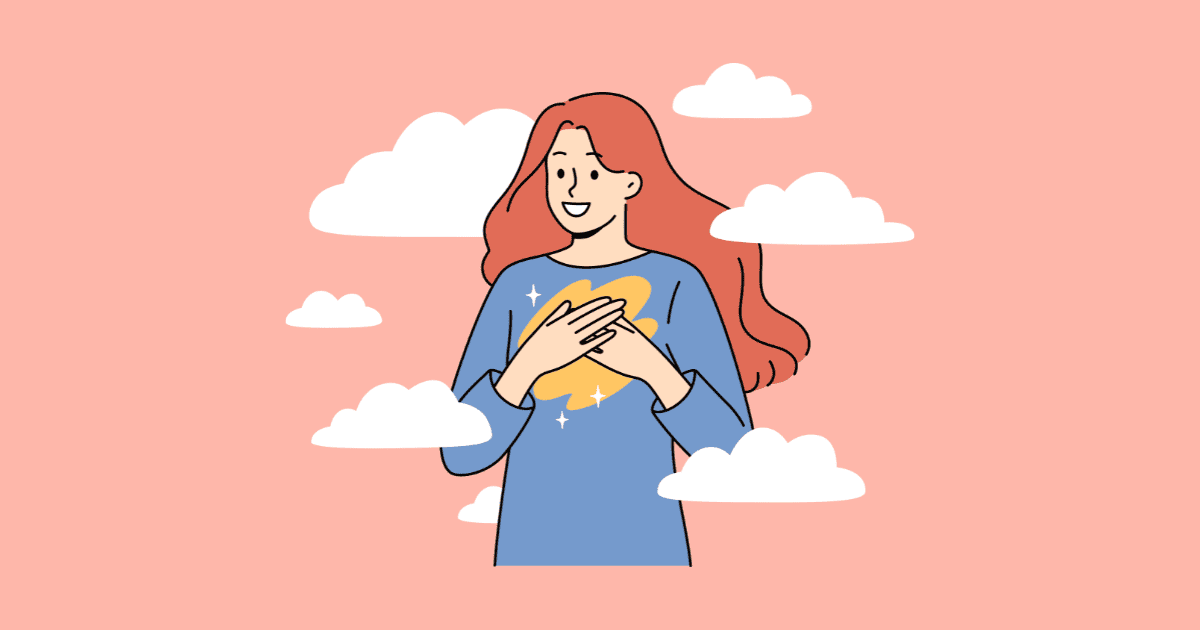
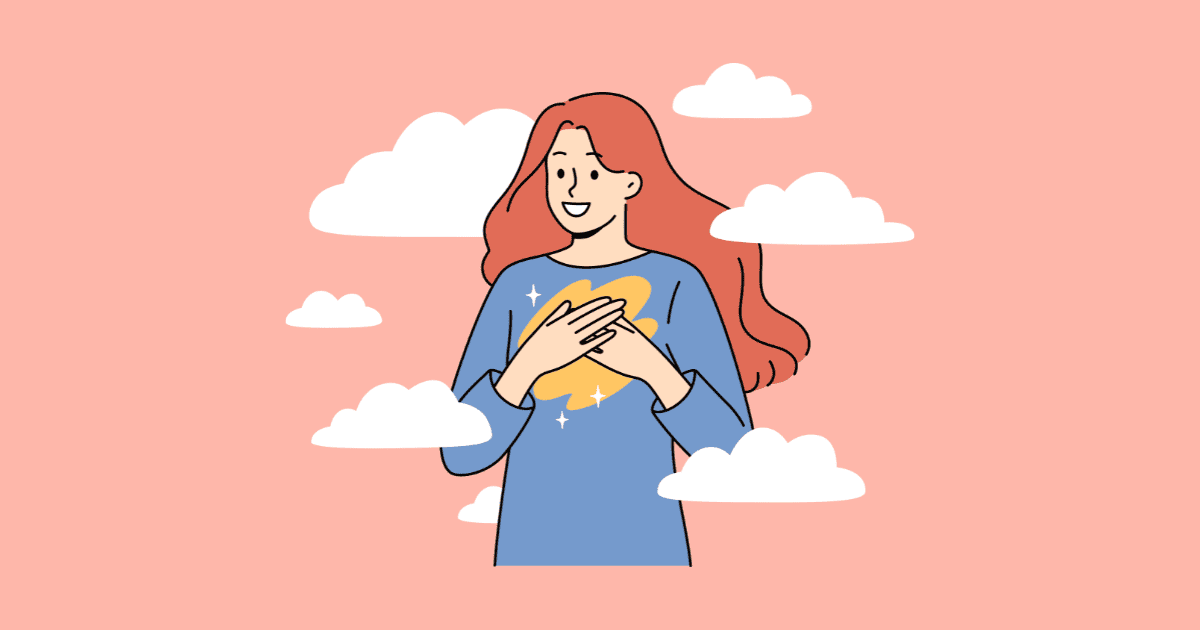
不登校の子どもにとって、親の存在は大きな支えになります。
不登校は決して「ずるさ」ではなく、子どもなりの「SOS」です。
大切なのは、親が「どう対応するか」。
子どもの心に寄り添い、一緒に乗り越えていくことが、未来につながる第一歩になります。



次のことを意識して子どもをサポートしていきましょう。
子どもの話をじっくり聞く
子どもが不登校になると、親はつい「なぜ行かないの?」と理由を知りたくなります。
しかし、子ども自身も「なぜ行けないのか」が分からないことが多いものです。
まずは「今、どんな気持ち?」と問いかけ、子どもが話したくなるタイミングを待つことが大切です。
「無理に話させない」「アドバイスより共感」を意識することで、子どもは「分かってもらえた」と感じ、心を開きやすくなります。
無理に登校を促さず、小さな成功体験を積む
「そろそろ学校に行ったら?」と焦る気持ちは分かりますが、無理に登校を促すと逆効果になりやすいです。
不登校の子どもにとっては、「学校の前まで行けた」「友達とLINEで話せた」などの小さな一歩がとても大切です。
その成功体験を積み重ねることで、「自分もできる」という自信につながります。
必要ならカウンセリングや支援機関を活用する
不登校のサポートには、親だけで抱え込まず、専門家の力を借りることも重要です。
学校のスクールカウンセラー、自治体の教育相談、フリースクールなど、さまざまな支援機関があります。
「どこに相談したらいいか分からない」という場合は、市区町村の教育委員会や不登校支援団体に問い合わせてみると、適切な情報を得ることができます。



不登校に関する相談先については、次の記事が参考になります。
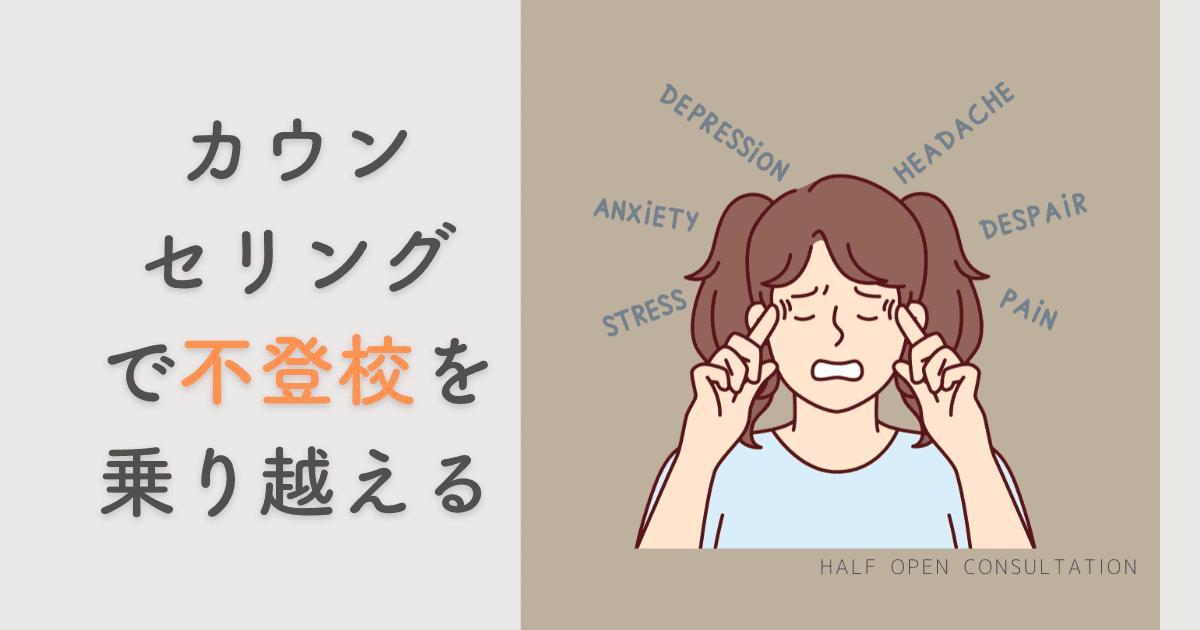
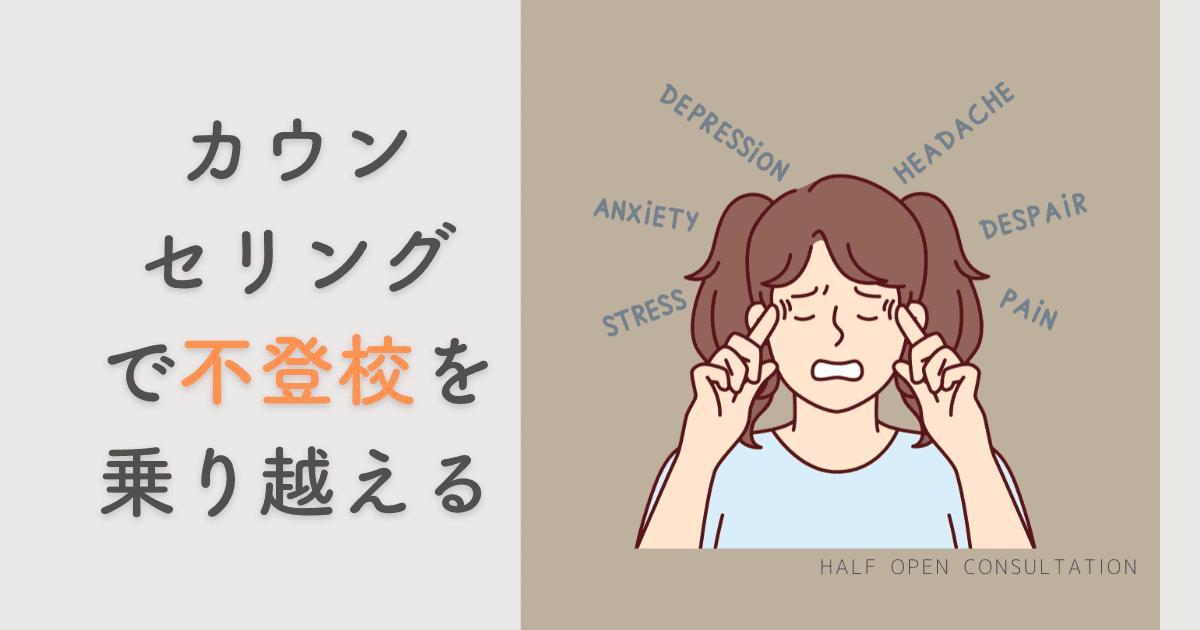
まとめ
今回は、不登校のきっかけや「ずるい」と感じてしまう親の心理を整理し、どう向き合えばよいのかについて解説しました。
不登校は決して「ずるい」ものではなく、子どもが発している大切なサインです。
親が「なぜ学校に行けないのか」を理解し、焦らずサポートすることで、子どもは安心感を得られます。
「学校に行かせること」だけがゴールではなく、子どもの気持ちを尊重しながら、一緒にできることを考えていくことが大切です。
不登校について考えていくと、「子どもをどうするか」だけでなく、親自身がどれだけ気を張り続けてきたかに気づくことも少なくありません。
不登校の悩みを含め、子育ての中で感じやすい迷いや苦しさを一度整理して考えたい方はこちらの記事も参考になります。
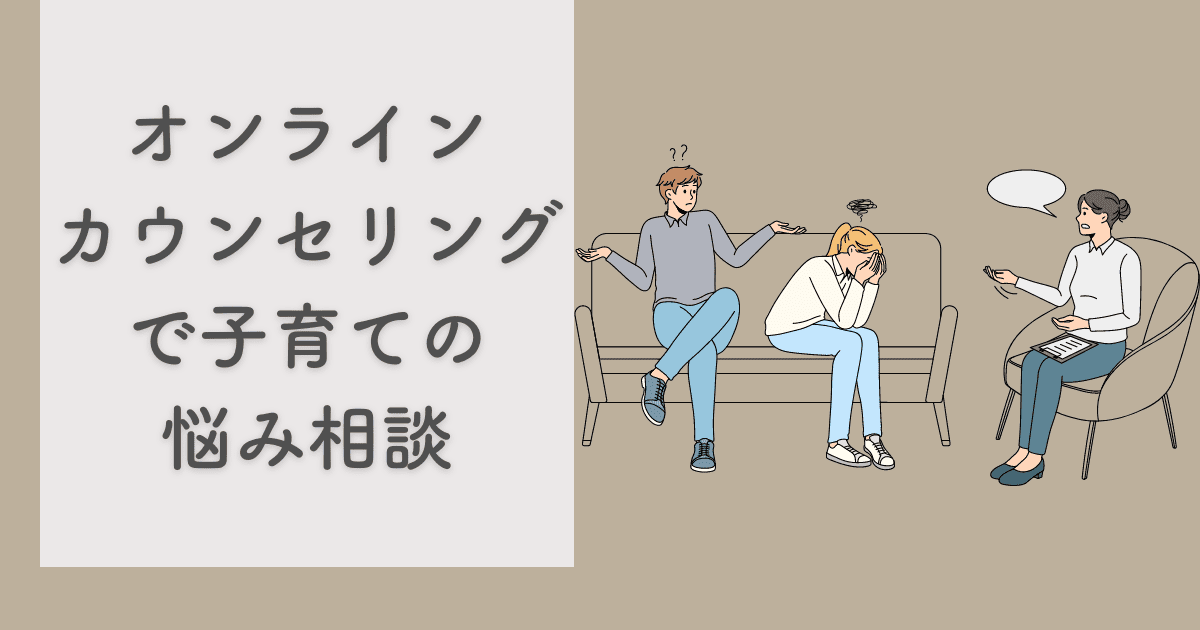
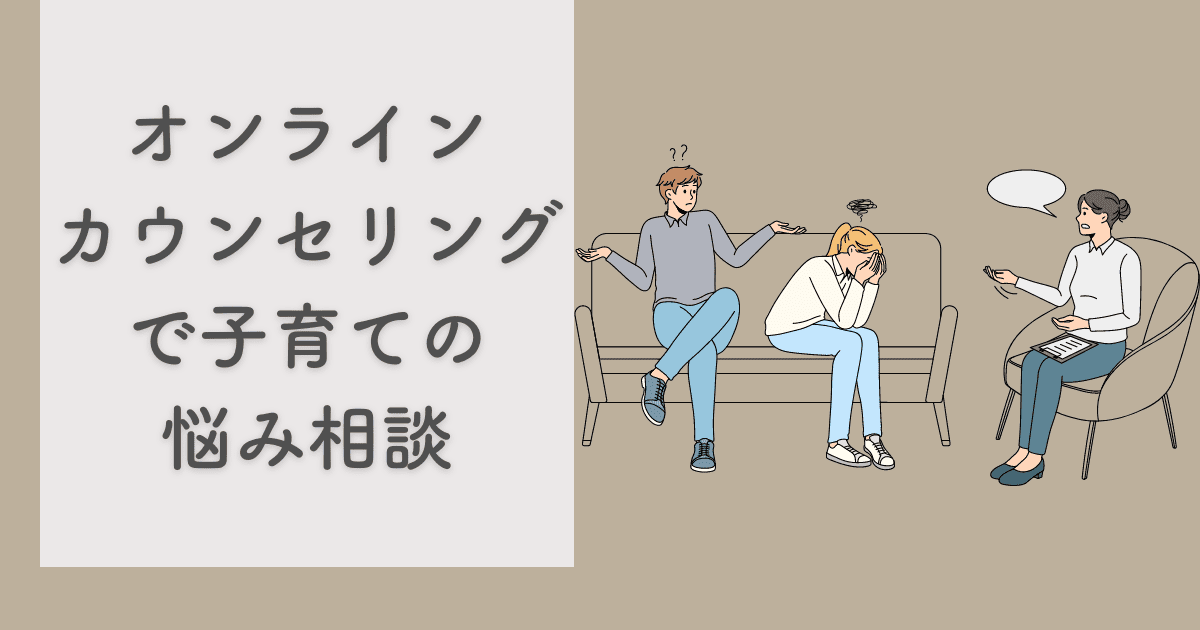
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
にほんブログ村
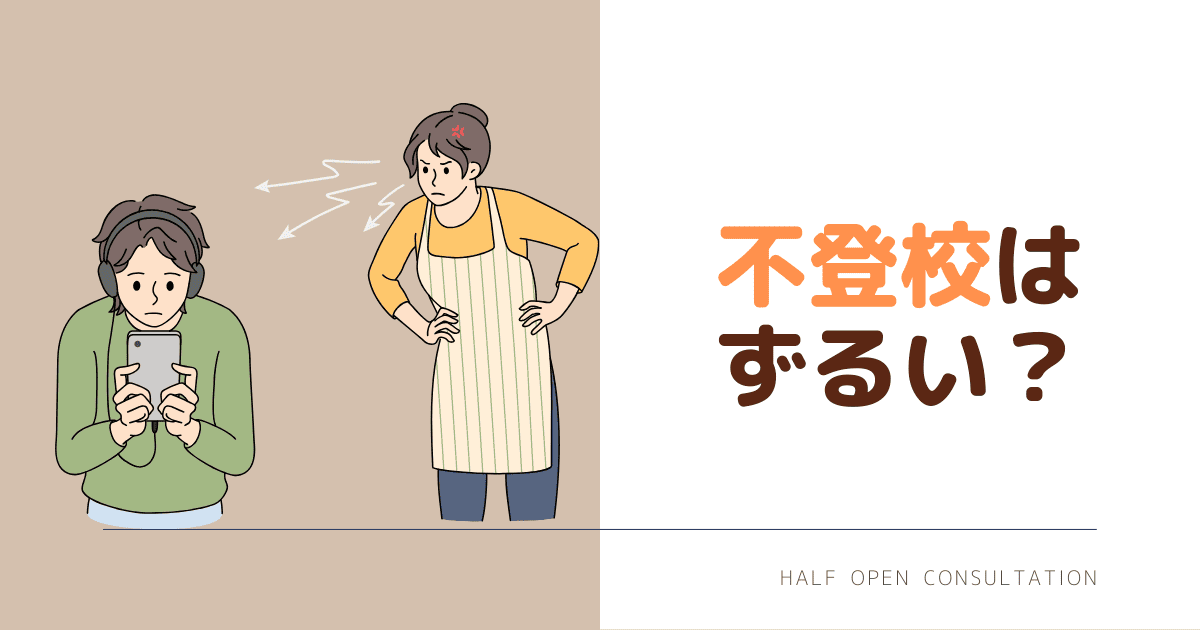

コメント