「うちの子、言葉が遅いかも…」
そんな不安を感じていませんか?
特に3歳頃になると、周囲と比べて言葉の発達に差を感じがちです。
そのため、心配になる親御さんも少なくありません。
そこで、本記事では、子どもの言葉の発達の目安やチェックポイント、家庭でできるサポート方法について、わかりやすくご紹介します。
- 言葉の発達が遅いかもしれないと感じている保護者の方
- 初めての子育てで子どもの発達の目安が分からず不安な方
- 専門機関への相談を検討しているが、一歩を踏み出せない方
言葉の発達の目安と個人差について知ろう
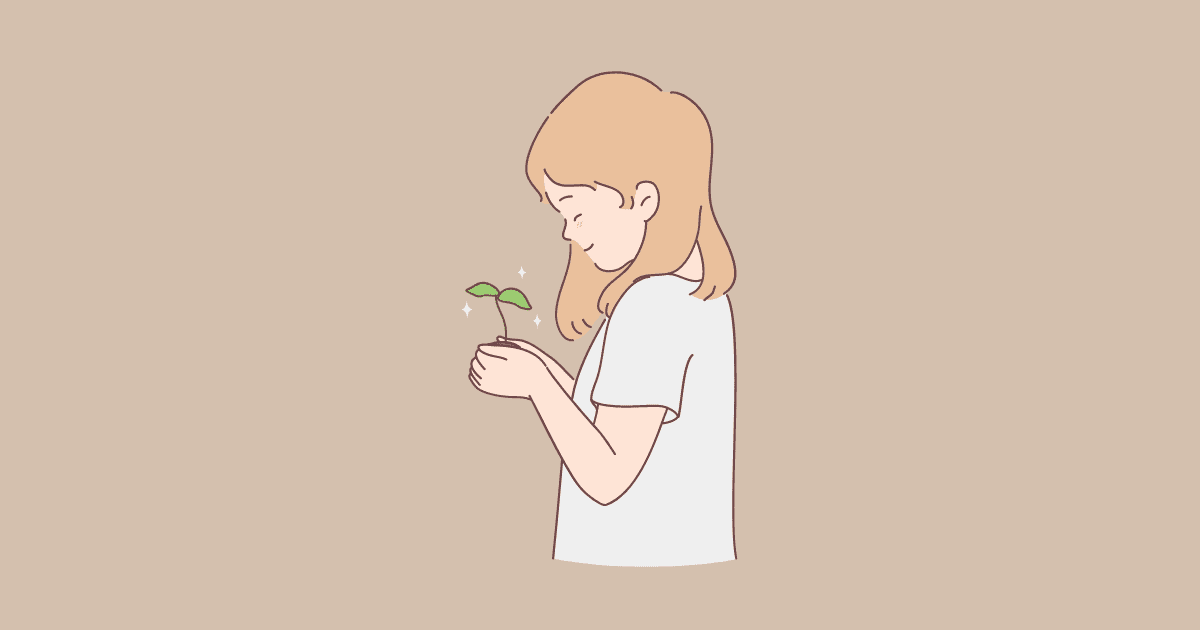
子どもの言葉の発達は、親にとって特に気になるポイントの一つです。
3歳頃になると、「これくらい話せるのが普通?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
まずは、一般的な発達の目安や、子どもによって異なる成長のペースについて知ることから始めましょう。
一般的な言葉の発達の目安
3歳頃になると、二語文(「ママ きて」「ワンワン いた」など)を使い始めます。
少しずつ、簡単な会話ができるようになる子が増えてきます。
また、「これなあに?」と質問が増えるのもこの時期の特徴です。
発達には個人差がある理由
言葉の発達は、性格、家庭での会話量、兄弟の有無など、さまざまな要因に影響されます。
活発に話す子もいれば、じっくり観察してから話し始める子もいます。
「遅い=問題」ではなく、その子の個性として見守ることが大切です。
言葉の発達のステップはみんな違う
言葉の発達は個人差が大きく、子どもはそれぞれのペースで習得していきます。
例えば、次のようなタイプがいます。
- おしゃべり大好きタイプ
- ひとり言もくもくタイプ
- 突然大人顔負けタイプ
おしゃべり大好きタイプ
言葉の意味は理解していなくても、話すことを楽しむタイプです。
自分から積極的に周りに話しかけていきます。
ひとり言もくもくタイプ
会話よりも、遊んでいるときなどにつぶやいたり、歌ったりするタイプです。
他の子に話しかけられても言葉でお返事することが少ないです。
ただ、言葉の意味は理解できているので黙っていながらも一緒に行動することができます。
突然大人顔負けタイプ
発話がない、または少ない期間を経て、突然大人のようにスラスラと話し出すタイプです。
話していない時期は、周囲の言葉をしっかりと聞いていて、頭の中では言葉が豊かに発達しています。
何かをきっかけにして、上手に話せるようになります。
言葉の発達が気になったときの3つのチェック
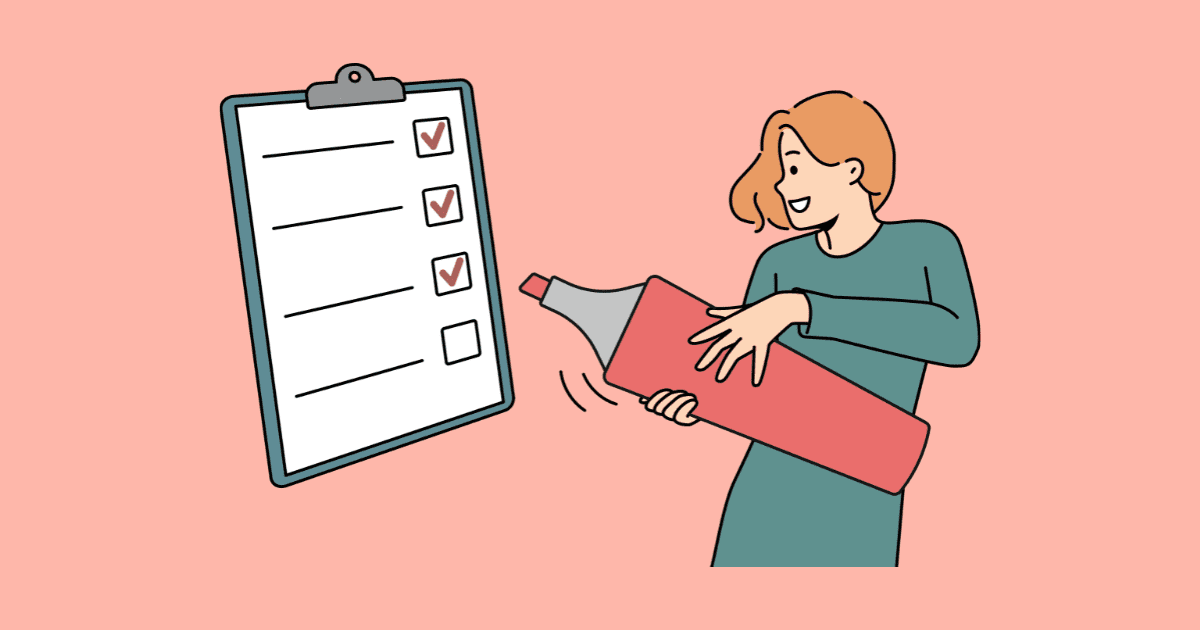
先ほどの3つのタイプに当てはまらない子もたくさんいるでしょう。
そうした子でも、次の3つができていれば大丈夫です。
- 言葉の意味は理解している?
- 話しかけると相手の目を見る?
- 名前を呼ぶと注意を向けてくれる?
言葉の意味は理解している?
言葉の意味を理解しているかどうかは大切なチェックポイントです。
例えば、次のようなお手伝いをお願いをしてみましょう。
- コップを持ってきて
- ゴミ箱にポイしてね
- ママの肩をトントン叩いてくれる
 ゆう
ゆう子供に話しかけたとき、親が答えを待てないことがあります。一呼吸おいて、子どもの返事や行動を待ってみましょう!
話しかけると相手の目を見る?
コミュニケーションは言葉のやり取りだけでなく、相手と自分の視線を交わせるかどうかも大切です。
子どもが相手の目を見て話せているかどうか観察しましょう。
もちろん子どもにとって苦手な人や、機嫌によって視線を合わせられないときはあります。
どんなときに話しかけられても相手と視線を合わせられないようであれば、相談機関に相談しましょう。
名前を呼ぶと注意を向けてくれる?
子どもの名前を読んだときに、言葉で返事をしなくても注意を向けてくれるかどうか。
子どもが遊びに夢中なときは、気づかない時もあります。
さまざまな場面で試してみましょう。



言葉が聞こえていないようなときは、中耳炎や難聴を疑うことも大切です。そうしたときは、耳鼻科の医師に相談しましょう。
言葉の発達のQ&A
3歳ころの子どもの言葉の発達についての質問をいくつか紹介します。
発音があいまい
もうすぐ3歳になるのですが、発音があいまいなのが気になります。



積極的に口の周りの筋肉を動かすようにしよう
言葉の発達に関わる口の周りの筋肉の発達は、個人差があります。
風船を膨らます、おもちゃのラッパを吹く、風車を口の風で回すなどして、遊びの中で口を動かす機会を作ってみましょう。
また、スルメなどの歯応えのあるおやつを食べることもおすすめです。
吃音が出る
幼稚園に入り、吃音が出るようになりました。



子どもなりに幼稚園の生活を頑張っている証拠です。
吃音は、緊張から生じていると考えられます。
新しい環境は、大人でも緊張しますよね。
子どもは、慣れない環境で頑張っているのでしょう。
幼稚園で緊張している分、家ではリラックスできる環境づくりを心がけましょう。
言い直しをさせる、幼稚園で習得したことを家で復習させるなどは控えましょう。
1か月を過ぎても症状が続くようでしたら、小児科や子育て支援センターなどに相談をするとよいです。
親が話すのが苦手
自分自身が話すことが苦手で、子どもに何を話しかけてよいのかわかりません。



負担に思う必要はありませんよ。
親は、子どもと話さなければならないと思いがちです。
ですが、日常生活で話しかけることができていればそれで十分です。
絵本を読む、歌を歌う、手遊びをするなども言葉を育む方法の一つです。
家庭でできる言葉のサポート方法
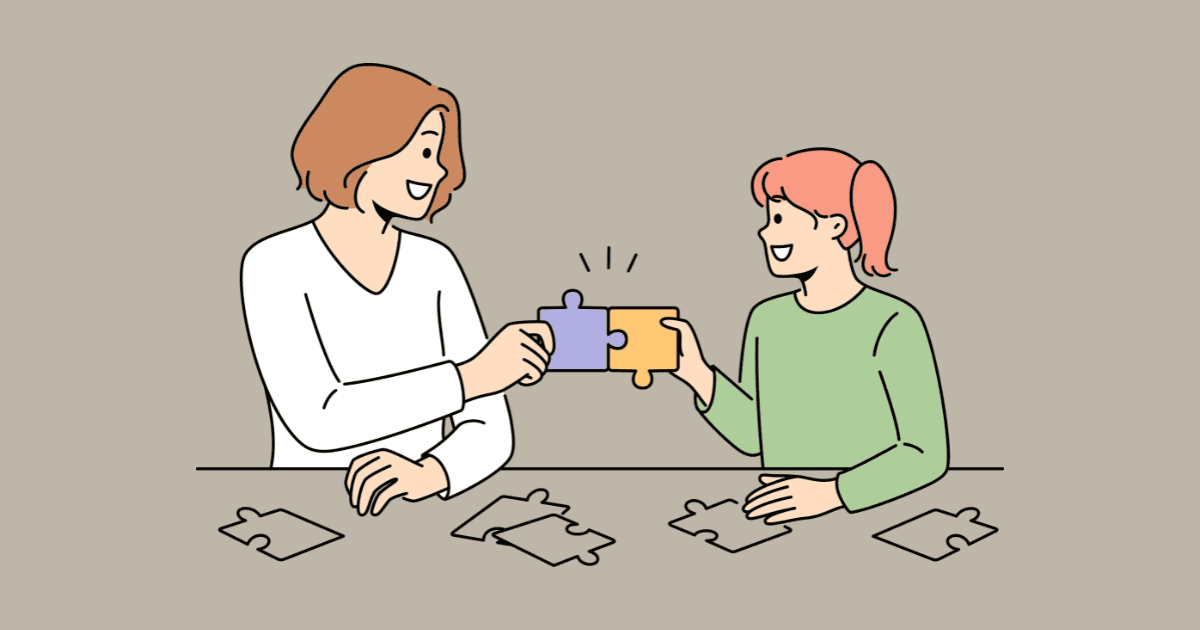
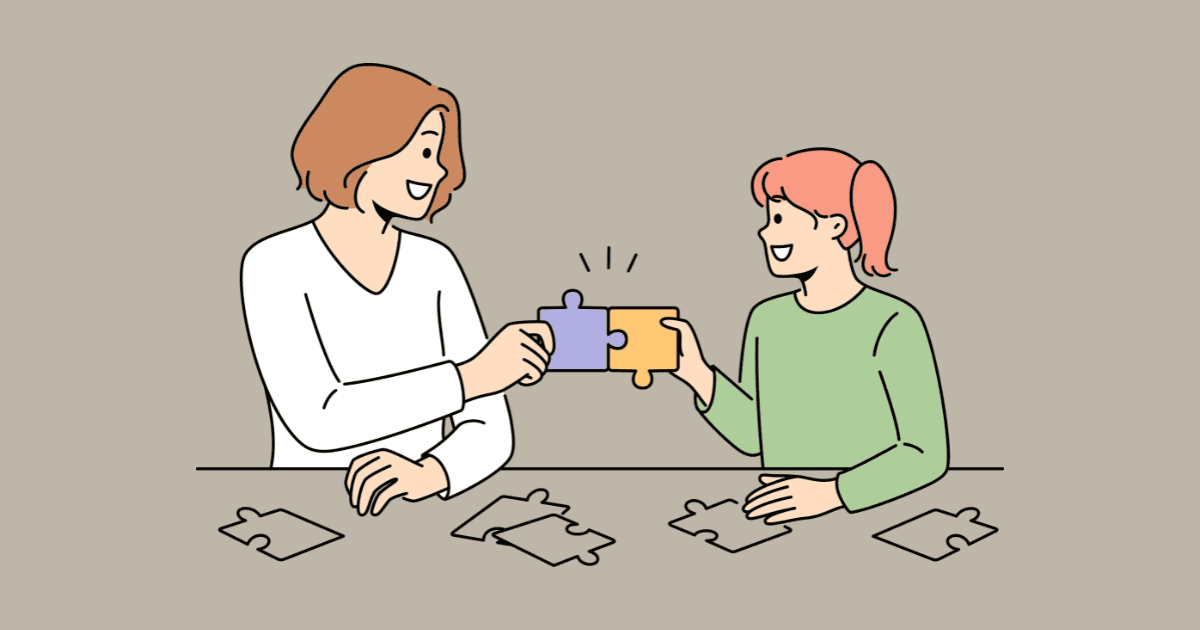
言葉の発達を促すには、家庭での関わり方がとても重要です。
特別な教材や訓練が必要なわけではなく、日々の会話や遊びの中で自然に育まれていきます。
お子さんの「話したい」という気持ちを引き出すために、親としてどのような接し方ができるのか、すぐに取り入れられるポイントをご紹介します。
日常会話で意識したいこと
子どもとの会話では、質問攻めにしないで、「あなたの話を聞いてるよ」という姿勢が大切です。
たとえば、子どもが「バナナ!」と言ったら「黄色いバナナだね、美味しそうだね」と返してあげましょう。
このように、言葉を広げて返すことで、自然な発語を促すことができます。
絵本や遊びを通じた言葉の刺激
絵本の読み聞かせは、語彙を増やすのにとても効果的です。
読むときはセリフに感情を込めたり、「次はどうなると思う?」と問いかけたりすることで、子どもの想像力や表現力も育ちます。
また、積み木やごっこ遊びなども、言葉を使うよい機会になります。
「話したい気持ち」を育てる関わり方
子どもが安心して話せる環境づくりが、言葉の発達には欠かせません。
うまく話せなくても急かさず、言おうとする気持ちを尊重しましょう。
「聞いてもらえた」「伝わった」という経験が、「もっと話したい」という意欲につながります。
まずは、共感しながら受け止める姿勢が大切です。
スマホ子育ては危険
ゲームや動画を見せていると、子どもの機嫌がよくなるからといって、スマホやタブレットを見せる機会が増えていませんか?
過度な利用は、心身の成長に悪影響を及ぼします。
特に、幼い子どもは、大人より短期間でスマホ依存に発展しやすいという調査結果もあります。
「夕飯を準備する間だけ」「電車に乗っている間」など、長時間にならないように親が時間を区切って管理しましょう。
そうしたルールを子どもに伝えて、それを守れたら褒めてあげましょう。
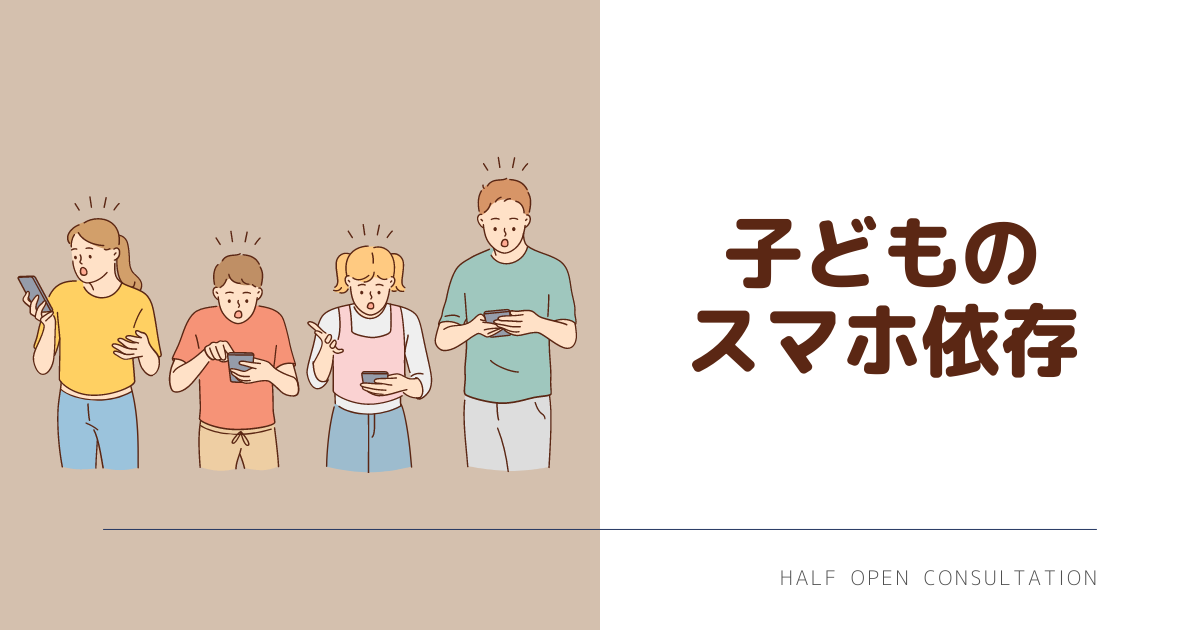
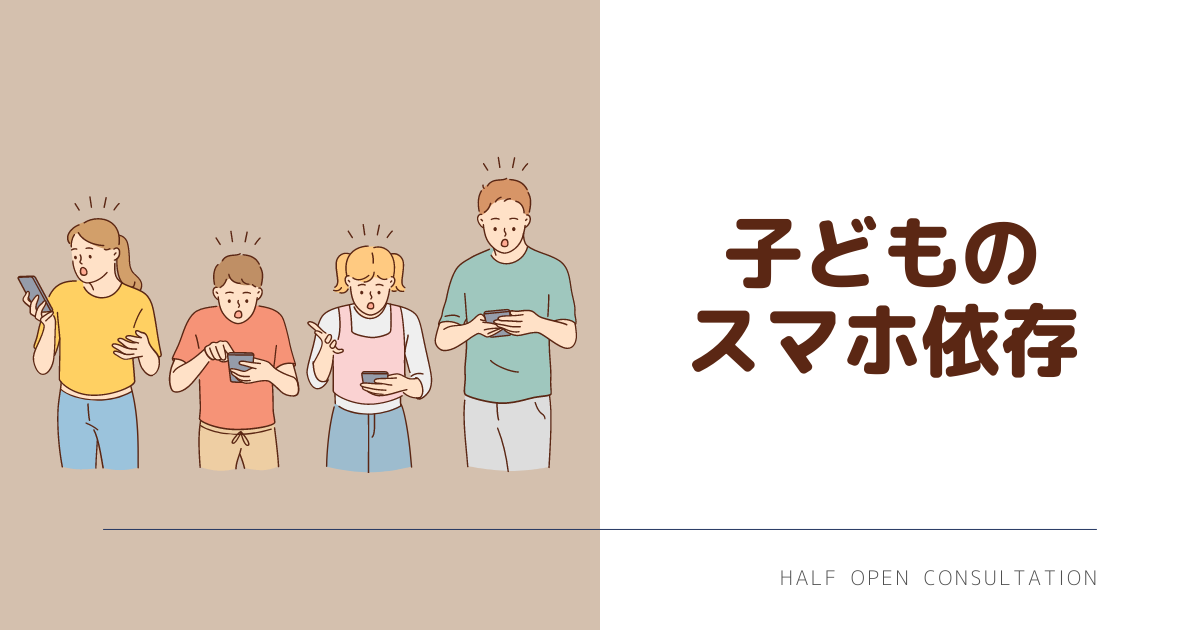
まとめ
この記事では、子どもの言葉の発達の目安やチェックポイント、家庭でできるサポート方法について紹介しました。
言葉の発達には個人差があり、ゆっくりでも少しずつ育っていく子も多くいます。
不安な気持ちを一人で抱えず、必要に応じて専門機関に相談することも大切です。
お子さんのペースを大切にしながら、できるサポートを続けていきましょう。
安心して子育てできるヒントになれば幸いです。
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後までご覧いただきありがとうございました。
にほんブログ村
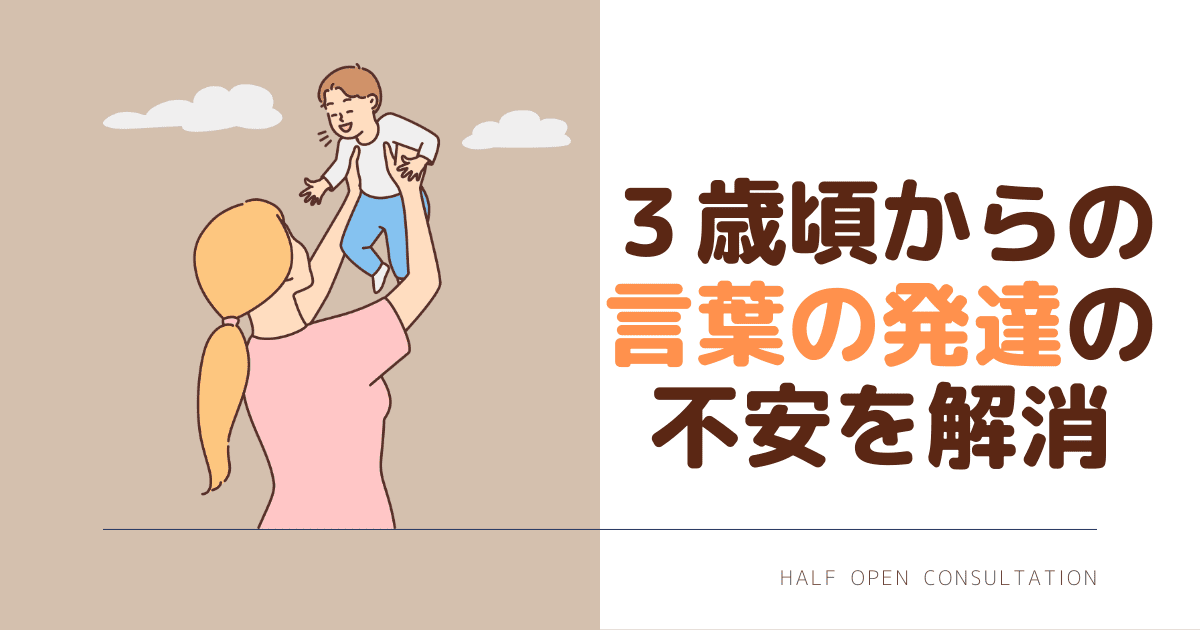
コメント