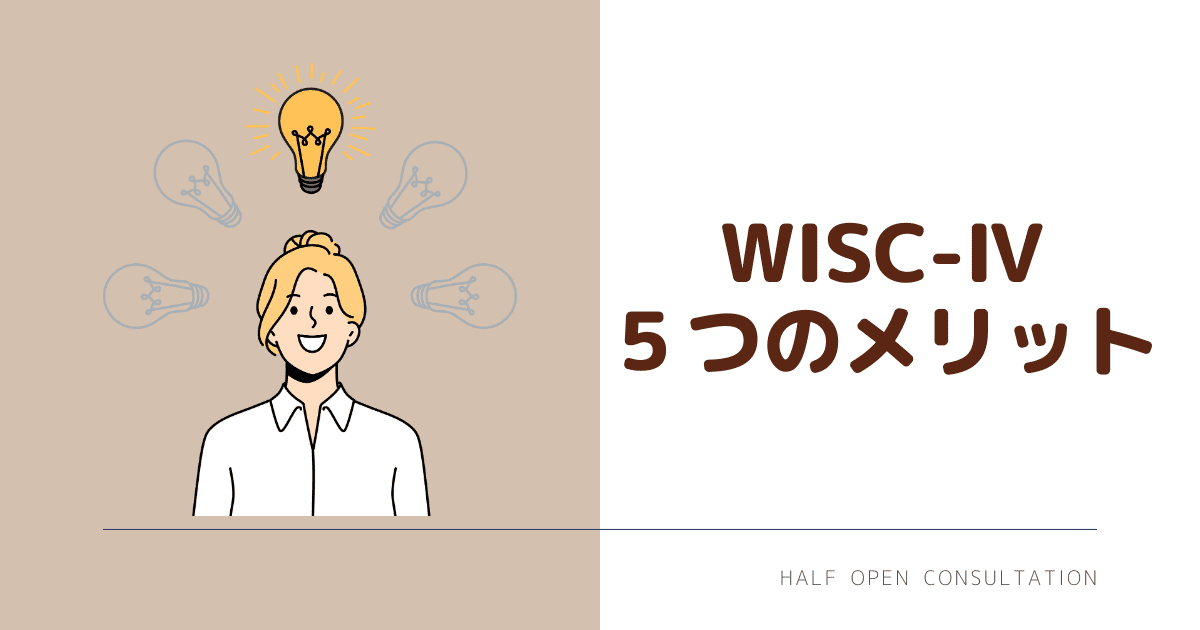今回の記事では,
子どもが知能検査(WISC)を受けることのメリット
について詳しく説明していきます。
もしも小学校に通っているお子さんが、学校生活にうまくいっていない場合、学校の先生から知能検査の受検を勧められることがあります。
自分が親であれば、「どうしてうちの子が?」とか、「もしかして知的障害なのかしら?」などと、ものすごく不安になったり、恥ずかしくなったりしてしまうかもしれません。
私は、小学生の子どもたちを持つ親の相談に乗る中で、このようなことで悩む親に何人も会ってきたので、その気持ちはとても分かります。
ただ、ちょっと待ってください。
 ゆう
ゆう知能検査は、決して知的障害を調べるためだけに行うものではありません。
知能検査を実施することで、お子さんの得意なところや苦手なことが分かったり、他にも様々なことが分かるといったメリットがたくさんあります。
そこで、今回は、
- 知能検査を受けるメリットを知りたい!
- 知能検査を受けるときに気を付けることとは?
という悩みや疑問について答えていきます。
もしも小学校で知能検査の受検を勧められた方は参考にしてください。
知能検査を受ける5つのメリットとは?


知能検査は、いくつか種類がありますが、世界中・日本中で最もメジャーな検査として「WISC-Ⅳ」があげられます。
「うぃすく・ふぉー」と読みます。
WISC-Ⅳを受けると、子どもについていろいろなことが分かります。
WISC-Ⅳを受けるメリットは次の5つです。
- IQが分かる
- 得意なことと苦手なことが分かる
- 指導をするときのコツがわかる
- 子育ての悩みを先生と共有できる
- 適切な支援につなげられる



それでは、一つずつ説明していきます!
IQが分かる
IQについては、聞いたことのある方、多いのではないでしょうか?
IQとは、知能指数という意味であり、同年代の子どもの中で知能がどの程度の水準にあるかが分かります。
IQ=100であれば、「同年代の子どもと比べて知能の水準は平均である」という意味になります。
その数字が100程度であれば、基本的に学校生活に支障は生じにくいですが、IQ=80未満では勉強についていくことが難しくなり、70未満だともしかしたら「知的障害」と診断されるかもしれません。
IQを知ることで、子どもが普通学級で勉強をした方が良いのか、それとも支援学級で学んだ方が良いのか、一つの方針を得ることができます。



とは言え、IQだけで知能の全てが分かるわけではありません。
IQについては、下記の記事で詳しく説明しています。
得意なことと苦手なことが分かる
IQを知る以上に意味があるのは、子どもの得意なことと苦手なことが分かることです。
WISC-Ⅳでは、ざっくりと説明すると次の4つの力を調べることができます。
- 言葉を使う力(言葉の力)
- 目から情報を取り入れたり記憶したりする力(目の力)
- 耳から情報を取り入れたり記憶したりする力(耳の力)
- 手先の器用さ・素早さ(手の力)
この4つの力のうち、どれが得意なのか、どれが苦手なのかを数字で知ることができます。



例えば、「言葉の力」と「目の力」が得意で、「耳の力」と「手の力」が苦手な子どもがいるとします。
この子どもは、
「他人と話をしたり、教科書やメモを読んで覚えたりすることが得意。一方で、耳で聞いたことを覚えることは苦手で、聞いたことを素早くメモに残すことも不得手。」
といった感じになります。
ここでは分かりやすいように4つの力に絞って説明しましたが、WISC-Ⅳではいくつかの種類の課題を取り組むことで、そこから様々な力を詳細に調べることができます。
苦手なことが分かれば、その子に合った学用品を用意することで、学校での学習面をサポートすることができます。
指導をするときのコツがわかる
子どもの得意なことと苦手なことが分かれば、その子を指導するときにどのような点に気を付ければよいかが分かるようになります。
先ほどの例の子どもであれば、
「指導をするときは,口で注意をするだけでは忘れてしまいやすいので、口頭の注意に合わせてメモを渡して目で見て理解できるようにさせる」とか、「黒板の文字を書き写すのに時間が掛かるので,その子が書き終えたかどうかを確認してから消す」
といった方法が考えられます。
もちろん学校ではすべての子どもに合わせて教育や指導を行うことはできませんが、個別の指導の時間であったり、親がしつけをしたりするときには、非常に役に立ちます。



知能検査を行う意味は、まさにこのためだと言えます。
子育ての悩みを先生と共有できる
知能検査を受ける場合、その結果は親と学校で共有することになります。
すると、子どもの得意なことと苦手なことを親と学校の先生で把握することができるようになります。
親と学校の先生が、子どもに対して一貫した指導を行うことができるようになり、それが子どもの成長にもつながっていきます。
また、これまで親が抱えてきた悩みや苦労を、学校の先生にも理解してもらうことになりますので、親の気持ちが少し楽になるという効果も期待できます。
適切な支援につなげられる
知能検査の結果で、IQが平均よりも相当程度低かった場合、子どもにとっては通常学級で学ぶことが大きな負担になっている可能性があり、支援学級を検討することになります。
また、IQの低さに加えて、日常生活や学校生活でも支障が生じている場合、「知的障害」と診断される可能性も出てきます。
その場合には、「療育手帳」を取得して、より丁寧な支援を受けることができるようになります。
そうした事実を親が受け入れるのはなかなか難しいかもしれません。
しかし、子どもにとっては早い段階で必要な支援を受けさせた方が、その子の学力や社会性の伸長につながります。
もしも、知的障害が分かった場合、早期から手厚い支援を受けられます。
特別支援学校に入学できれば、その子に合った方法で生活訓練や職業訓練などを受けることができます。
すると、社会人になるときに障害者の雇用枠を活用して、大企業などに就職できる可能性も出てきます。



私が過去に支援したことのあるお子さんは、特別支援学校卒業後、某自動車メーカーに就職して、高卒で就職した人よりも、多くの給料をもらっています。
知能検査を受けるときに気を付けること
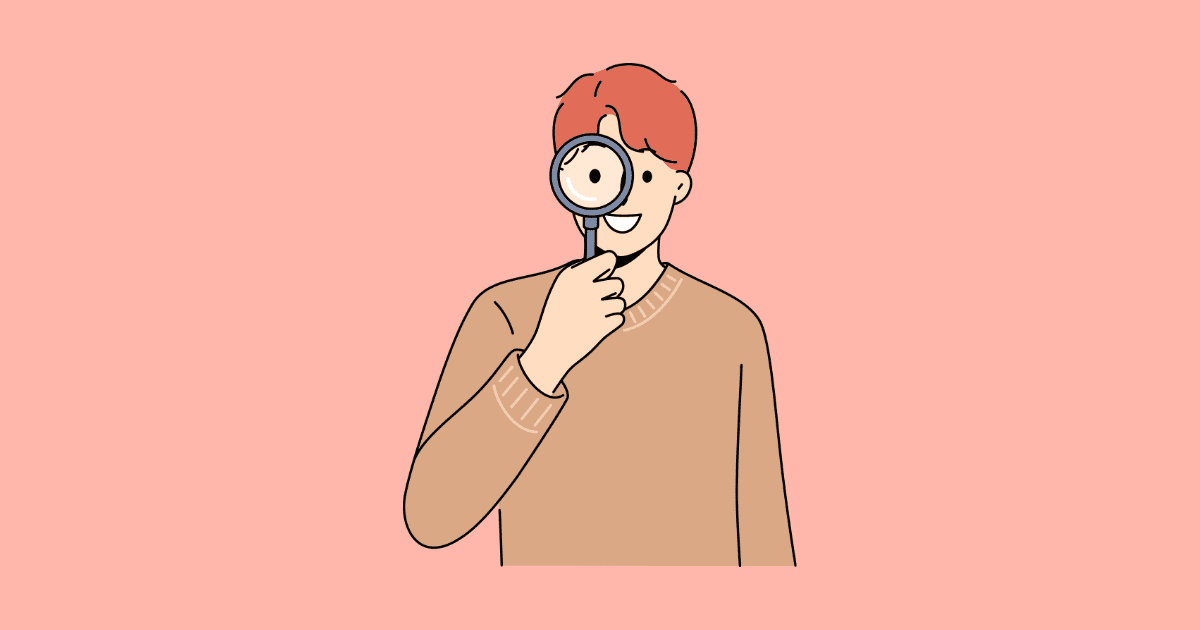
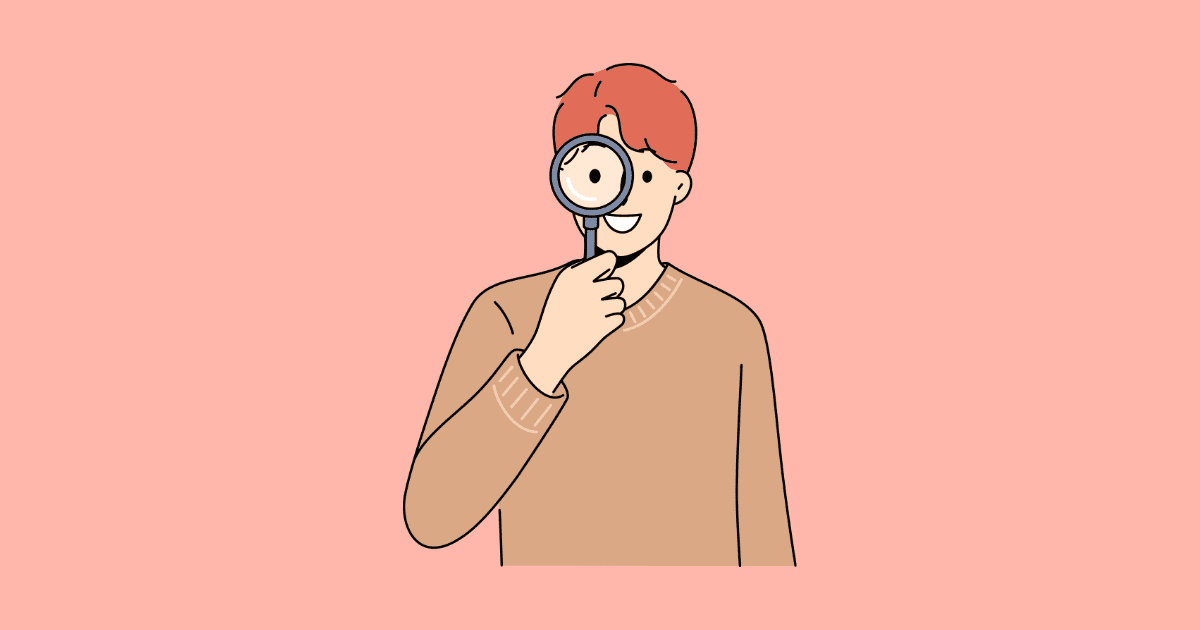
いざ知能検査を受けることになったとき、親が気を付けることはどのようなことでしょうか?
子どもの気持ちに立って考えながら、大切なこと3点を説明します。
親が知能検査の大切さを理解する
子どもにとって、知能検査を受けるということは、親以上に不安が大きいものです。
親が知能検査に否定的な考えを持っていたとしたら、子どもはますます不安になり、実際の検査で自分の力を発揮することができないかもしれません。
だからこそ、親が知能検査を受けることの大切さを理解して、子どもの不安な気持ちを取り除いてあげることがとても重要です。



親も不安だと思います。家族だけで抱えずに、先生や検査をしてくれる人にいろいろと話を聞いてもらいましょう。
IQの数字は知らせない
子どもにとって、知能検査を受けることは不安であると説明しました。
そうした子どもは、自分のIQの数字を知ることはそれ以上に不安です。
小学生低学年であれば、あまり理解できないかもしれませんが、小学生高学年であれば数字の持つ意味を理解できてしまいます。
数字は、インパクトが大きく、その子にとって生涯忘れられない傷になるおそれがあります。



それに、小さな子どもにIQを知らせることは全く意味がありません。
何よりも、その子の得意なことや苦手なことを教えてあげることが大切です。
IQの数字の取り扱いについては、先生や検査者と相談しつつ、親が子どもに直接教えないように気を付けましょう。
得意なことをたくさん伝える
知能検査では、得意なことや苦手なことが分かると説明してきましたが、子どもに伝えるときには苦手なことは少なめに、得意なことを多めに伝えましょう。
子どもが、自分の得意なことを知り、それを生活の中でどのように生かすかということが分かることが理想です。



得意なこと:苦手なこと=9:1くらいでよいと思います。
子どもが得意なことを伸ばすことができれば、それが苦手なところをカバーすることにもなります。
知能検査のフィードバックについては、次の記事も参考になります。
おすすめのオンラインカウンセリング
自分のことや家族のことでお悩みの方は、一度オンラインカウンセリングを検討してみてはいかがでしょうか?
他人に相談することに多くの人は抵抗がありますが、私のブログをお読みになっていただいている方は、悩みを解決するために一歩進むことのできる方です。
実際のカウンセリングルームや精神科病院などにいくのは勇気がいりますし、家族の理解も得にくいと思いますので、そうした方には「オンラインカウンセリング」をおすすめしています。
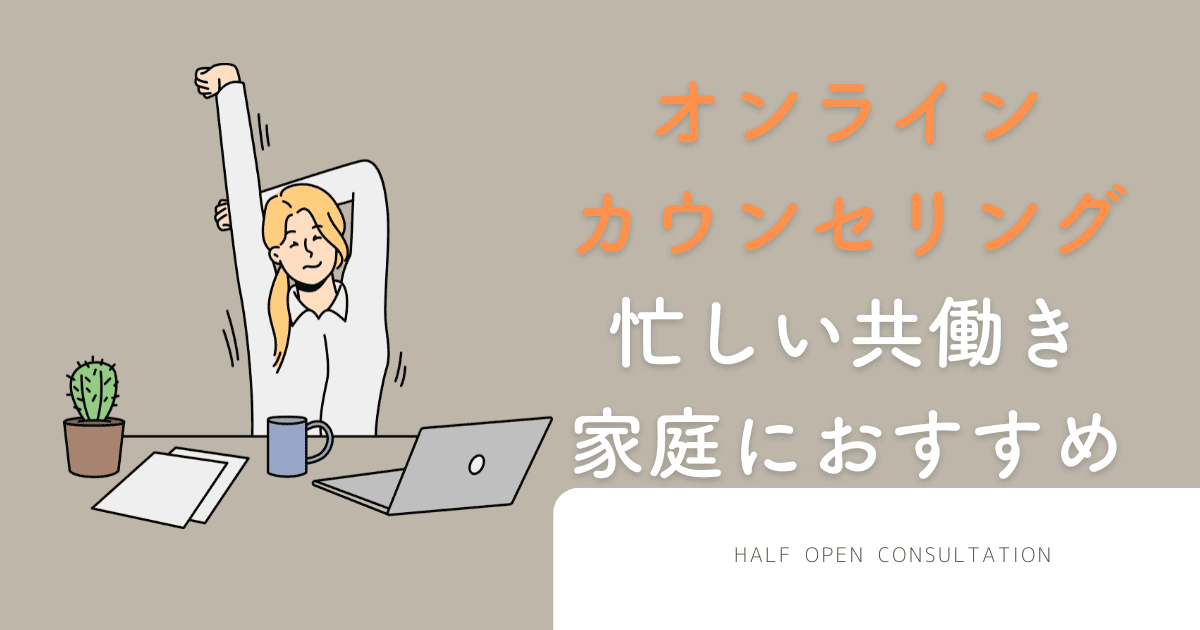
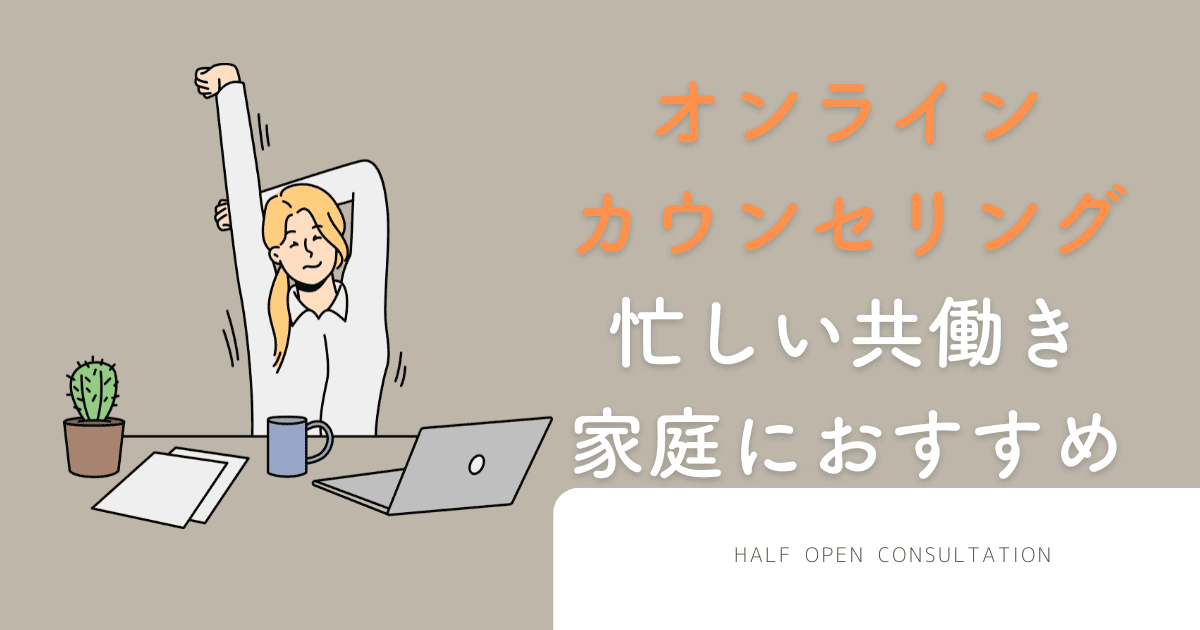
ネットで検索すると様々なオンラインカウンセリングが出てきますが、「うららか相談室」は、私と同じ公認心理師や臨床心理士といった信頼性の高い心理の資格をお持ちの方が相談に乗ってくれます。
多種多様な相談内容にも対応しているので、一度試してみてはいかがでしょうか。


- 国内最大のオンラインカウンセリング
- 600名を超える専門家に相談できる
- カウンセリング方法を4種類から選べる
- 誰にも知られず、匿名での相談が可能
\まずは無料会員登録から!/
/満足保証サポート制度\
まとめ
今回の記事では、子どもが知能検査を受けることのメリットについて解説してきました。
親や子どもにとって、知能検査を受けることは不安が大きいかもしれませんが、たくさんのメリットがありますので,そのことを頭の中に入れておきましょう。
知能検査によって、子どもの得意なことや苦手なことが分かれば、日常生活や学校生活を送る上でのコツが分かるようになり,子どもの心の成長にもつながります!
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村