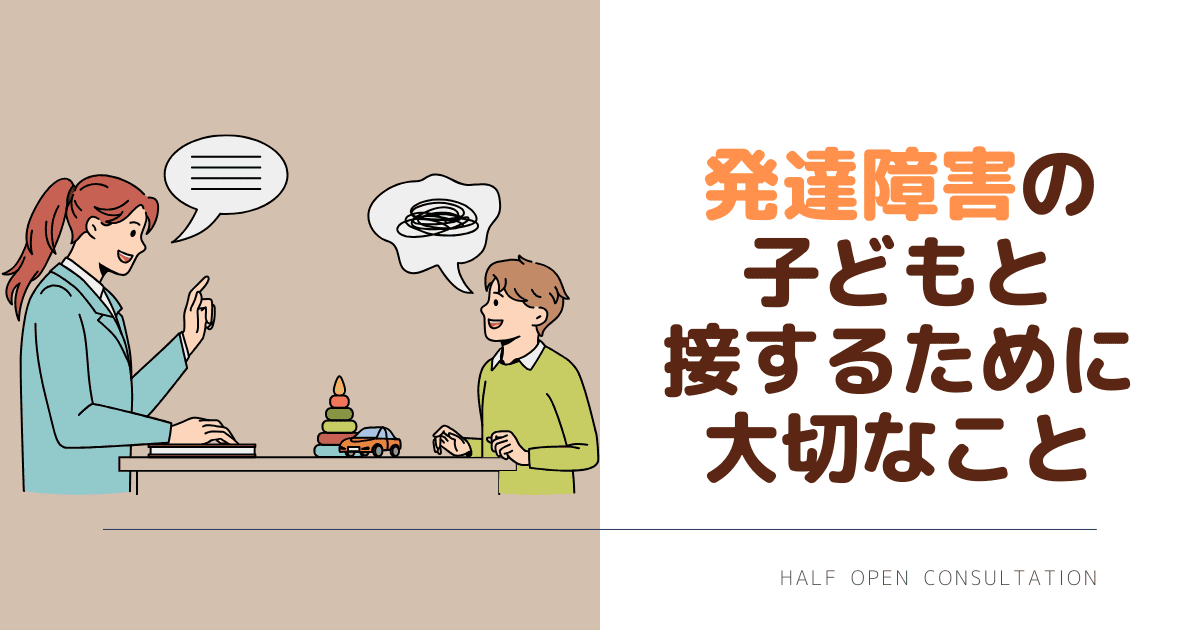今回の記事は、
発達障害の子どもと接する上で大切なこと
について詳しく説明していきます。
発達障害のあるお子さんを育てていると、目の前の対応に追われてしまい、その子の特徴に応じた対応をしようとしても、うまくできないときがあります。
特に、こだわりが強かったり行動が激しかったりする場合、本当に苦労の連続で、冷静に対応することができなくなりがちです。
 ゆう
ゆう私の心理相談室には、そうしたことに悩む親が相談にいらっしゃることが少なくありません。
そこで、今回は、
- 発達障害について知りたい!
- 発達障害の二次障害について学びたい!
- 発達障害のある子どもと接する上で大切なこととは?
といった疑問や悩みに答えていきます。
発達障害のあるお子さんの子育てでお悩みの方は、是非参考にしてください。



発達障害の基本についても押さえておきましょう!
発達障害とは?
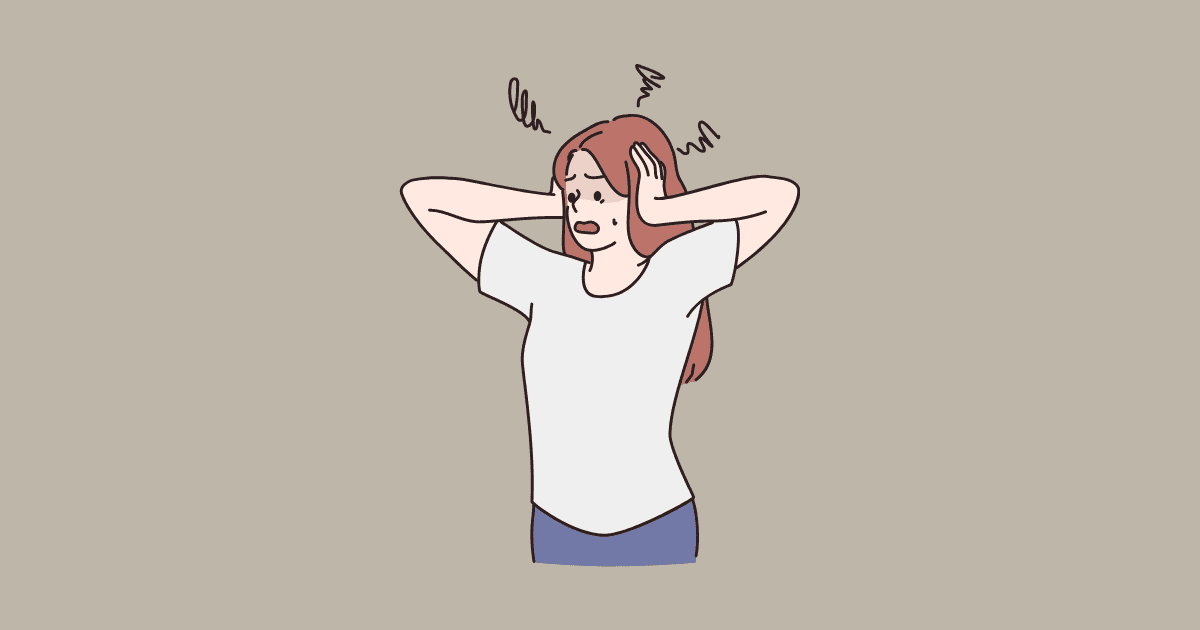
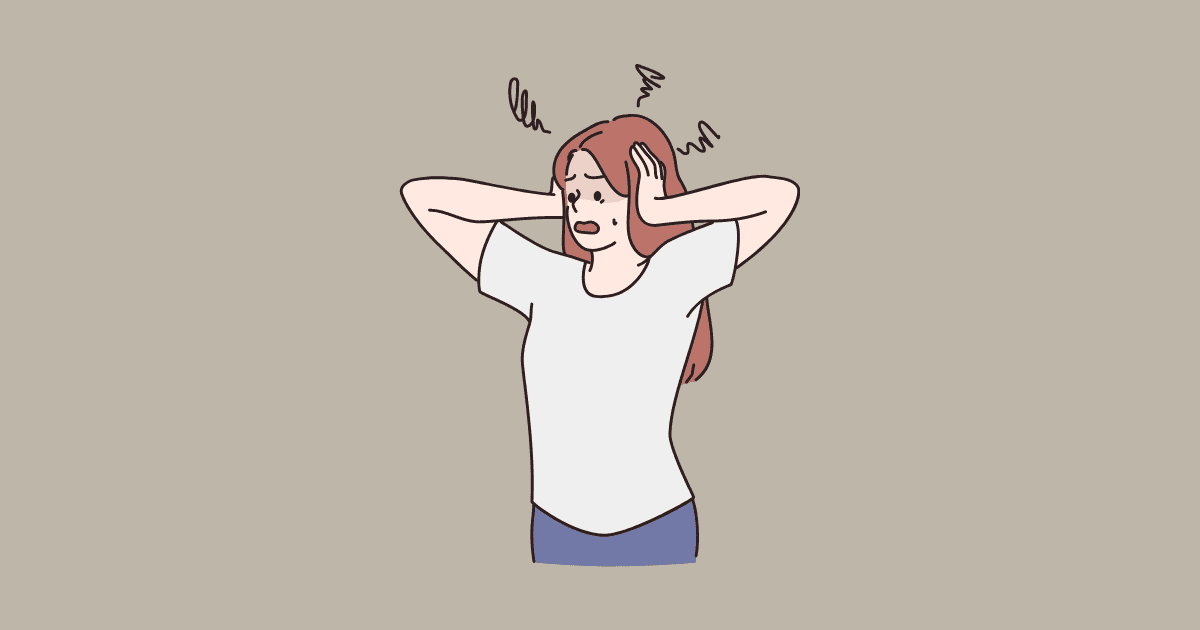
発達障害はいろいろな種類がありますが、代表的な種類としては次の3つです。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如多動症(AD/HD)
- 学習障害(LD)



これに「知的障害」を加えるという考え方もあります。
発達障害に共通する特徴としては、言語や知的な発達の遅れや偏り、人とのコミュニケーションや社会性などに支障が生じるといったことが挙げられます。
ここでは「自閉スペクトラム症(ASD)」と「注意欠如多動症(ADHD)」の2つについて説明していきます。
症状などについては、厚生労働省のホームページでも詳しく説明されています。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)の特徴は次のとおりです。
コミュニケーションの難しさ:言葉や視線、表情、身振りなどを用いて相互的にやりとりをしたり、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりすることが苦手。
こだわりの強さ:特定のことに強い関心をもっていたり、こだわりが強かったりする。
感覚の過敏さ:五感の過敏さ(蛍光灯の光が苦手。素足で砂を踏むことが苦手など)
発達障害の診断がないお子さんでも、似たような傾向を持つ子は結構います。
そうした子どもたちは、上記のような特性があるため、自覚はなくても、他人を不快にしてしまうような振る舞いを取ってしまいがちです。
具体的には、次のような感じです。
- 相手の気持ちが分からず、相手が傷付くような言葉を言ってしまう。
- こちらがいくら丁寧にやり方を教えても、自分のやり方を押し通そうとする。
- ちょっとした怪我でも大げさに痛がる(本人は本当に痛いと感じている)。
親や周りの大人は、その子が「わざとやっているんじゃないか。」、「注意しても駄目ならどうすればいいんだ。」とイライラしたり悩んだりしてしまいがちです。
注意欠如多動症(AD/HD)
注意欠如多動症(AD/HD)の特徴は次のとおりです。
不注意:活動に集中できない、気が散りやすい、物をなくしやすい、順序立てて活動に取り組めないなど。
多動-衝動性:じっとしていられない、静かに遊べない、待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまうなど。
具体的には、次のような行動が該当します。
- じっとしていられず、落ち着きがない。
- 忘れ物や落とし物が多い。
- 人の話を最後まで聞かないで行動に移す。
小学生低学年までの子どもであれば、こうした行動があっても当たり前です。
その程度が強かったり、小学校高学年や中学生になっても変わらなかったりする子もいます。
親としては「何で普通に座っていることができないんだろう」、「何度注意しても変わらない」といったモヤモヤ・イライラした気持ちが生じやすくなります。
また、子どもが他者に直接迷惑を掛けるような行動に及んでしまい、大きな問題に発展することがあります。
なお、親自身が大人のADHDに気づく方法やトレーニング方法については、次の記事を参考にしてください。
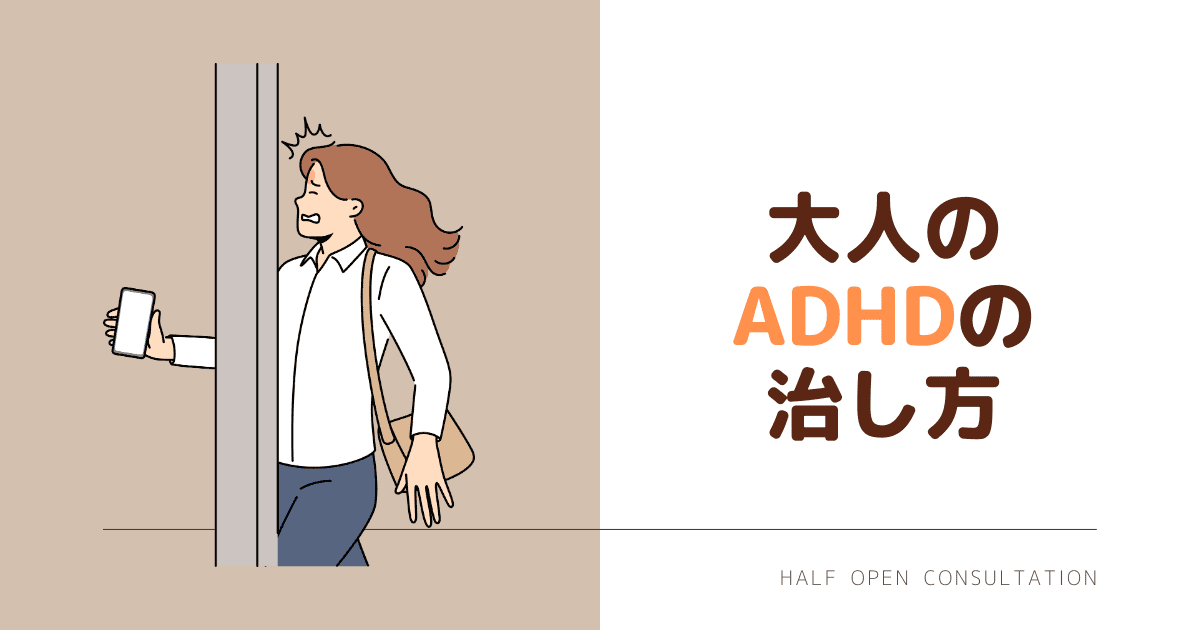
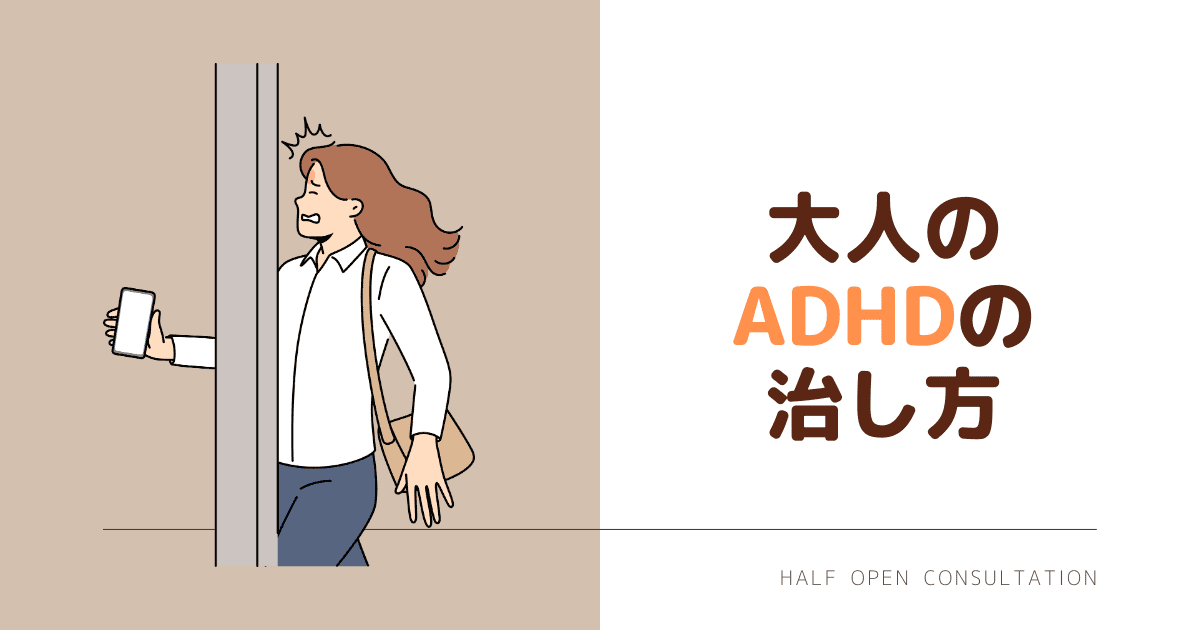
発達障害の子どもの増加
みなさん、発達障害の子どもの割合は増えているということはご存じでしょうか?



2022年の調査では、小学生の約8%が発達障害に該当する可能性があるという結果が出ています。
発達障害は脳の器質的な障害の影響を受けていると言われています。
そのため、子ども自身も変えたいと思っても簡単には変えられないものです。
発達障害のある子どもに接するための心構え
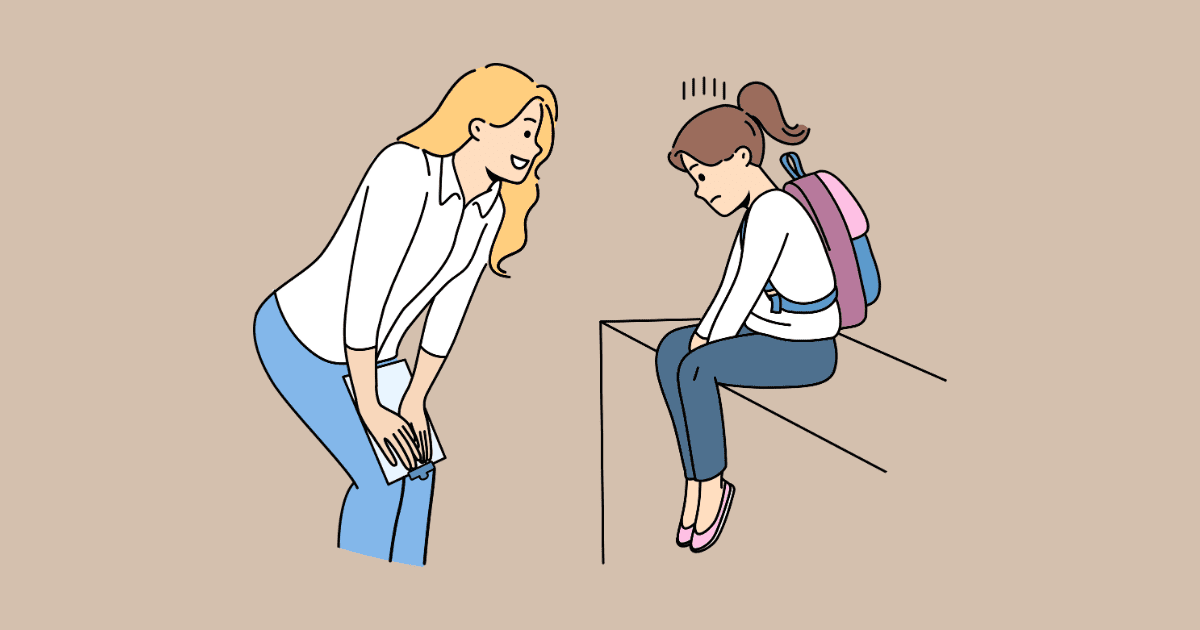
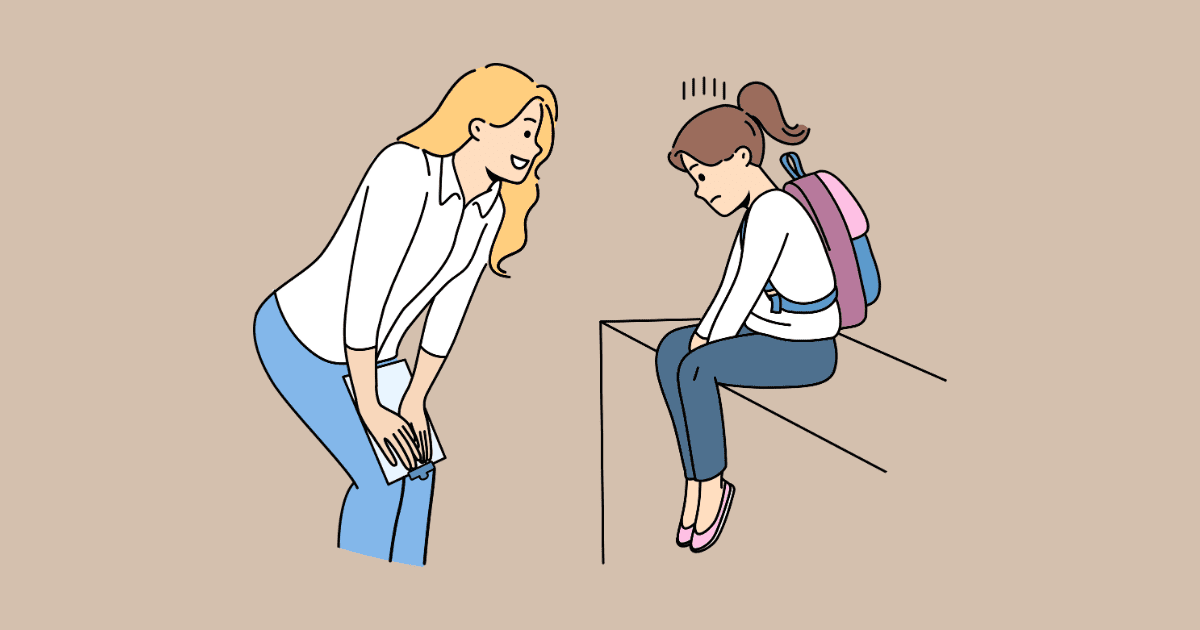
まずは、発達障害のある子どもに接するための心構えをお伝えします。
それは、次の3点です。
- 困っているのは子ども自身
- 発達障害の理解と受け入れ
- 発達障害のある子の特性やニーズへの理解
困っているのは子ども自身
発達障害のある子どもと接していると、「どうしてこんなことするの?」「何が気に入らないんだろう!」「なぜ他の子と同じようにできないの?」といった気持ちになることがあります。
こうした子どもの気持ちがよく分からないし、どのように接すればよいかが分からずに悩んでしまう人は多いと思います。
そこで、最初に、私がみなさんに伝えたいのは次のことです。
親は相当に悩んでいるかもしれませんが、子どもは自分がうまくできていないことについてもっともっと悩んでいます。
子どもに合った接し方は、一人一人異なります。
しかし、「子どもが一番困っている」ということを親がきちんと理解しておくことが何よりも重要です。
このことだけでもわかっていれば、発達障害のある子どもと接するときに、親自身が気持ちに余裕を持って接することができます。



心が傷ついた発達障害の子どもにたくさん会ってきました。親が子どもの気持ちを理解することがその子の心の成長に大切です。
子どもの理解と受け入れ
発達障害には大きく3つの種類があると最初に説明しました。



ASD、ADHD、LDの3種類です。
発達障害のある子どもは、一人一人特徴が異なり、これらの3種類の特徴が入り混ざっている子どももいて、一人として同じ特徴の子どもはいないとも言えます。
そのため、その子がどのような特徴があって、どのようなことが苦手で、何に困っているのかということを理解してあげることが大切です。
それらの特徴を理解した上で、その子の苦手なことも得意なことも、ありのままに受け入れてあげましょう。
子どもは、親に理解してもらうもらうだけでなく、とにかくありのままの自分を受け入れてもらうことで安心できるようになります。
子どものニーズへの理解
発達障害のある子どもの個性・特徴を理解しつつ、その子に必要なことを把握することも大切です。
私の長女は若干のASDの傾向があるため、長女の例で説明します。
長女は、食事をするときに、自分なりの食べる順番を決めていること(こだわり)や味を混ぜたくないこと(味覚の過敏さ)から、「野菜→メインのおかず→ごはん→デザート」の順番でしか食べようとしません。
私や妻は、小さい頃から長女に対して「三角食べをしようね(ご飯・おかず・汁物を交互に食べること)」と言い続けてきました。
しかし、それによって長女は食事の時間が苦痛になっていた時期がありました。
これ以上注意を続けても、長女の個性・特徴は変わるものではないですし、何よりこのまま食事の時間が楽しくなくなってしまうのは避けたかったため、注意をすることを控えるようにしてきました。
いまだに長女の食べる順番のこだわりは変わっていませんが、少なくとも食事の時間は楽しんで食べれるようになりました。
最近では、親自身が「なぜ三角食べをしなければいけないと思っていたんだろう。」と反省し、長女の食べる順番のこだわりを尊重してあげられるようにもなってきました。
コミュニケーションの工夫
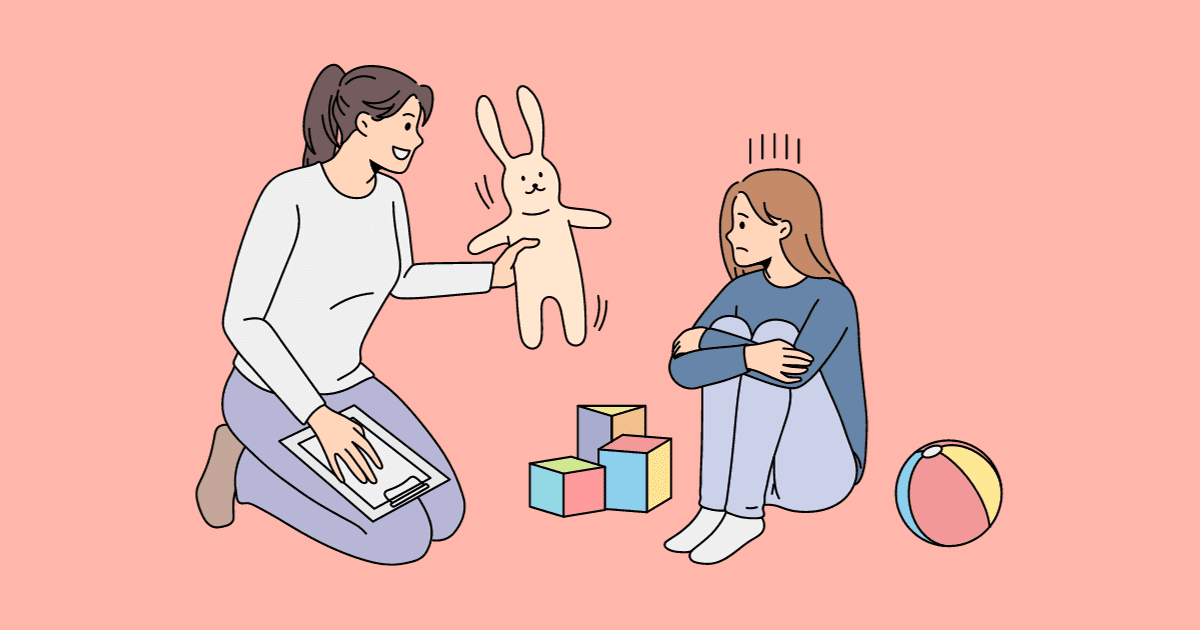
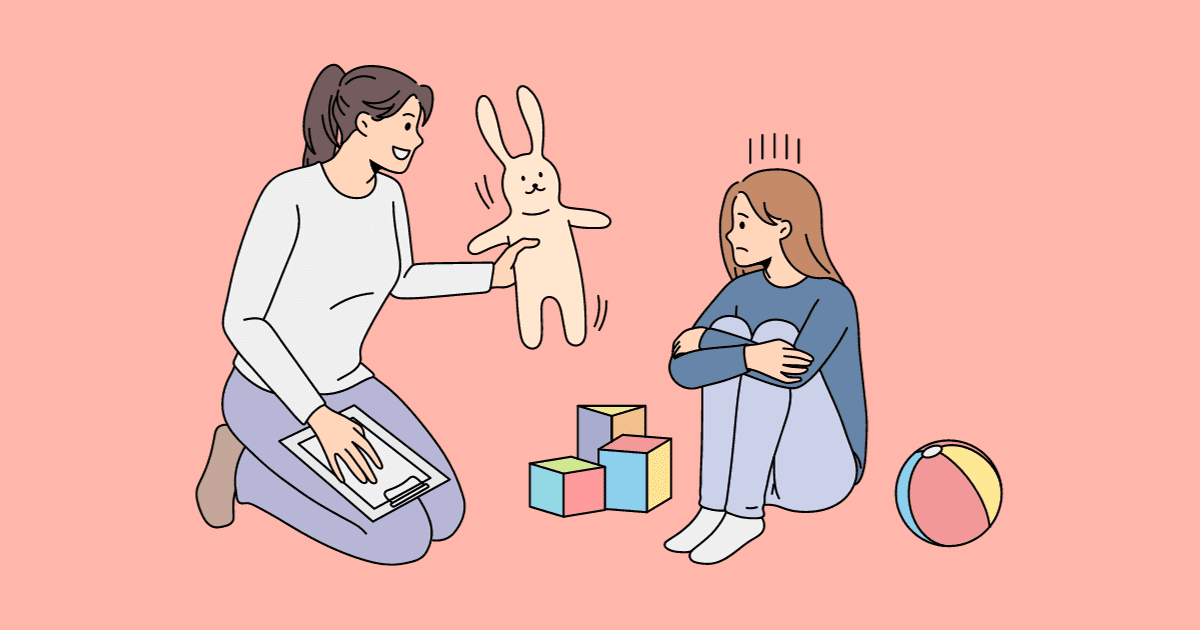
発達障害のある子どもはコミュニケーションが苦手な傾向があります。
そうした子どもたちには、ちょっとした工夫をすることで円滑なコミュニケーションにつながります。
コミュニケーションの障害を理解する
発達障害のある子どものコミュニケーションの障害を理解しておくことが大切です。
発達障害のある子どもの中でも、ASD傾向がある場合、言葉の裏にある意味をくみ取る力が不足しています。
そのため、曖昧な表現で伝えても理解できない場合があります。
ADHD傾向がある場合、長い話を最後まで話を聴いていられないため、わかったつもりになって、指示を勘違いすることもあり得ます。
中には、目で見た情報を覚えておくことは得意でも、耳で聞こえた情報を記憶しておくことが苦手な子どももいて、指示をした内容を覚えられないこともあります。
子どもによってこれらの特徴が混ざっている場合もあるため、その子一人一人の特徴を理解しておくことが、円滑なコミュニケーションにつながります。
クリアで単純な指示の重要性
発達障害のある子どもとコミュニケーションを取る時には、次の3点気をつけて工夫して話しかけましょう。
- わかりやすい言葉を使う
- はっきりとした口調で話しかける
- できるだけ短く伝える
さらに、話し掛けられた内容を覚えるのが苦手な子どもに対しては、後で見返せるようにメモを残したり、メールを送ったりして、視覚情報も合わせて伝えるようにすると、その後の円滑なコミュニケーションにつながります。
発達障害の方のコミュニケーションスキルの伸ばし方について、次の記事を参考にしてください。
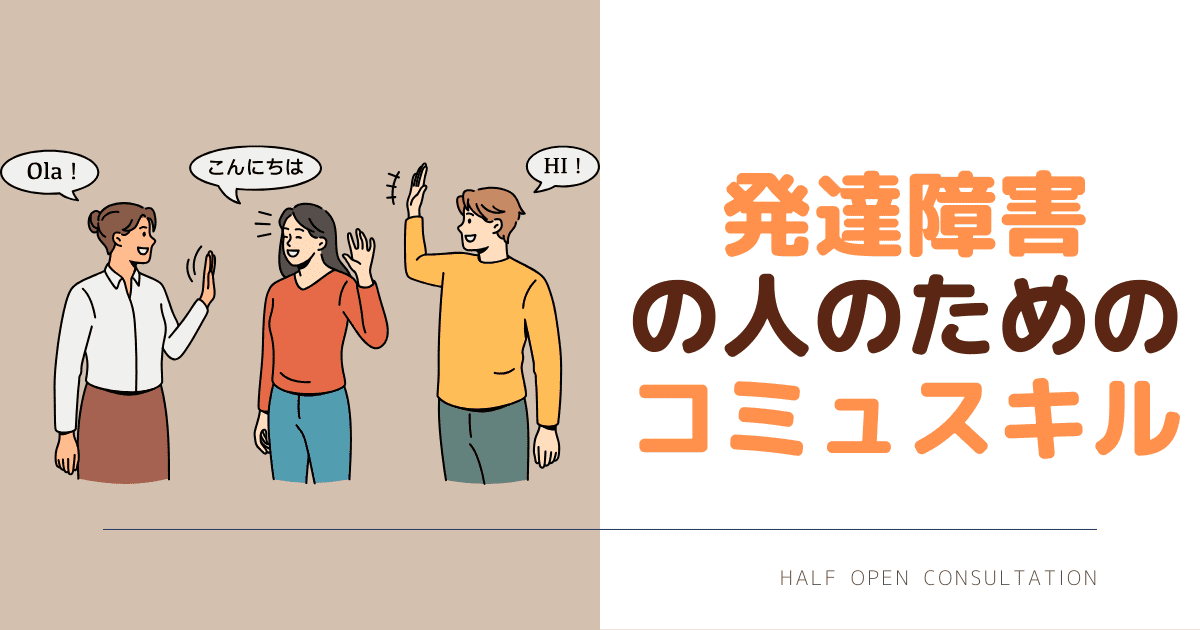
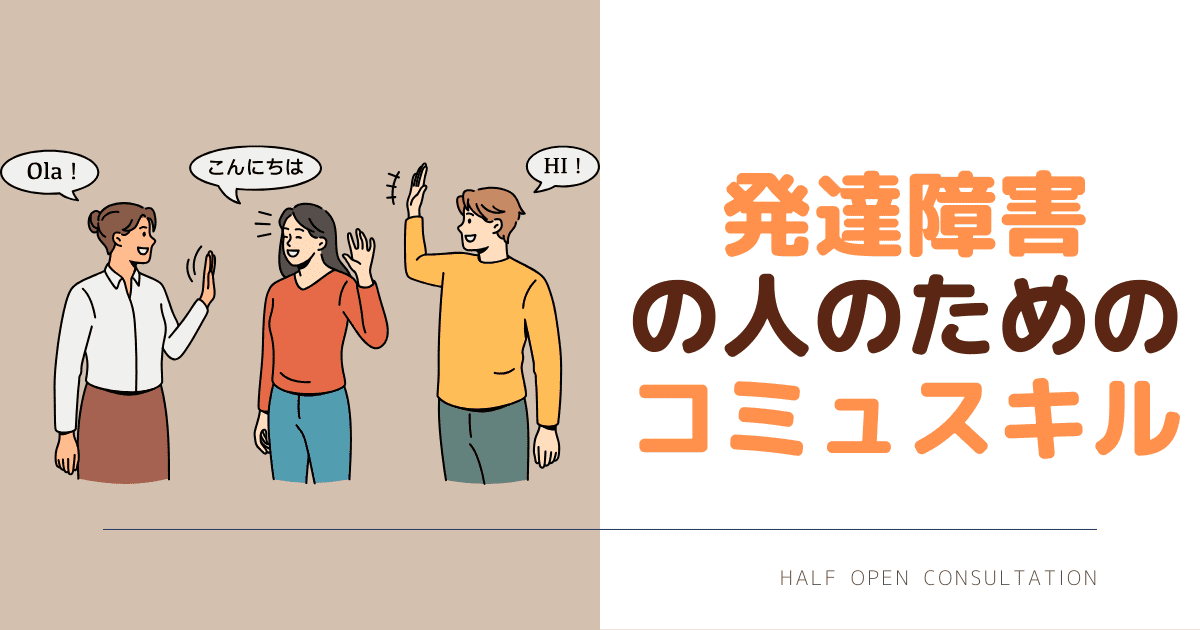
行動面でのアプローチ
発達障害の子どもは、環境の変化に弱かったり、これまで注意ばかりされてきて、自分の行動に対して自信が乏しいという特徴があります。
こうした子どもたちには、①予測可能な環境の提供と②ポジティブな強化の活用が有効です。
予測可能な環境の提供
ASD傾向のある子どもは、想像力が乏しいため、予測ができない急な出来事があるとパニックに陥ってしまいます。
すると、普段ならできることが急にできなくなってしまい、自信を低下させてしまいがちです。



ASD傾向の子どもには「ルーティーン」が安心感につながります。
その子のルーティーンを優先してあげられるように、自宅環境や毎日の過ごし方など、変えなくて良いものはできるだけ変えないようにすると良いでしょう。
毎日やることが決まっていると、ASD傾向の子どもはむしろパフォーマンスを発揮して、得意なことをますます得意にすることができるようになります。
ポジティブな強化の活用
うちの子は「勉強ができない」、「スポーツが苦手」、「友達と遊ぶのができない」と悪いところばかり目が向きがちですが。
しかし、一人ひとりにはそれぞれの強みや得意なことが必ずあります。
「パズルが得意」、「電車の時刻表を覚えるのが得意」、「穏やかで友達に優しい」など小さなことで良いので、早いくから強みや得意なことを見つけられるように気をかけておくことが大切です。
そうした強みや得意なことを伸ばしていくことが、発達障害の子どもの成長には欠かせません。
感覚過敏への対応
発達障害のある子どもは、他の子どもと比べて、感覚が過敏であるという特徴があります。
例えば
- 蛍光灯の白い光が眩しく感じる
- エアコンの音が不快
- 教室の匂いが苦手
- 洋服のタグがチクチク感じる
- ちょっと触れただけで痛く感じる
などがあります。
こうした感覚過敏がわかっていれば対策が取れますが、周囲の理解を得る努力をすることも親としては求められるでしょう。
発達障害の感覚過敏については、次の記事でも詳しく説明しています。
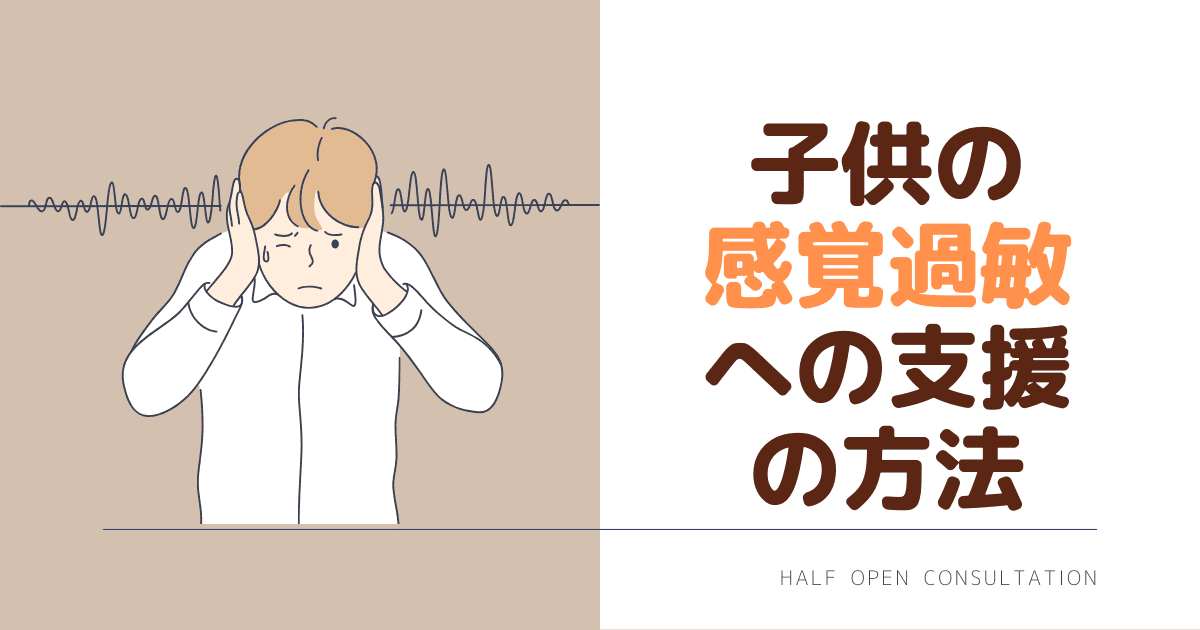
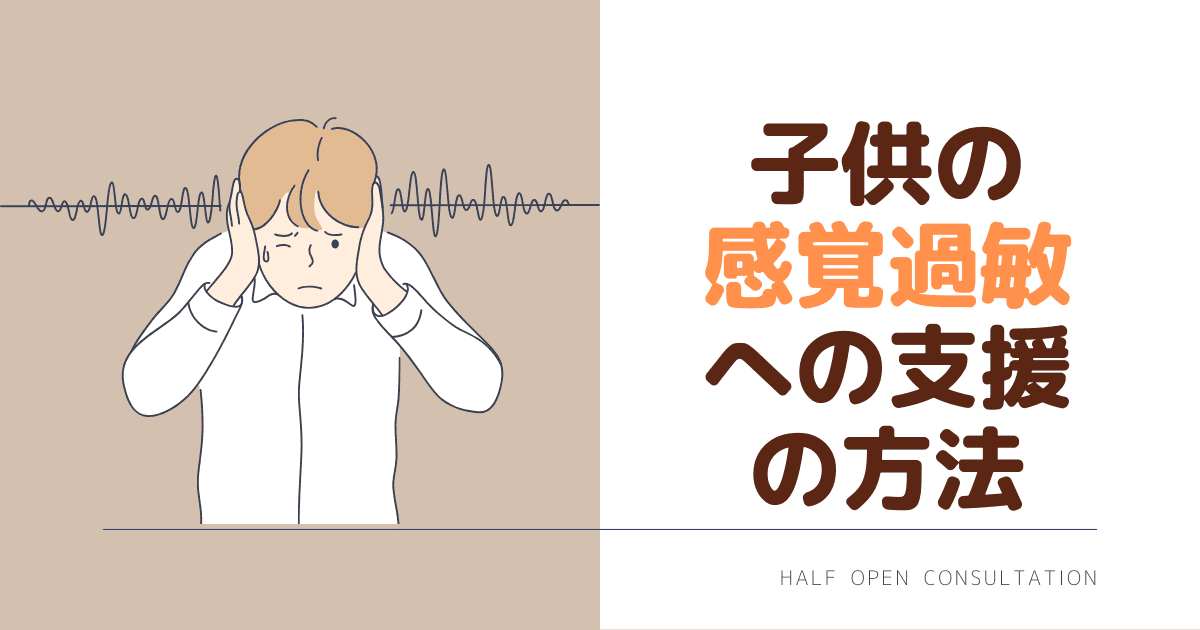
発達障害の悩み相談
もしもお子さんの発達障害にお悩みで、どこに相談すれば良いかわからない方は、専門機関に相談することをお勧めします。
発達障害全般であれば「発達障がい者支援センター」、子どもの発達や問題行動については「児童相談所」、診断が必要であれば「小児精神科病院」などです。
しかし、そうした専門機関に直接行くのは勇気が必要です。
そうした方には「オンラインカウンセリング」をおすすめしています。
詳しくは次の記事で詳しく説明しています。


- 国内最大のオンラインカウンセリング
- 600名を超える専門家に相談できる
- カウンセリング方法を4種類から選べる
- 誰にも知られず、匿名での相談が可能
\まずは無料会員登録から!/
発達障害の二次障害
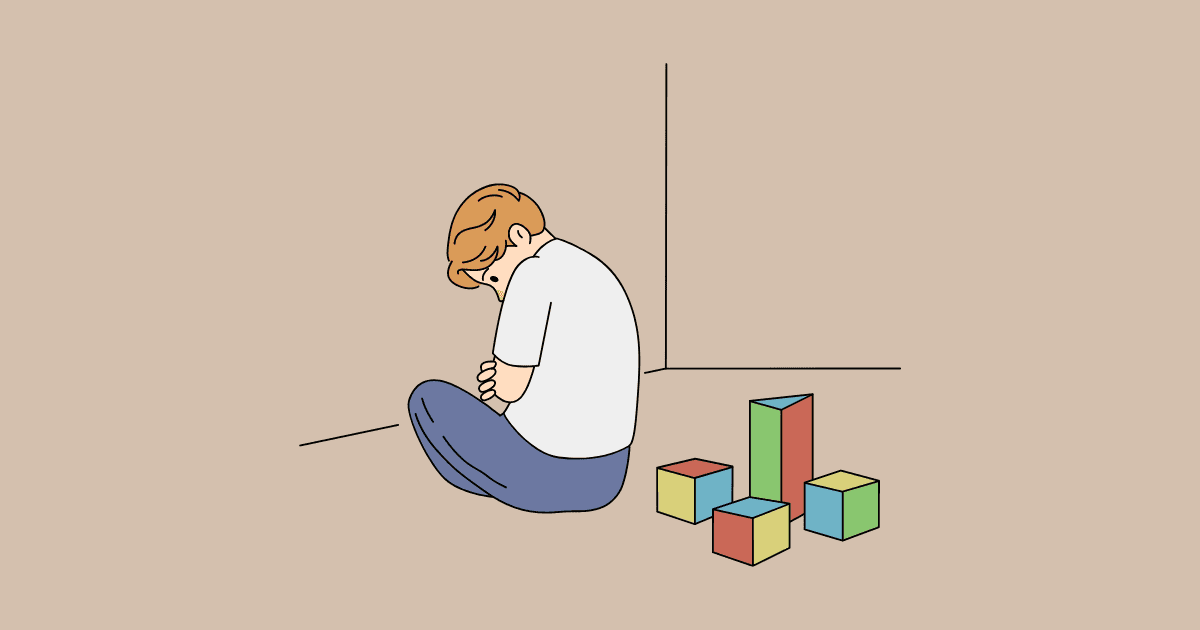
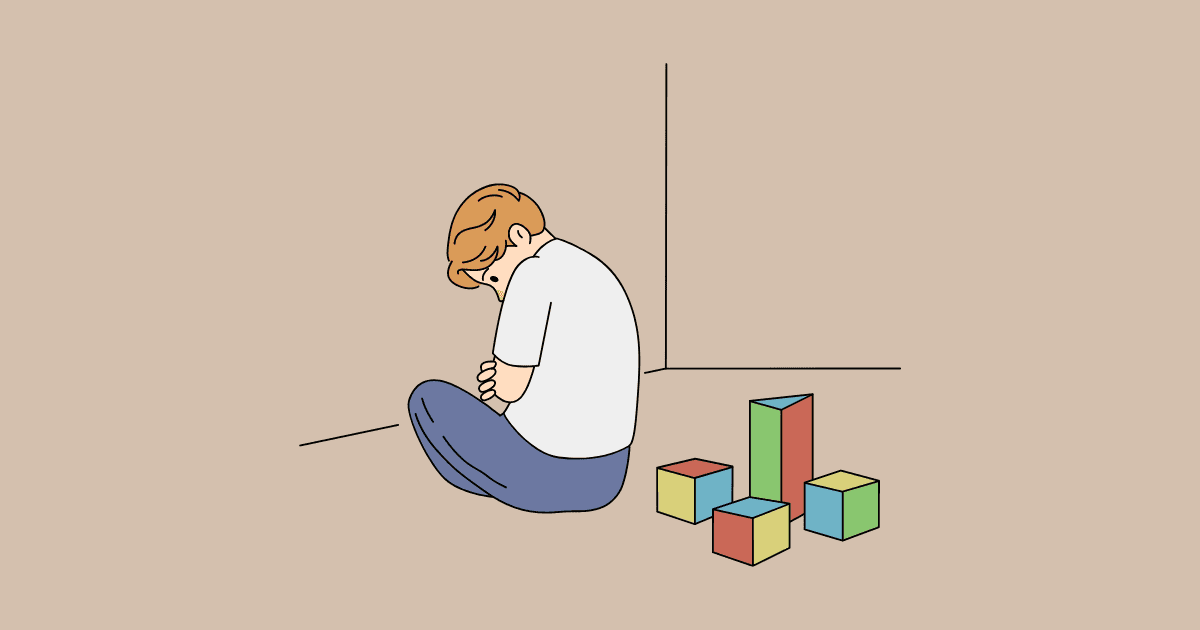
発達障害のある子どもや、その傾向のある子どもは、本人に自覚や悪気がなくても他者に迷惑を掛けてしまうことがあります。



そうした子どもは、周りの大人に注意をされることが多くなります。
子どもは一時的には素直に受け止めて直そうと努力をしようとします。
しかし、発達障害は脳機能の障害とも言われているように、簡単に直すことができず、自分の行動に思い悩むようになります。
すると、余計にその行動が悪化してしまい、周囲から再び注意を受けるようになります。
初めは「自分がいけないんだから,自分で気を付けよう」と考えていたのが、「どんなにやってもうまくいかない。」と傷付き悩み落ち込むようになります。
更には「どうせ自分なんて頑張ってもできない。どうでもいい。」などと不満やイライラが高まってきて、別の問題行動や身体や心の不調が生じます。
このように、発達障害があることを背景として、別の問題が生じてしまうことを「二次障害」と言います。
二次障害には、「行動面」「身体面」「精神面」でそれぞれ問題が生じることがあります。
身体面:頭痛、腹痛、抜け毛など
精神面:うつ、イライラしやすい、不眠など
行動面:家出、暴力、強迫的に手洗いを繰り返すなど
子育ての悩みで問題になりやすいのは、行動面の問題になりますが、その対応はかなり困難になります。
だからこそ、発達障害のある子どもについては、その子が傷付く前に、その気持ちをきちんと理解して、適切な対応をとることが大切です。
発達障害の二次障害については、次の記事で詳しく説明しています。
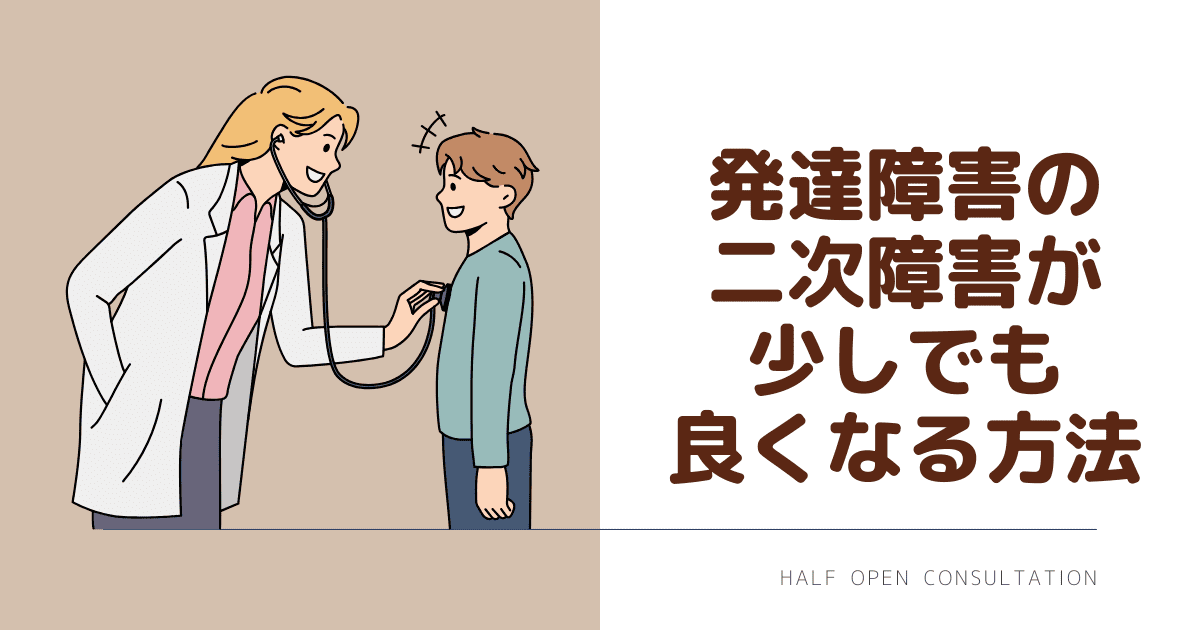
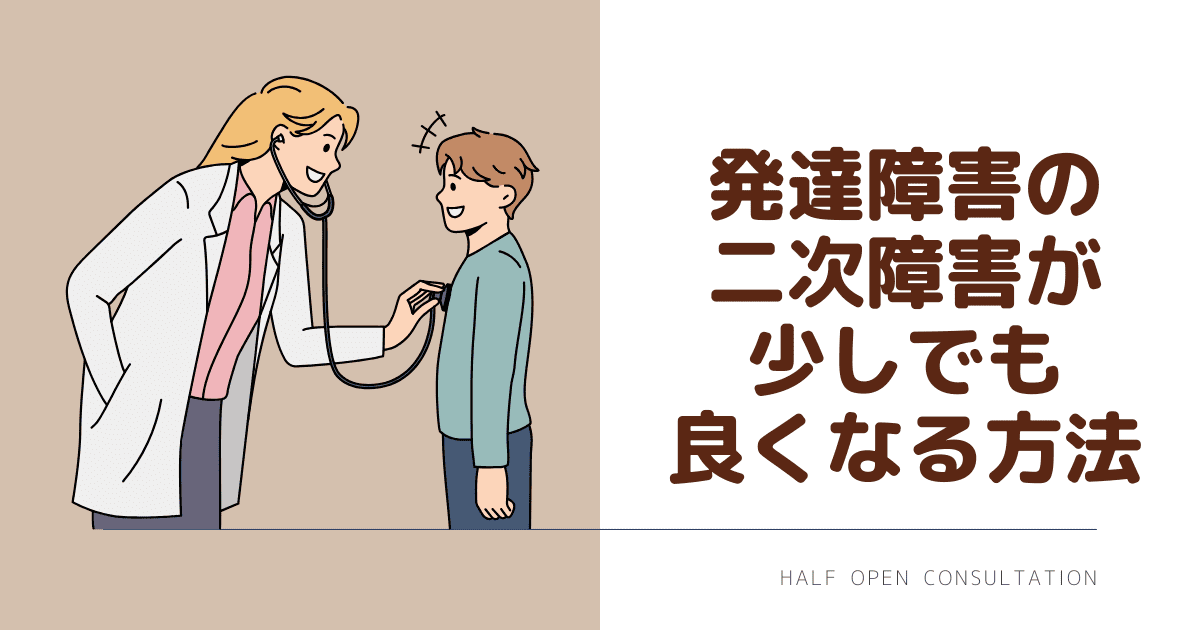
まとめ
この記事では、発達障害の子どもと接する上で大切なことについて説明しました。
発達障害のあるお子さんを育てるのは非常に苦労すると思いますが、その子自身が一番困っているということを理解した上で接していってください。
なお、発達障害の子どもにおすすめの学用品などを紹介した記事がありますので、併せてご覧ください。
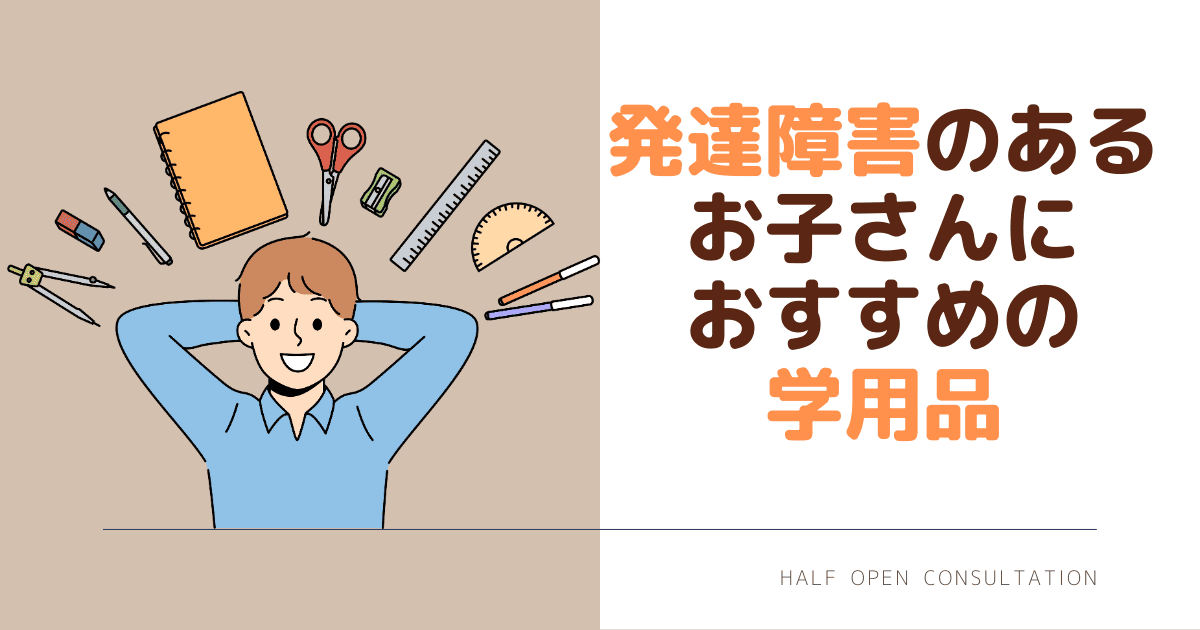
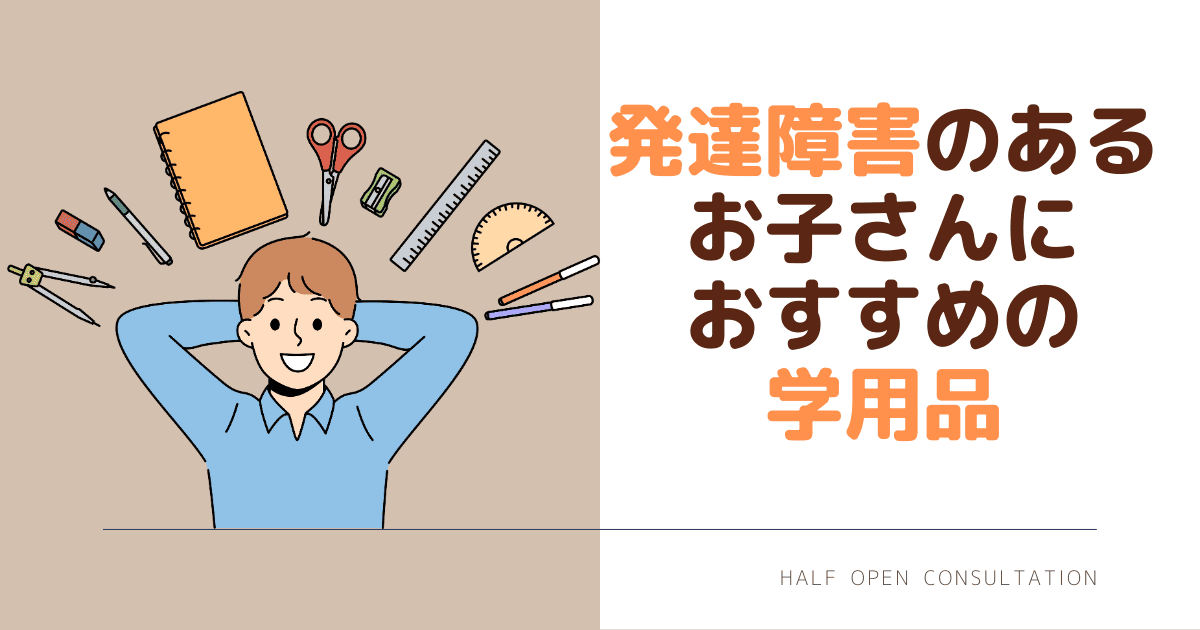
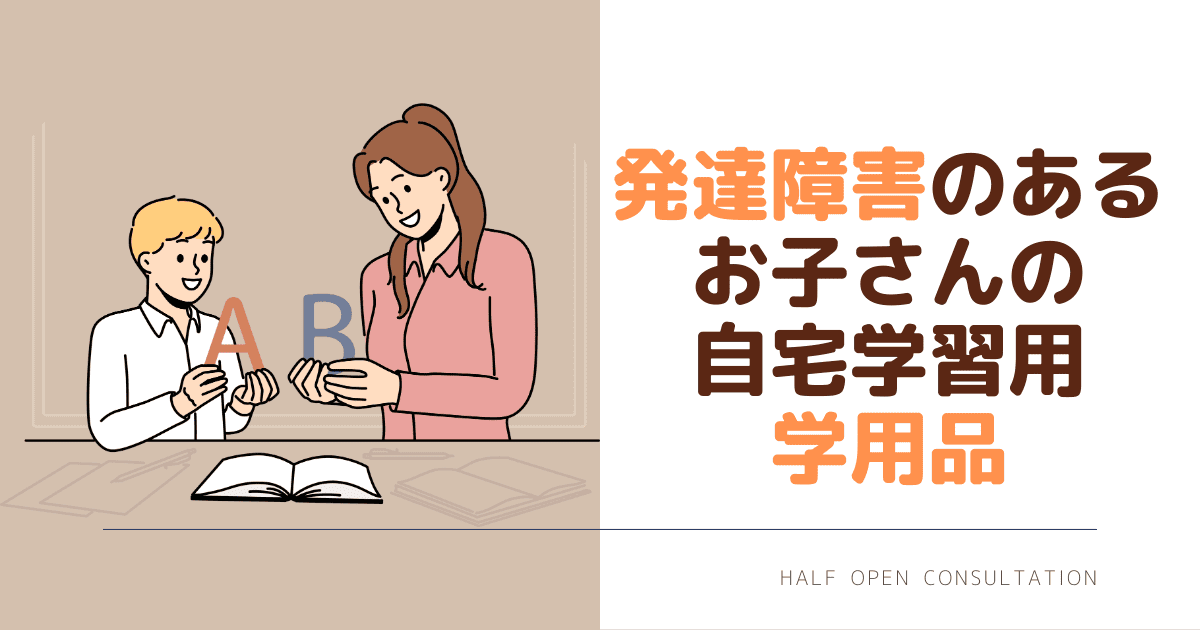
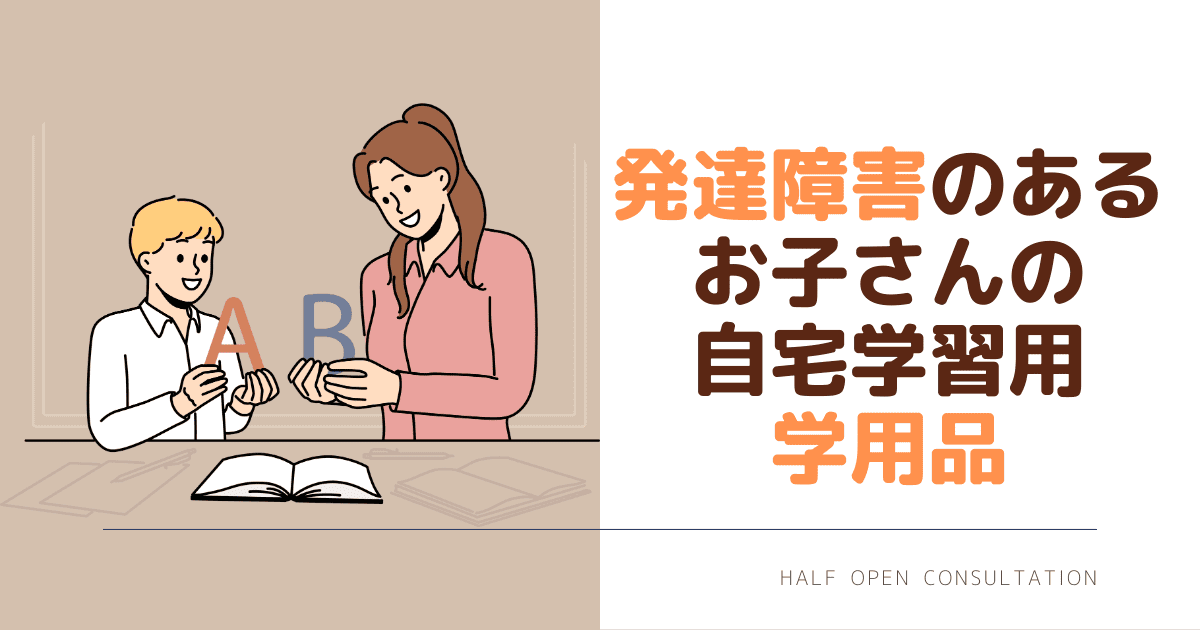
最後までお読みいただきありがとうございました。
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村