子どもの将来の成功や幸せを願わない親はいないでしょう。
子どもの成功や幸せのためには、学力だけでなく、「自己肯定感」と「非認知能力」を伸ばすことがとても大切です。
自己肯定感が高い子どもは、困難に直面しても前向きに挑戦し、自ら学び成長する力を持っています。
非認知能力(粘り強さ・協調性・感情のコントロールなど)は、社会で生き抜く力の土台となります。
本記事では、心理学の視点から、子どもの自己肯定感と非認知能力を高めるために親ができることを解説します。
- 子どもの自己肯定感を育てたいと考えている親
- 学力だけでなく、子どもの生きる力を伸ばしたいと考えている親
- 自己肯定感が低いと感じる子どもに、どう接すればよいか悩んでいる親
この記事は、おおたとしまさ氏監修の書籍「究極の子育て 自己肯定感×非認知能力」を参考にしています。
 ゆう
ゆう重要なポイントを抜粋しています。
強くしなやかなメンタルを手にいれる
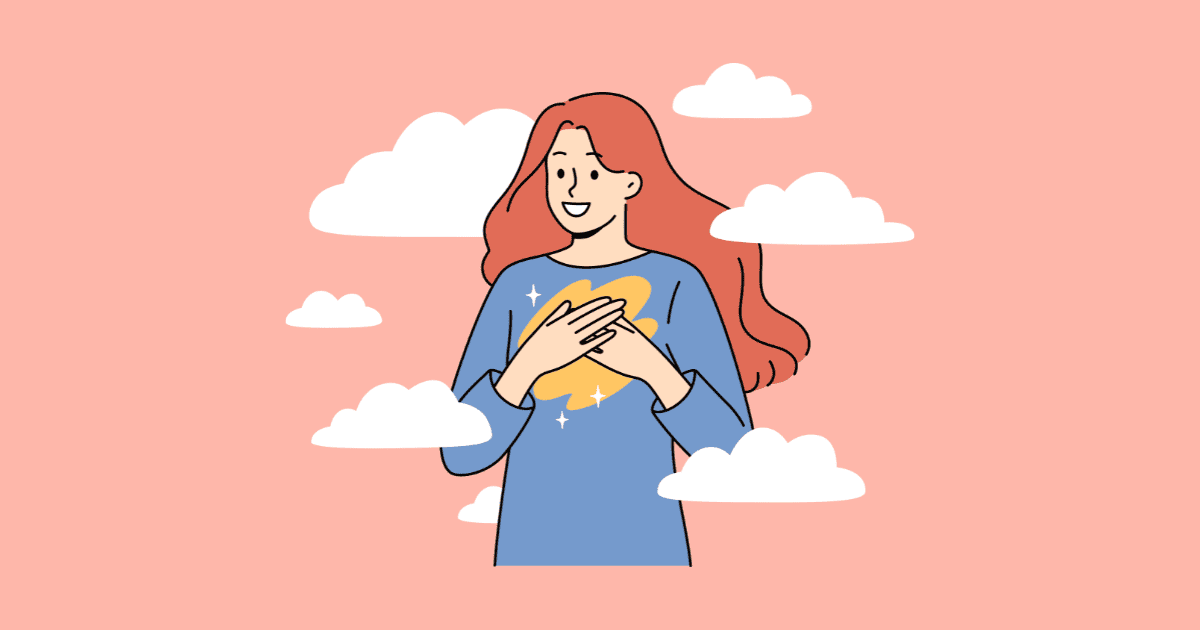
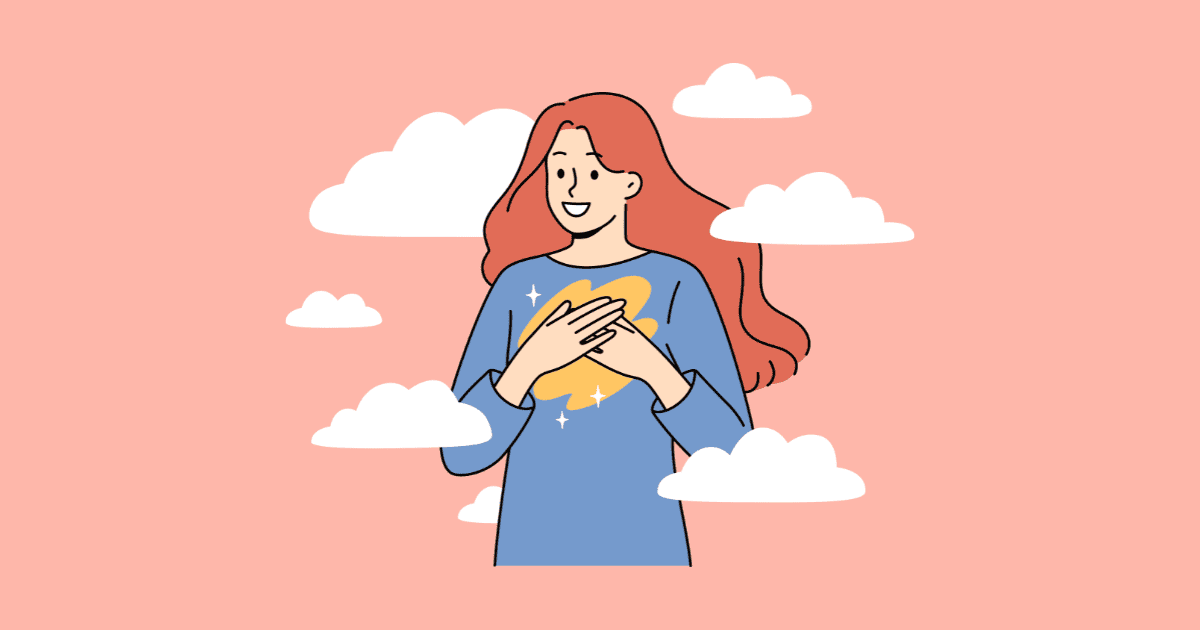
人生には成功もあれば、失敗や困難もつきものです。
そんなときに大切なのが、強くしなやかなメンタルです。
強さとは単なる我慢ではなく、挫折しても立ち直る力や、自分の感情をコントロールする力を指します。
特に10歳までの子どもは、失敗を恐れずに挑戦できる環境が重要です。
本章では、子どもがストレスやプレッシャーに負けず、前向きに生きていくための心の育て方を紹介します。
大切なのは、ストレス発散の選択肢を示すこと
仕事や家事、日々の子育てに追われてたくさんのストレスを抱えている方が多いと思います。
この「ストレス」ですが、その要因について大きく分けると次の2つに分けられます。
ライフイベント:人生のうちで何度も経験することのないストレス(入学・卒業、就職、結婚など)
デイリーハッスル:日常的なストレス(満員電車、人間関係など)
こうしたストレスは、大人だけでなく、子どもも感じています。
生まれたばかりの赤ちゃんでも、「お腹が空いた」「おむつを替えてほしい」「ママがいないよ」といった状況で泣きますが、それはストレスが影響しているといえます。
幼稚園や保育園では、友だち関係のストレスが出てきますし、小学生になればテストや通知表などで他者から比べられることによるストレスも生じます。
親であれば、できるだけ子どもにストレスがないようにしてあげたいと思うかもしれません。
しかし、本当にストレスをなくしていいのでしょうか?
ある程度のストレスは、人間が生きるために重要です。
「自分が生きていくためにするべきことをしないといけない」という危機感を与えてくれるのがストレスです。
つまり、子どものストレスを排除し過ぎることは危険だということです。
ストレスが生じたときに、そのストレスとどう向き合っていけばいいのかを、子どもが小さいうちから教えてあげることが大切です。
ストレスに対する対処法(ストレスコーピング)は次の2つです。
- 問題解決型:未来への不安に対し、その不安を解消する行動を取る
- 情動焦点型:過去の問題に対し、気を紛らわせるなどしてストレスを発散する



子どもに教えるときは、どちらなのか明確に区別する必要まではないです。
子どもは自分で選択できる手段が限りなく少ないので、親が選択肢を提示してあげる必要があります。
子どもがストレスを感じているようであれば、子どもの好き嫌いに注目して選択肢を示してあげましょう。
幼い子どもなら、好きなものをいくつか提示してあげて、その中から選ばせると良いです。
子どもが成長してきて小学校中学年くらいになると、具体的な問題を解決する必要も出てきます。
例えば、勉強に集中できなくてストレスを感じているのであれば、親が勉強を見ていた方がいいのか、一人で自分の部屋でやる法外のか、あるいは塾に通いたいかなど、子どもと相談しながらいろいろな選択肢を示してあげるのです。
- ストレスは生きていくために必要なもの。やみくもに排除しようとしないこと
- 子ども自身がストレス発散法を見つけられるよう、選択肢を示してあげる
- 親が子どものストレス対処法を決めつけず、時間をかけて一緒に考える
親子でできる「レジリエンス」の簡単トレーニング法
子どもが小学生になると、幼児の頃と比べてさまざまな悩みを抱えるようになります。
それは、「いいこと」です。
なぜかというと、幼い頃には悩まなかったようなことにも、心が発達したことで「悩めるようになった」からです。
未来を展望し過去を振り返る力を得て、対人関係が広がると、悩みも多くなるものです。
子どもにとって、悩みやトラブルは成長の糧です。
失敗して学ぶのが人間であり、未熟な部分をぶつけ合うことが子どもにとっては大切な学びなのです。
ただ、日本人の場合は、子どもにも親が「怒っちゃダメ」という言葉をかけるといった具合に、ネガティブな感情を封じ込めようとする傾向にあります。
子どもがネガティブな感情をすでに持ってしまっていれば、どんなに封じ込めようとしてもゼロにはなりません。
親は、子どものネガティブな感情を封じ込めるのではなく、感情任せになるのでもなく、マネジメントする力を鍛える必要があります。
そこで、ネガティブな感情の一つである「劣等感」に負けないためのトレーニング、すなわちレジリエンス、心の回復力を鍛える4つのトレーニングを紹介します。
心を回復する上で鍛錬しておく4種類の「筋肉」をイメージするよう子どもに伝えてトライさせてみましょう。
| 「I am」マッスル | 私は○○ | 私は優しい、私は賢い、など自分そのものを肯定する |
| 「I can」マッスル | 私は○○できる | 私は泳げる、私はピアノを弾ける、など自分ができることに着目する |
| 「I like」マッスル | 私は○○が好き | 私は花が好き、私は漫画が好き、など好きなもの・ことを連想する |
| 「I have」マッスル | 私には○○がいる | 私は可愛いペットを飼っている、私には頼りになるお父さんがいる、など大切にしているものに目を向ける |
目的は、自分が持ついいところ、いいものをつねに「見える化」することで劣等感に打ち勝ち、自分の強みを資源にすることです。
子どもには、寝る前にそれぞれ3つくらい思い浮かべさせる、あるいは書き出すようにしてみましょう。
レジリエンスについては、次の記事も参考にしてください。
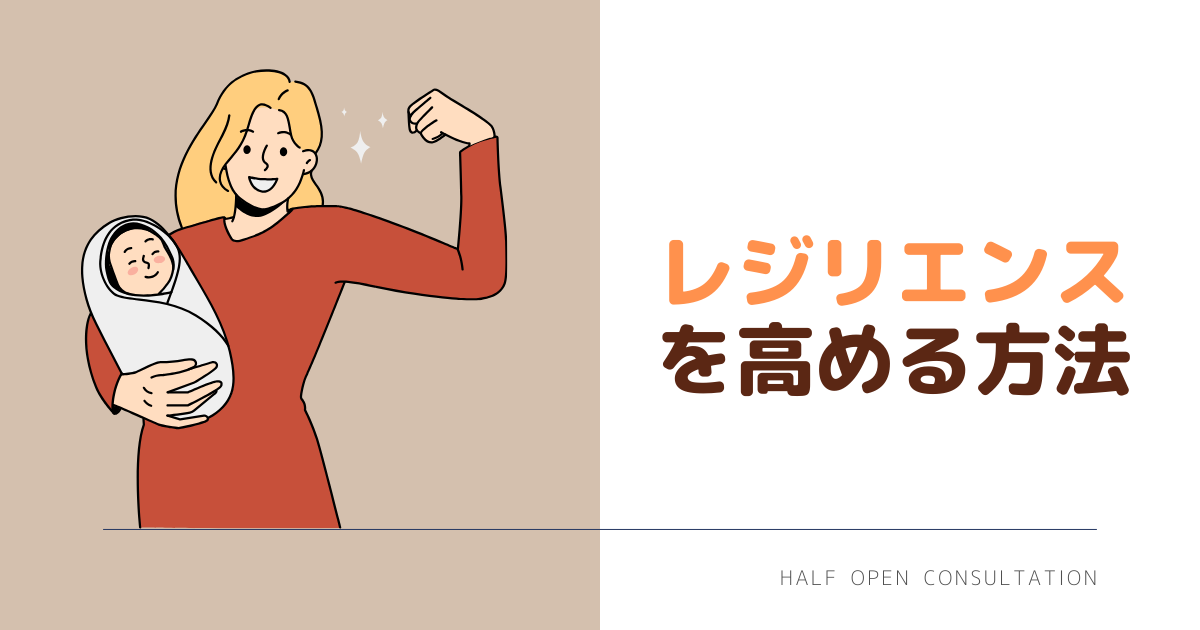
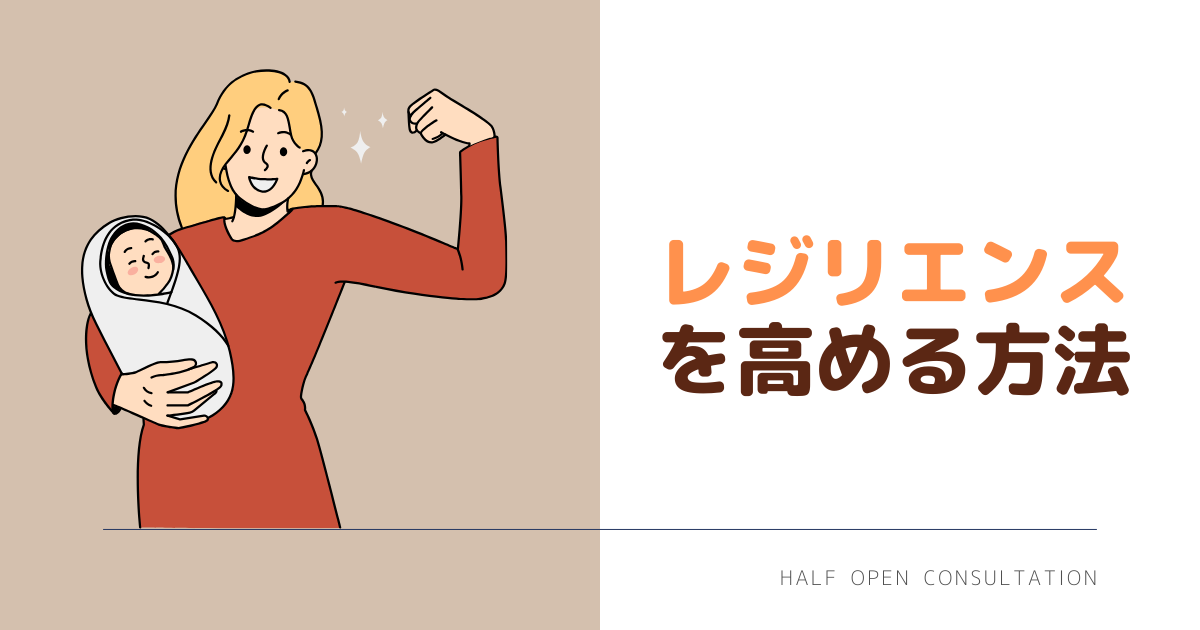
- 子どもが悩んだりネガティブな感情を持ったりするのは成長の証
- 劣等感に負けないために、「レジリエンス」を鍛えよう
- うまくいかないことがあっても、けっして性格のせいではない!
ソーシャルスキルを身につける
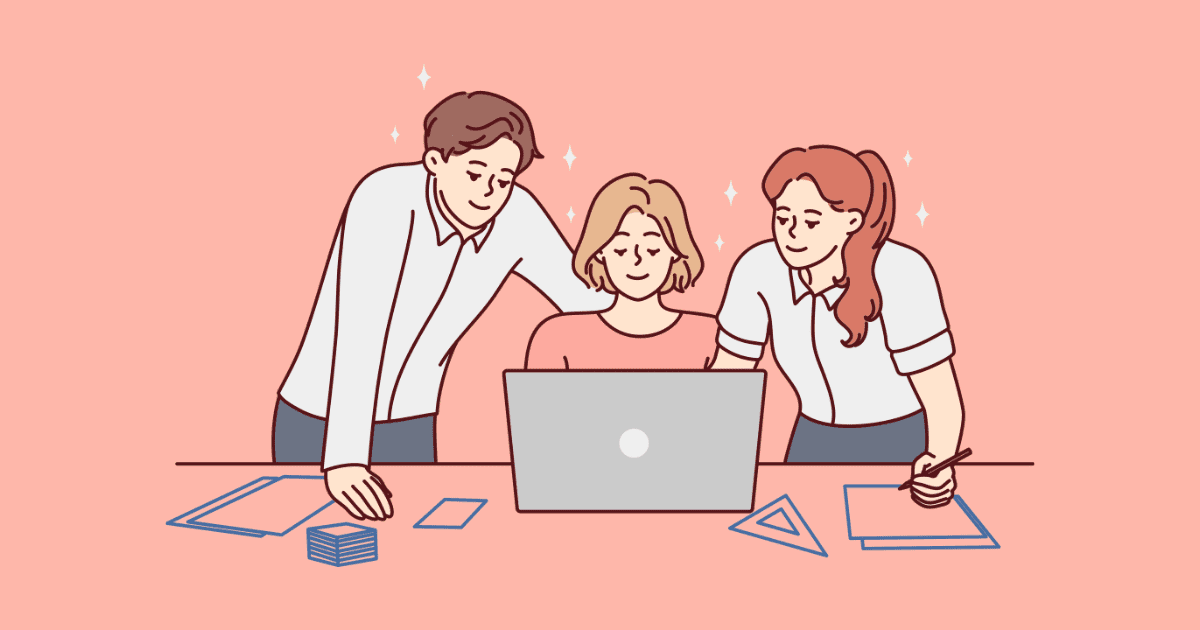
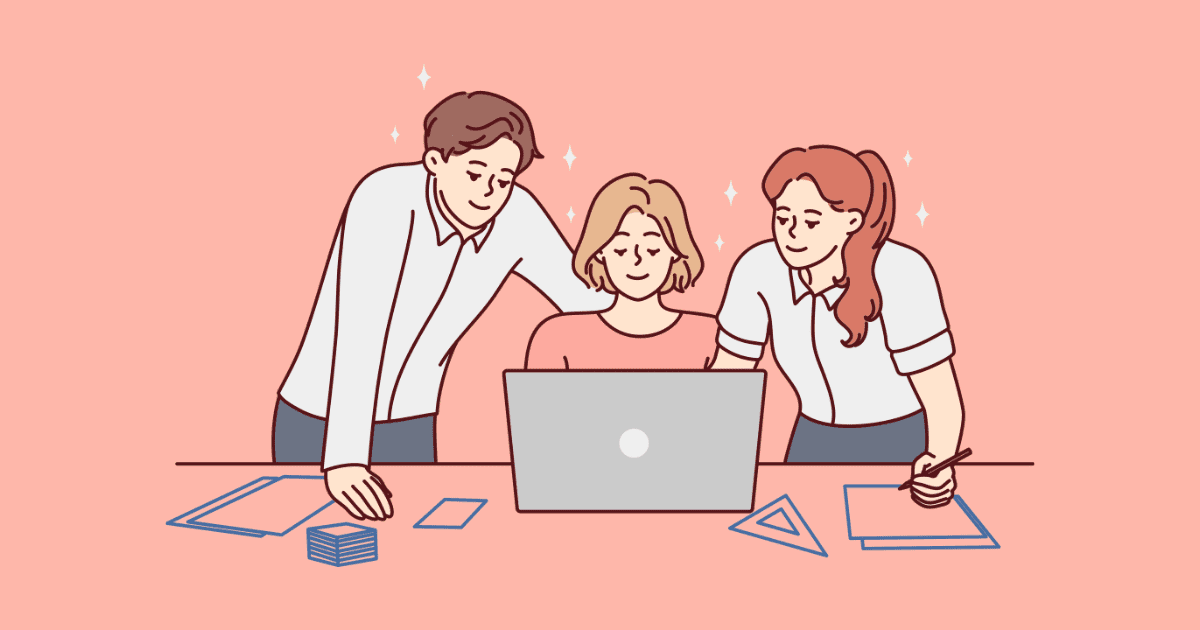
人との関わり方は、子どもが社会で生きる上で欠かせない力です。
友達との関係を築き、協力し、自己表現をする力は、大人になってからの人間関係の土台になります。
ソーシャルスキルが高い子どもは、トラブルを減らし、周囲と良好な関係を築くことができます。
本章では、子どものコミュニケーション力や共感力を育むために、家庭でできる具体的な方法を解説します。
子どものソーシャルスキルを伸ばす家庭教育法
ソーシャルスキルはけっして特別な技能ではなく、多くの人が日常的に使っているしぐさや行動のことを意味します。
例えば、手の振り方一つで、「こっちにきて」や「バイバイ」とも伝えることができます。
このように、社会生活をうまく営むために「こういう場合はこういう振る舞いをする」というフォームのようなものです。
昔であれば、親や祖父母、近所の大人たちが子どもたちに教えてきました。
しかし、核家族化が進むにつれて、それが難しくなってきています。
また、子どもは遊びを通じてソーシャルスキルを身につけるものですが、習い事が増えたり遊ぶ場所が減ったりして、昔のように友達と遊ぶ機会も減ってきています。
今は、親が教えることができなければ、子どもはソーシャルスキルを学ぶことができないのです。
そこで、親は、子どものいいところをどんどん伸ばしてあげるために何をするべきなのかという発想で、もっとポジティブに家庭教育をすると良いでしょう。
親が人生を楽しんでいて、いつもニコニコしていて、「人生って面白いよ」と伝えてくれたら、子どももワクワクした気持ちで毎日を過ごせます。
また、ソーシャルスキルについて、基本的には年齢によって必要なスキルは変わることはありません。
年齢によって理解力には違いがあるので、それに合わせた教え方をすれば良いのです。
- 3〜4歳児:「お口はチャックね」と静かにすることを教える。
- 小学生:「相手が話しているときは顔を向けましょう」と態度を教える。
- 中学生:「相手の話の内容に注意しましょう」と内面的な部分も教える
ところで、親は子どもに見返りを求めてはいけません。
教育熱心な親は、教育に対して非常に真面目です。
そして、人間というのは努力すればするほど、相手にも期待してしまうものです。
しかし、子どもは親からの期待を背負ってしまうと、ストレスに感じてしまったり、のびのびとした気持ちになれなかったりしてしまいます。
親が一番求められるスキルは、子どもの発するたくさんの欲求に対して「応答するスキル」です。
これはコミュニケーションスキルになりますが、コミュニケーションを通じて、子どもは自分が提供した話をちゃんと親が聞いてくれたことの喜びや、親とのつながりを感じます。
それが、人間にとって重要な「自尊心」や「自己肯定感」につながります。
- 子どもが自由に遊べる機会をつくってあげよう
- 親自身が人生を楽しみ、ポジティブに家庭教育をする
- 子どもに見返りを求めるのでなく、子どもの欲求に「応答」しよう
自己主張できる子に育てるには、「気がね」をさせないこと
これからの時代に求められるのは「自己主張する」力です。
この力に反するのが、「気兼ねする」力です。
「気兼ね」とは、他人に対して気を遣って、自分が本当にしたいことをしないでいるということです。
気兼ねする子どもにしてしまう子育てには、「4つのNGしつけ」というものがあるようです。
- 他人の目を気にするしつけ
- 他人と比較するしつけ
- 頭ごなしに叱るしつけ
- 禁止が多いしつけ
1は、「お父さんに叱られるよ」「先生に言いつけるよ」といったしつけです。
静かにしなくてはならない場所で子どもが騒いでいるのであれば、「静かにしていてね」と言えばいいだけです。
2は、子どものきょうだいや友達と比較するしつけです。
「お兄ちゃんは1年生の時にはもっとしっかりしていたのに」などと言われると、子どもは周りの評価を気にするようになります。
3と4は、やりたいことを全否定されたり禁止されたりすれば、子どもは自分の本心を親にも見せなくなってしまいます。
子どもを気兼ねする人間にしないためには、まずこれら「4つのNGしつけ」をしないように心がけることです。
それから、「待つ、任せる、見守る」という3つの姿勢を意識することです。
また、親の価値観を優先しないようにすることも重要です。
子どもの人生は子どものためのものであって、親のものではありません。
子どもと話し合いながら、子どもの人生を一緒に考えていくスタンスが必要なのです。
- 「気兼ね」する子どもにしてしまう、否定ベースのしつけに注意
- 子どもの力を信じ、「待つ」「任せる」「見守る」を意識しよう
- 子どもの人生は子どものもの。親の価値観を優先しない
非認知能力を高める
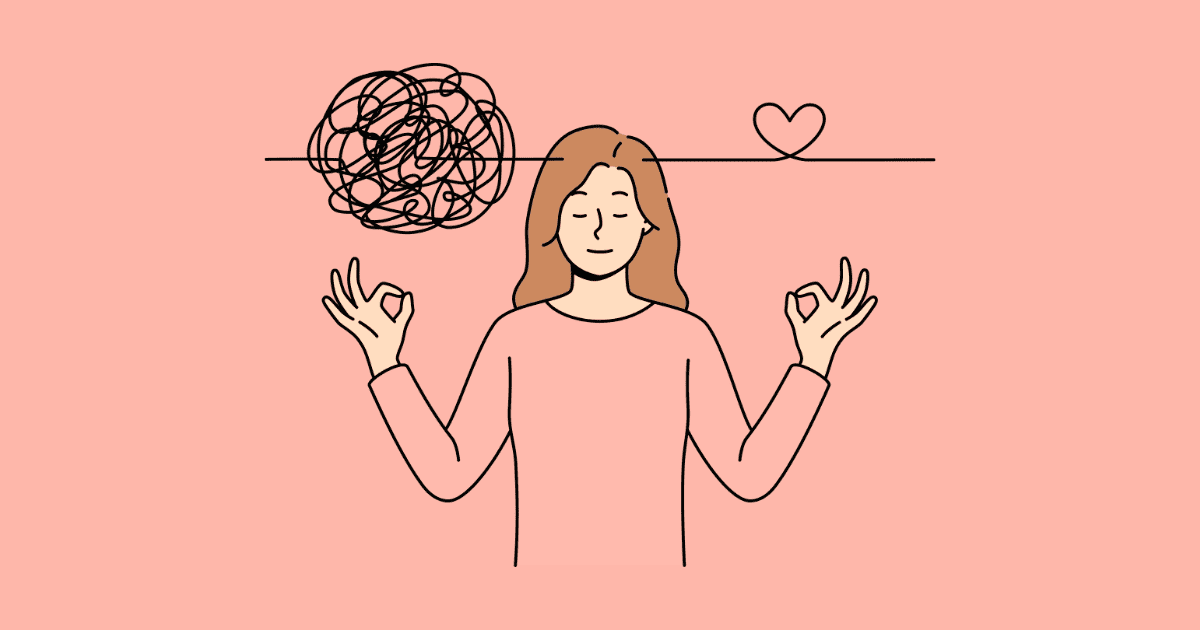
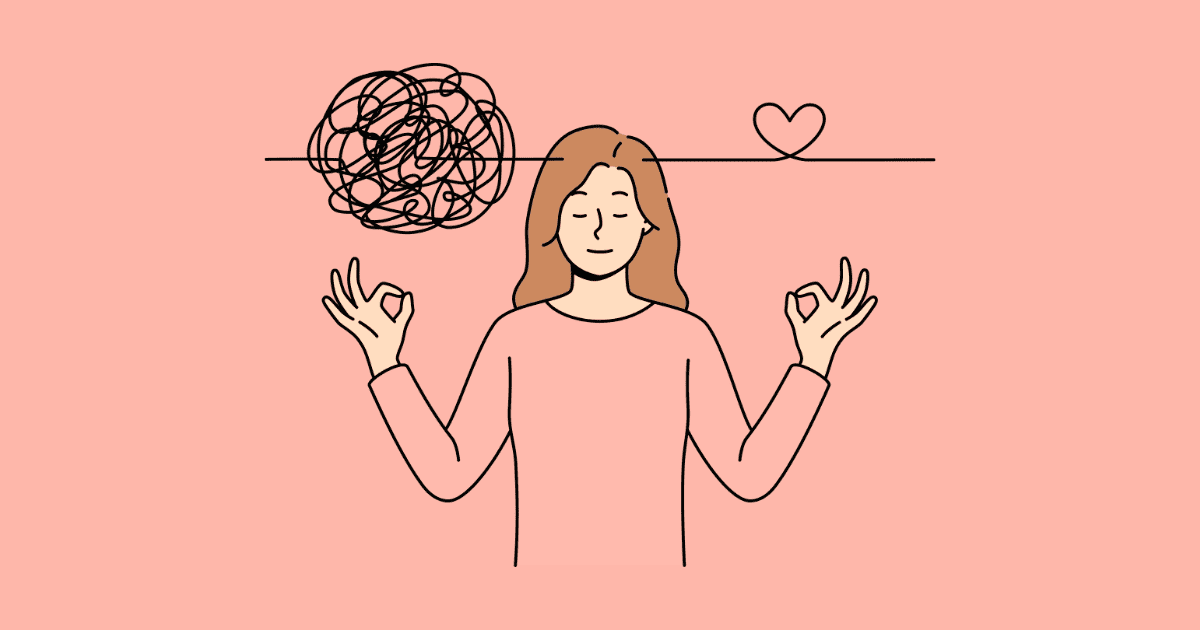
近年、学力以上に重要視されるのが「非認知能力」です。
粘り強さ、やる気、自己制御力など、将来の成功に大きく影響する力ですが、学校では直接教えてくれません。
では、どうすれば子どもの非認知能力を伸ばせるのでしょうか?
親の関わり方次第で、子どもは「できる!」という自信を持ち、主体的に行動できるようになります。
本章では、家庭でできる実践的な方法を紹介します。
子どもが「目をキラキラさせる世界」があればOK
非認知能力とは、何か特別なものなどではなく、昔であれば子どもの普段の遊びや当たり前の子育ての中で勝手に育っていたものです。
かつての子どもたちは、豊かな自然の中で元気にたくさん遊び、異年齢の子どもたち、あるいは異世代の大人とも触れ合う機会が数多くあり、多様で具体的な体験を通じた経験を積み重ねていました。
すると、遊びの中でうまくいかないことがあっても、熱中して続けるうちにうまくいくといった経験を通じて、困難を乗り越えるために必要な意志力や忍耐力、やり抜く力を獲得することができました。
しかし、今は習い事に忙しく、単純に遊ぶ時間自体が大きく減っています。
そのため、遊びを通じて非認知能力を得る機会が激減しているのです。
では、親はどうすれば良いでしょうか?
それは、大人からしっかりと受け止められる経験を子どもにさせること、そして、子どもの興味関心を大人が大切にするということです。
非認知能力の多くは、「主体性」に関わるものです。
人間は、好きなことに対してであれば、主体的に取り組むことができます。
つまり、子どもの非認知能力を伸ばしてあげるためには、子どもの興味関心を大事にしてあげることがもっとも重要です。
特に、子どもにとって最高のおもちゃは「自然物」です。
子どもと一緒に自然のある場所で一緒に遊ぶように心がけると良いです。
家の中で遊ぶ際には、空き箱や廃材などで自由に遊ばせることも、子どもにとっては貴重な経験になります。
子どもにとって興味関心から行うような行動であれば、多少親にとって迷惑なものであっても、自由にやらせてあげると良いでしょう。
こうした行動は、意欲や探究心などの非認知能力だけでなく、認知的な力を伸ばすことにもつながるでしょう。
- 非認知能力、認知能力の両方が大切。非認知能力が伸びると認知能力も伸びる
- 子どもの興味関心を大人がしっかりと受け止め、大切にしてあげよう
- 子どもの想像力と創造力をフル回転させられる遊びをさせてあげよう
学童でのさまざまな経験が、子どもに「学び」を授ける
共働き世帯なら、子どもを学童に通わせている家庭も多いと思います。
子どもの成長にとって、学童で過ごす時間はとても有意義なものです。
小学生の時期は、自分の強みを発揮する力や自発性、主体性など、非認知能力を伸ばすための時期といえます。
学校での授業だけでなく、放課後や長期の休みをどのように過ごして非認知能力を高めるかがとても大切です。
子どもは視野が狭いものです。
だからこそ、たくさんのさまざまな経験をする必要があります。
学童の自由時間に、工作をしたり、宿題をしたり、友達と一緒に遊んだりと、毎日異なるたくさんの経験を重ねられます。
また、学童では「縦割り」の社会も経験できます。
年齢が違う相手とのコミュニケーションをしっかりと学ぶことができる場所といえます。
自分の思いが必ず通るわけではないのが実際の社会であるという現実を小学生のときから学べるメリットもあります。
- 放課後や長期休みなど、「課外」の時間をどう過ごすかが大切
- 学童はさまざまな体験によって視野が広がり、非認知能力が高まる
- 学童特有の「縦割り」で、年齢のちがう相手とのコミュニケーションが学べる
自己肯定感を育む
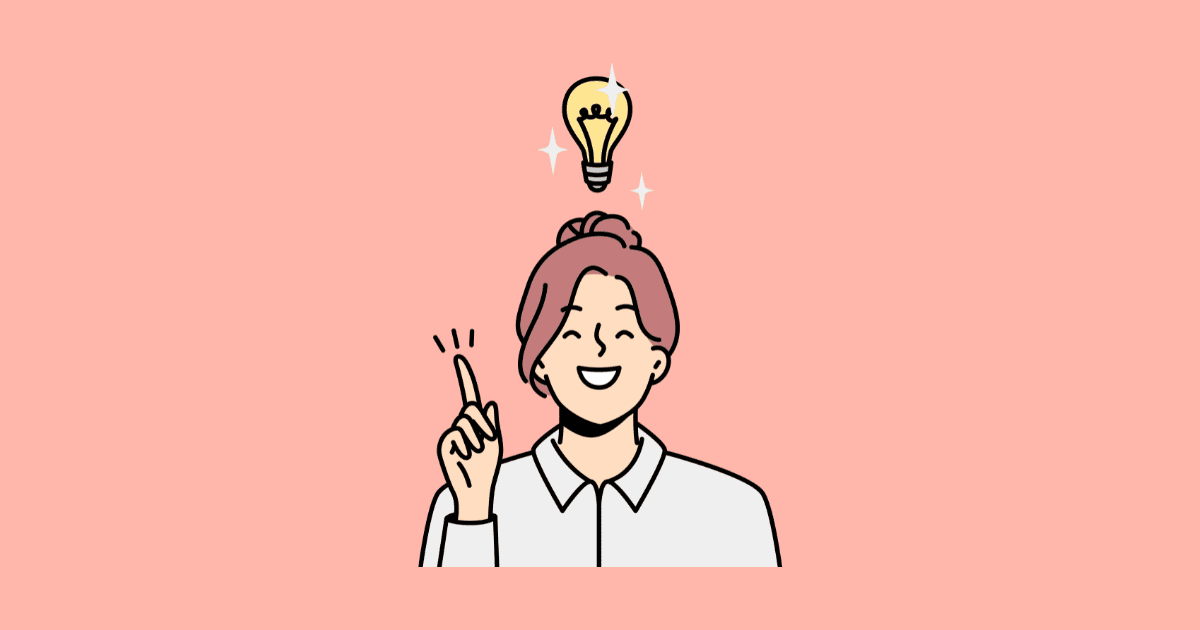
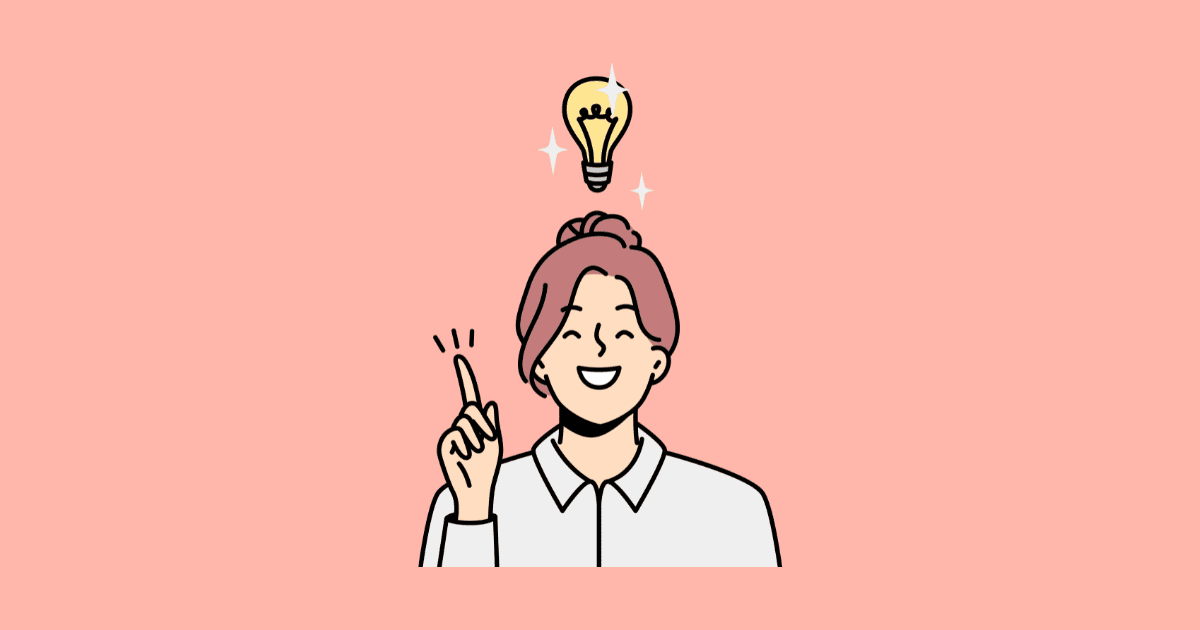
自己肯定感が高い子どもは、自分の価値を認め、自信を持って行動できます。
一方、自己肯定感が低いと「どうせ無理」、「自分なんて…」と挑戦する前に諦めてしまうこともあるでしょう。
親の何気ない言葉や態度が、子どもの自己肯定感に大きな影響を与えます。
本章では、「子どもを否定せずに見守る」「努力を認める」など、今日からできる自己肯定感の育て方をお伝えします。
「Iメッセージ」で親の気持ちを伝えて!
親が子どもと話をするとき「YOUメッセージ」と「Iメッセージ」を意識することで、子どもの自己肯定感を育むことができます。
YOUメッセージ:「あなた」を主語にしたメッセージ
Iメッセージ:「私」を主語にしたメッセージ
例えば、「あなたって聞き上手ですね」は、YOUメッセージです。
「あなたを話していると、(私は)すごく楽しいです。」は、Iメッセージです。
YOUメッセージには、「あなたはこうだ」という評価のニュアンスがあることがわかりますか?
いい評価であれば問題ないですが、そうでない評価になると相手は気分を害してしまうかもしれません。
家庭において、親子関係をより良好なものにするためにもIメッセージは役立ちます。
例えば、子どもが門限の時間を過ぎても帰宅せず、ようやく帰ってきた子どもに対して、どのような言葉をかけますか?
もしかすると「何時だと思っているの!?」と怒ってしまいたくなる人もいるかもしれません。
そこで、なぜ怒りたくなったということをよくよく考えてみると、その怒りの背景には「心配」が隠れているのではないでしょうか?
だからこそ、声を荒げて怒るのではなく、「(私は)すごく心配だったよ。」と伝えてあげれば良いのです。
一つ中して欲しいのは、Iメッセージに思えるものの中にも、「偽のIメッセージ」があるということです。
例えば「お母さんは、あなたが間違っていると思う」「お父さんは、こうするべきだと思うよ」といったものです。
純粋なIメッセージではなく、「こうするべき」「こうしなさい」という指示・命令が含まれています。
親が自分の意見を伝える際には、子どもに自分の考えを押し付ける構造にならないように、細心の配慮をすることが大切です。



Iメッセージについては、次の記事も参考にしてください。


- 「YOUメッセージ」でなく「Iメッセージ」を使って子どもと話す
- 指示や命令を含む「偽のIメッセージ」に注意しよう
- 相手を問い詰める「なぜ」「どうして」を使うのは控えよう
「根拠のない自信」で、子どもはぐんぐん伸びていく!
「自己肯定感」と「自信」は似て非なるものです。
自己肯定感が高い人間というのは、無条件に自分を認めている人間を指します。
「自分は自分なんだから、自分のままでいい」と思っているのです。
一方、自信があるように見えても、実は自己肯定感が低い人間は、「僕は○○ができるからすごいんだ」と思っているのです。
つまり、そのベースにあるのは、自己肯定感が高い人間とは対照的に「根拠のある自信」となります。
逆に、自己肯定感が低い人間の場合は、自分のベースにあるのは「○○ができる」「○○を持っている」といった根拠のある自信なので、自分と比べて「○○ができない」「○○をもていない」という他人を認めようとしません。
すると、他者と良好な関係を築くことができにくくなります。
自己肯定感の高低は、「チャレンジ精神」にも大きな影響を及ぼします。
自己肯定感の高い人は、どんな失敗をしても「無条件に認めている自分の核の部分」は損なわれることはなく、絶対に変わらない「安心感」を持っています。
一方、自己肯定感の低い人は、何かに失敗したら自分の価値が無になってしまうような「恐怖感」を持っています。
そのため、心の支えである「僕は○○ができる」という「今、あるもの」を高める方向ではなく、維持する方向に意識が向きます。
すると、どうしてもチャレンジを怖がるということになります。
そこで、親は、とにかく「子どもの言葉をばかにしないで真面目に聞く」ようにしましょう。
それは、「褒める」とは違って、「認める」ということです。
子どもの行動のプロセスそのものを認める、あるいは子どもの言葉に対して「面白いところに気づいたね」と発想そのものを認めるのです。
それが、子どもに「根拠のない自信」を与えて、自己肯定感を高めることにつながるでしょう。
- 「根拠のない自信」があれば、他者を認めて尊重できる
- 子どもの行為のプロセスや、考え方の発想そのものを認めよう
- 子どもからのサインを見逃さず、「見ているよ」と伝える
親子のコミュニケーションを深める
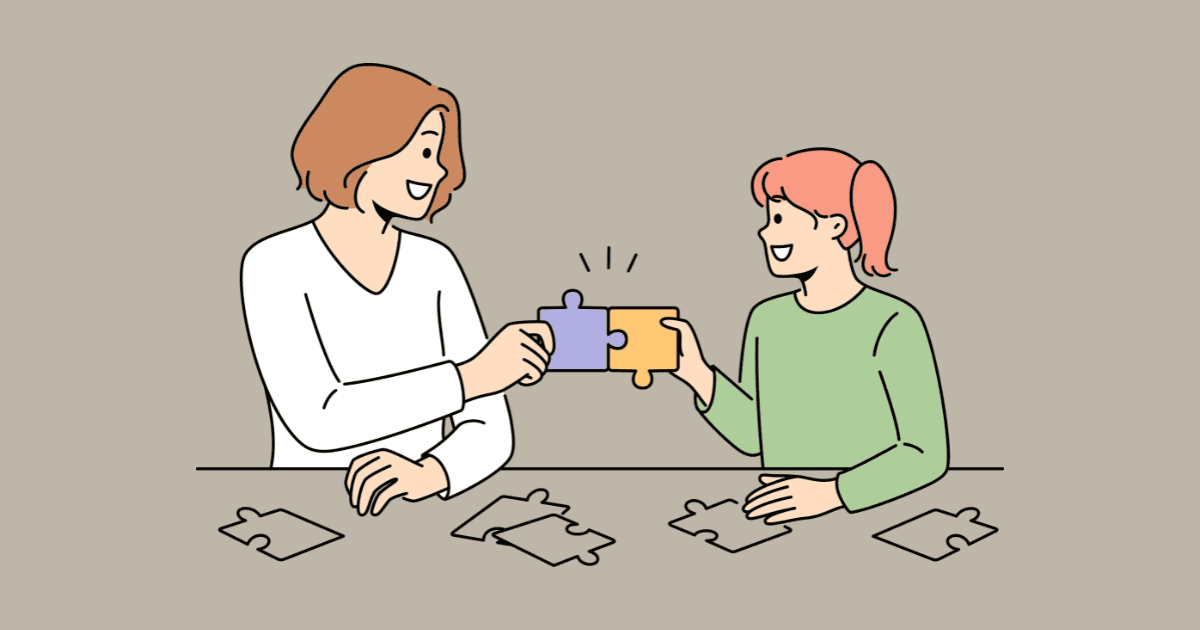
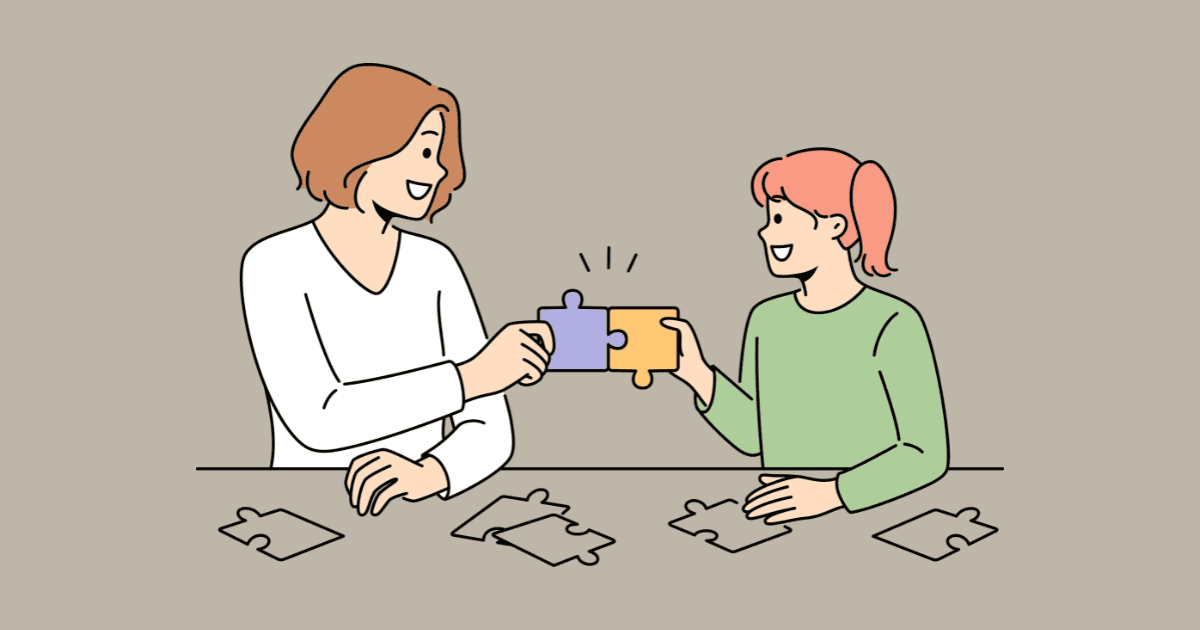
親子のコミュニケーションが深まると、子どもは「大切にされている」と感じ、安心感を持って成長できます。
一方で、忙しい日々の中で、子どもとゆっくり話す時間が取れず、すれ違いが生まれることもあるでしょう。
子どもが本音を話しやすい関係を築くには、どのような工夫が必要なのでしょうか?
本章では、日常の会話を豊かにし、親子の信頼関係を深めるためのヒントを紹介します。
なにより大切なのは親子間の「アタッチメント」
アタッチメントとは、簡単にいえば「親子の絆」のことです。
子どもが赤ちゃんの頃、何か嫌なことがあれば泣きますよね。
するとお母さんが抱っこしてくれて安心することができます。
そういう親子のやり取りの中で、子どもは親との感情的な絆を深めていきます。
このアタッチメントこそ、子どもがより良い人生を歩んでいける人間になるための礎になります。
親とのアタッチメントが形成できている子どもは、自信を持って問題解決に臨むことができます。
また、アタッチメントの形成により、子どもは感情をコントロールする力を獲得していきます。
親が泣いている子どもを慰める、こうした経験をするうちに、子どもは自分自身の慰め方、自分自身の感情をコントロールする方法をどんどん吸収して学んでいます。
感情をコントロールする力は、「他者とうまく付き合う力」にもつながります。
この「感情をコントロールする力」が育っていない子どもは、駄々をこねたり、かんしゃくを起こしたりするようなことが増えます。
こうした子どもは、ストレスに弱い特徴もあります。
子どもがストレスに弱いと、「親の子離れ」ができていない親だと、いつまでたっても親が子どもを慰めるかのように、子どもの感情をコントロールしてしまいがちです。
すると、子どもは自分の感情をコントロールする実践の場を経験することができません。
親は「子どもは自分とは全く別の人格を持った一人の人間」という認識を持つ必要があります。
こうした認識を持って接していければ、最初は一人でできなかったことを子どもができるようになり、あとは子どもに任せられるようになっていきます。



感情コントロールの育て方については、次の記事も参考にしてください。
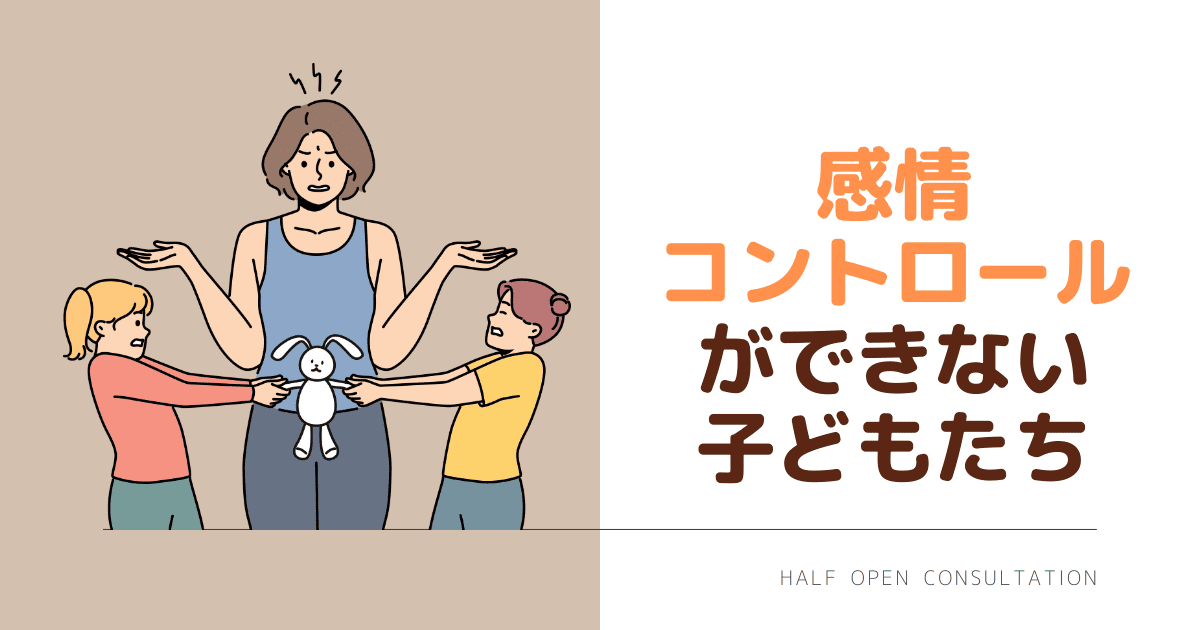
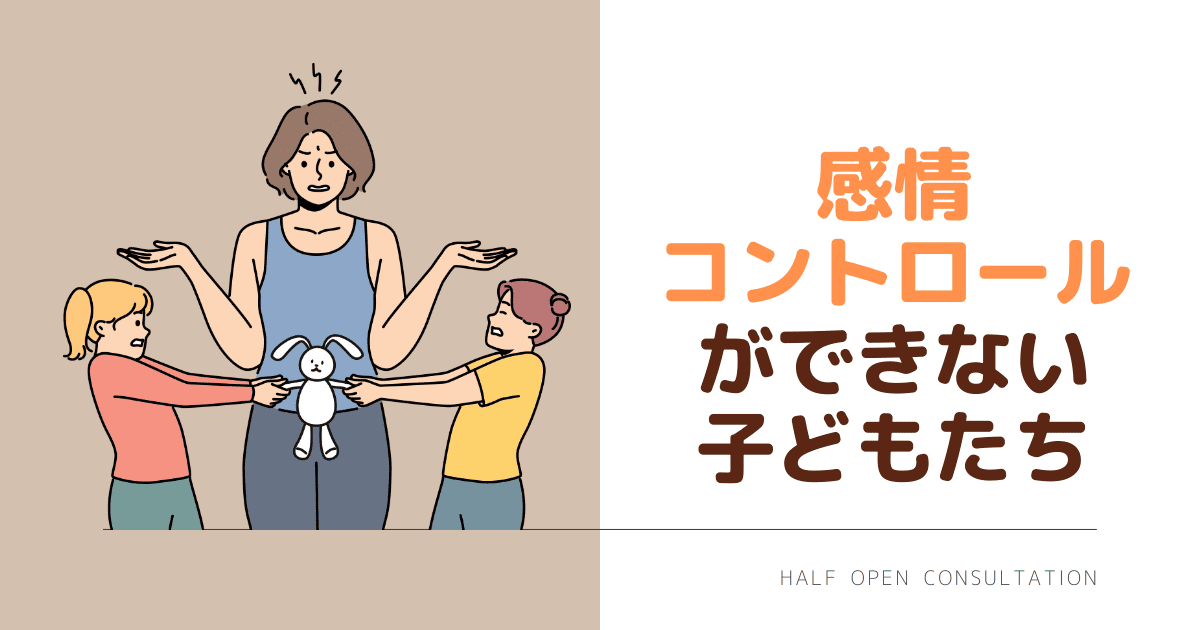
- 「アタッチメント」によって、感情をコントロールする力が身につく
- 子どもが頻繁に感情をコントロールできなくなるようなら、しつけを振り返る
- 子どももひとりの人間。子ども自身に「任せる」ことも大切
自己決定できない「いい子症候群」の防止法
「いい子症候群」の子どもたちは、必要以上にいい子であろうとする傾向があります。
その大きな特徴としては、次のとおりです。
- 自分を抑えて周囲の人の期待に過剰に応えようとする
- 空気を読もうとするあまりに、自分というものがわからなくなっている
子どもをいい子症候群にさせてしまう最大の要因は、親の子どもとの関わり方にあります。
つまり、子どもが子ども自身の気持ちに従って行動できるようなかかわり方を、親ができていないということです。
例えば、子どもが高校や大学の進路を選ぶとき、親であれば「あなたが好きな学校に行っていいよ」というでしょう。
でも、子どもがいざ志望校を口に出すと、「その学校だとこういうところが心配」「この学校がいいと思う。」などといってしまうかもしれません。
これでは、子どもからすれば、自分の行きたい学校に行っていいとはとても思えないでしょう。
いい子症候群を引き起こす親は、「あなたのためを思って言っているのよ」という態度を取ります。
子どもからすると反発しづらく、そして子どもたちはいい子症候群になっていくのです。
いい子症候群が怖いのは、いい子症候群の子どもたちの多くが、いい子症候群であることに無自覚だという点です。
そのまま大人になってしまうと、いい子症候群の子どもは「アダルトチルドレン」と呼ばれるようになります。
子どもをいい子症候群にしないためには、子どもに空気を破る練習をさせれば良いです。
わかりやすい例を挙げるなら、外食のときに子どもが親の顔色を見てメニューを選ぶのではなく、自分の食べたいものを真っ先に選ぶようにしてあげるのです。
子どもが親の顔色をうかがうような素振りを見せたら、危険信号です。
今、手がかからないいい子というのは、後々手がかかる人間になりやすいです。
そして、子どもが自分で決められるまで、親は辛抱強く待ちましょう。
子どもをいい子症候群にしないため、親にもっと必要なものは、何よりも根気、「待つ力」です。
- 親の期待を押しつけていると、子どもは「いい子症候群」になってしまう
- 「アダルトチルドレン」になってしまうと、空虚感や生きづらさを抱えてしまう
- 子ども自身が自分でものごとを決められるように、親は辛抱強く待とう
まとめ
今回は、子どもの自己肯定感と非認知能力を高めるために親ができることを説明しました。
自己肯定感と非認知能力を育むには、親の関わり方が大切です。
日常の中で「ありのままを認める」「挑戦を応援する」「感情を受け止める」「子どもが決められるまで待つ」など、少し意識するだけで、子どもは安心して成長していきます。
すぐに効果が出るものではありませんが、長い目で見て続けることが重要です。
親自身も完璧を目指す必要はありません。
おおらかな気持ちで、子どもと一緒に成長していきましょう。
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村
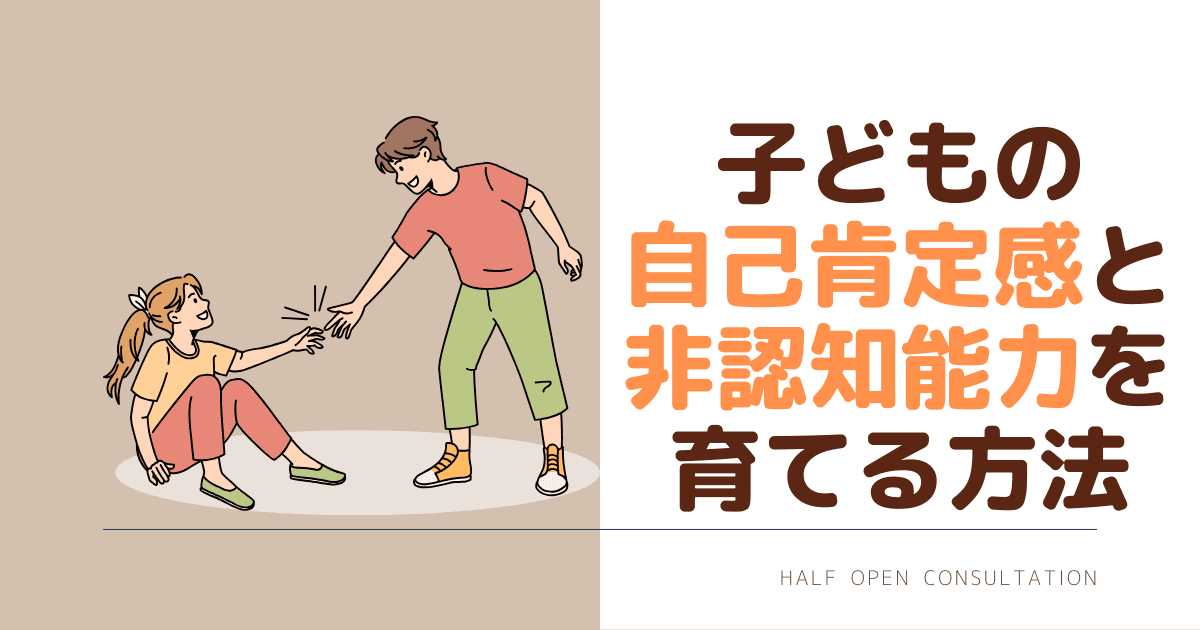

コメント