「産後うつ」と聞くと母親の問題と思われがちですが、実は父親も起こることをご存じですか?
近年、「父親の産後うつ」が注目されるようになり、特に仕事と育児の両立に悩む共働き家庭のパパに多く見られます。
睡眠不足や育児のプレッシャー、妻との関係変化などが重なり、気づかないうちに心身が疲弊してしまうのです。
しかし、適切なセルフケアを実践すれば、父親の産後うつを防ぐことができるかもしれません。
そこで、本記事では、父親の産後うつの原因やサインを解説し、働くパパが実践できるセルフケア方法を紹介します。
- 共働きで仕事と育児の両立に悩んでいるパパ
- 最近、気分が落ち込みやすくなったと感じるパパ
- 夫の産後うつを心配しているママ
 ゆう
ゆう家庭を支えるパパ自身の心の健康を守ることが、家族全体の幸せにつながります。無理せずできるセルフケアのポイントを知り、健やかな育児ライフを送りましょう。
父親の産後うつとは?
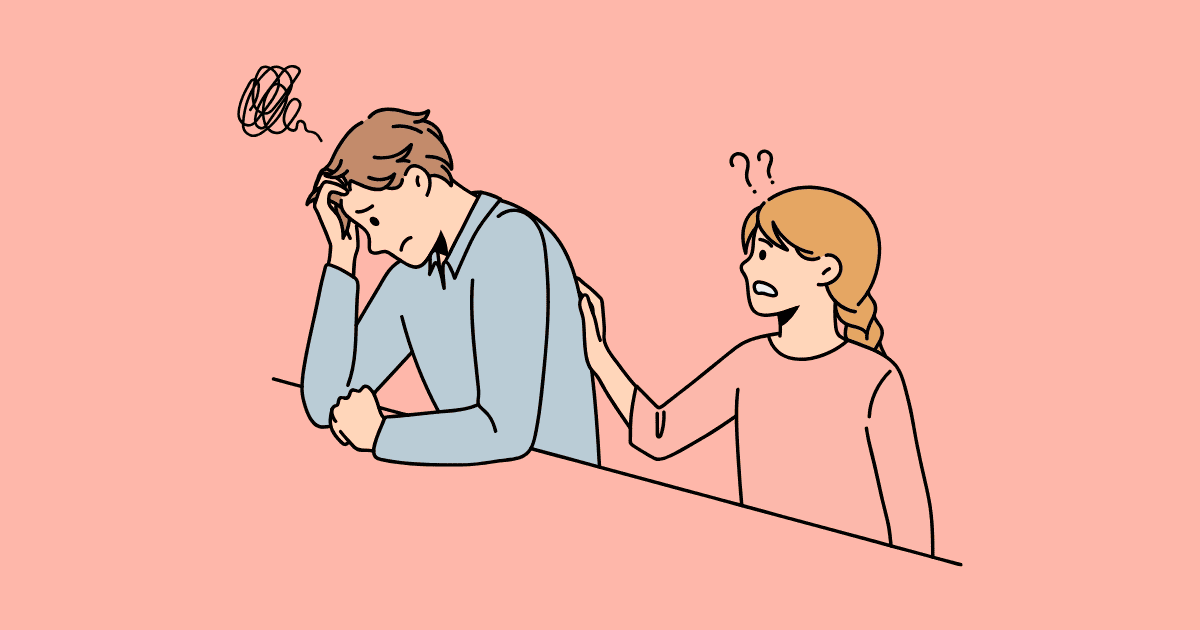
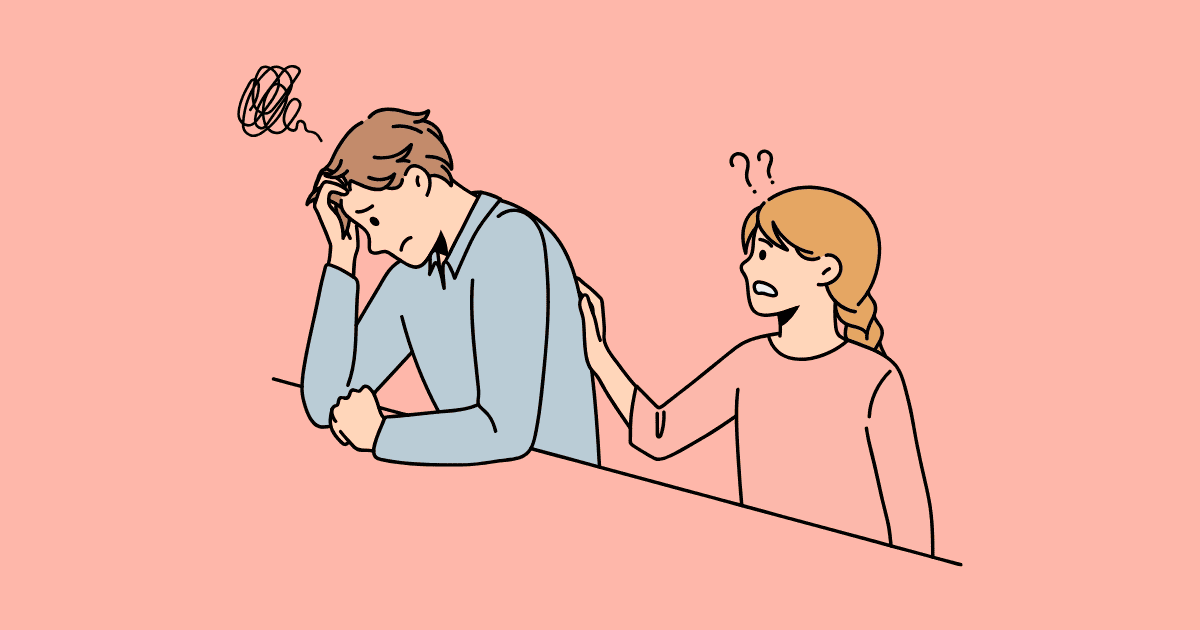
「父親の産後うつ」について、2025年に話題になり、ネット上で炎上して物議となりました(ヤフーニュース)。
「父親の産後うつ」というワードだけが一人歩きし、「産んでもないのに」、「育児うつと分けて」などの反論が相次ぎました。
ただし、後述しますが「父親の産後うつ」についての研究が進みつつあり、そうした中で支援の動きも広がっています。
ここでは、父親の産後うつの定義や発症率などを紹介します。
産後うつは母親だけのものではない
「産後うつ」という言葉を聞くと、母親に起こるものだと思われがちですが、父親も産後うつになることがあります。
特に共働き家庭では、仕事と育児の両立に苦しみ、精神的に追い詰められるケースが少なくありません。
母親ほど育児に時間を割けない罪悪感や、仕事の責任が増すプレッシャー、夫婦関係の変化による孤独感などが重なり、気づかないうちにストレスが蓄積してしまいます。
しかし、父親の産後うつは周囲に理解されにくく、「頑張らなければ」という思いから相談できない人も多いのが現状です。
母親だけでなく、父親も産後うつを発症する可能性があることを理解することが、家庭全体の安定のための第一歩です。
父親の産後うつの定義と発症率
父親の産後うつは、出産後に父親が経験する抑うつ状態を指します。
主な症状には、気分の落ち込み、イライラ、不安感、睡眠障害、育児や仕事への意欲低下などがあります。
これまで母親の産後うつが注目されてきましたが、近年の研究では、父親の約10%が産後うつを経験すると報告されています(「父親の産後うつ」竹原健二・須藤茉衣子)。
特に、出産後3〜6か月の間に発症しやすく、この時期は育児の負担が増すだけでなく、母親の体調が回復途上であり、夫婦ともにストレスを感じやすい時期です。
しかし、父親の産後うつは「男だから大丈夫」と見過ごされがちで、適切なケアが受けられないこともあります。
近年注目される「パタニティブルー」
「パタニティブルー」という言葉も注目されています。
これは、出産後の父親が一時的に気分の落ち込みや不安を感じる状態を指し、母親の「マタニティブルー」と似た現象です。
生活環境の急激な変化などが影響していると考えられており、特に初めての子育てを経験する父親に多く見られます。
しかし、「パタニティブルー」は一時的なものであり、通常は数週間以内に回復します。
一方で、長期間にわたって気分の低下が続く場合は「産後うつ」に移行する可能性があり、注意が必要です。



母親の「マタニティブルー」については、次の記事を参考にしてください。
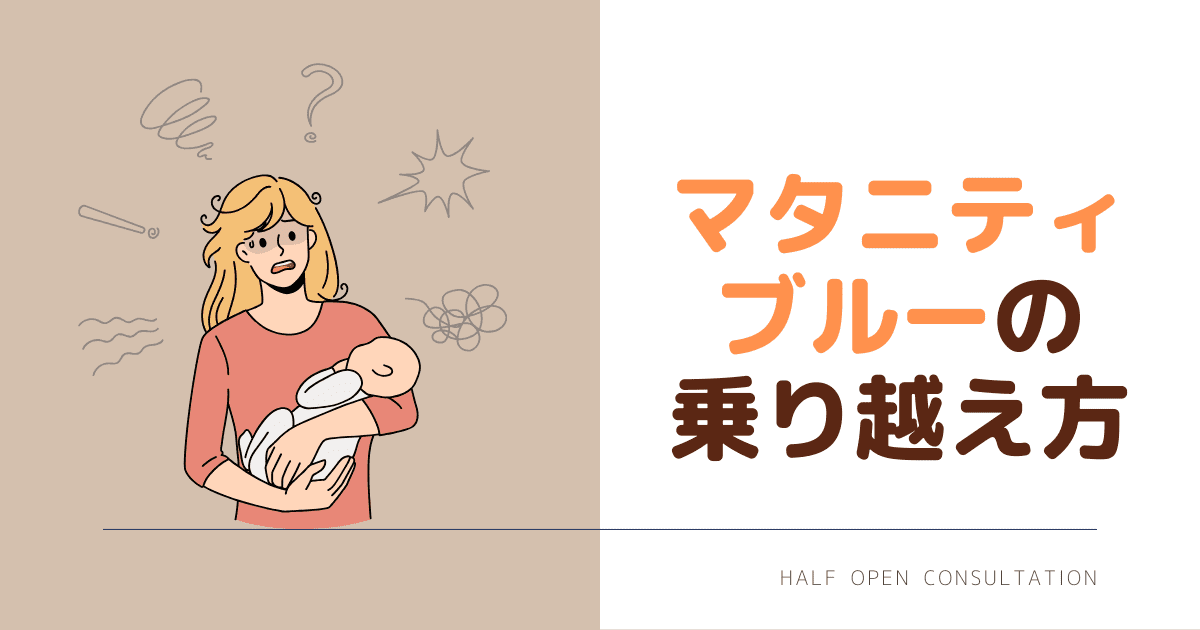
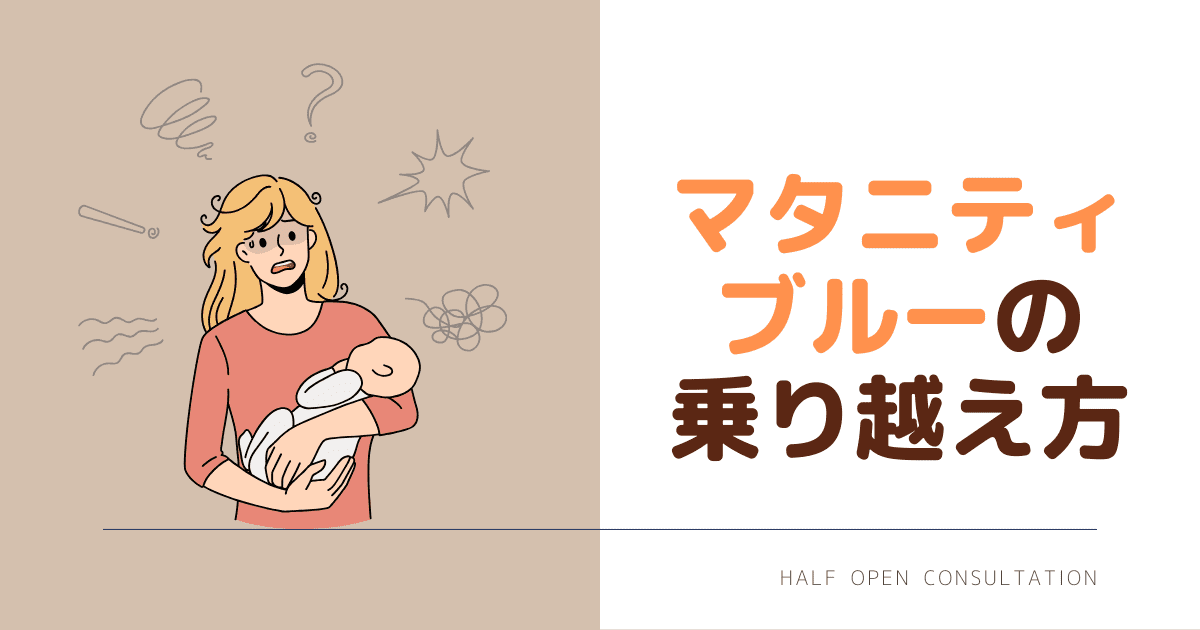
父親の産後うつが起こる原因
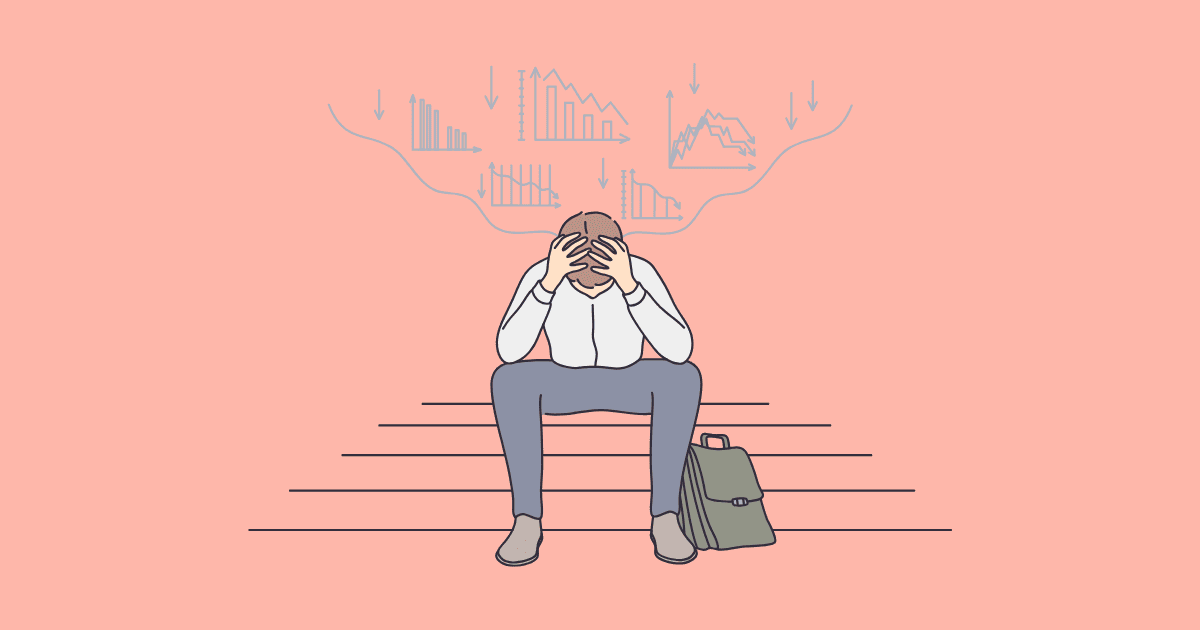
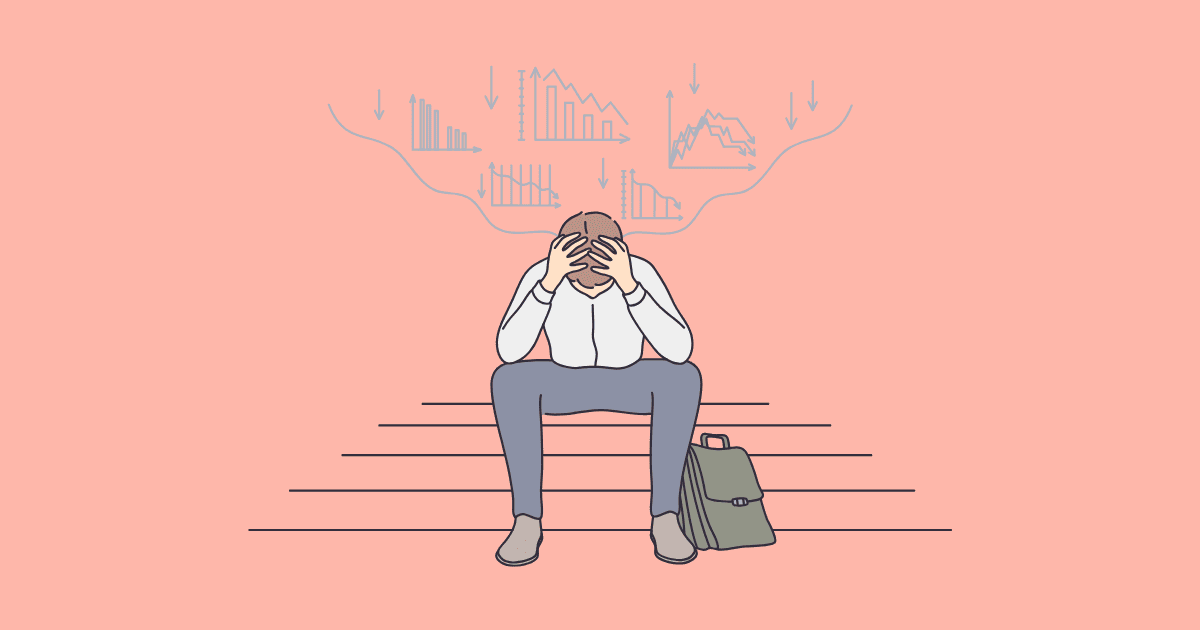
父親の産後うつは、さまざまな要因が絡み合って発症します。
特に共働き家庭では、仕事と育児のバランスを取ることが難しく、心身の負担が大きくなりがちです。
育児・家事の負担増加、仕事との両立、夫婦関係の変化、社会的な孤立感、睡眠不足など、複数のストレスが積み重なることで、気づかないうちに心の不調が進行してしまいます。
ここでは、父親の産後うつが起こる主な原因について詳しく解説し、どのような状況がリスクを高めるのかを見ていきます。
育児・家事の負担増加によるストレス
出産後、父親も育児や家事の負担が大きくなります。
特に、現代の共働き家庭では、母親だけでなく父親も積極的に育児に関わることが求められます。
しかし、初めての育児で戸惑うことも多く、「やり方が分からない」「手際が悪いと言われる」などのストレスを感じることもあります。
また、家事の分担も増え、これまでの生活リズムが崩れることで疲労が蓄積しやすくなります。
こうしたストレスが続くと、「自分は父親として十分ではないのではないか?」「役に立っていない」などと自信を失い、気持ちが落ち込んでいきます。
仕事と家庭の両立のプレッシャー
出産後、父親は「もっと仕事を頑張らなければ」というプレッシャーを強く感じることが多くなります。
育児や家事に時間を取られる一方で、職場では今までどおりの成果を求められ、両立の難しさに直面するケースが少なくありません。
そうした中で、「育児にもっと関わりたいのに仕事が忙しくてできない」、「職場では育児の大変さを理解してもらえない」といったジレンマが、精神的な負担を大きくさせます。
また、仕事での疲れが育児に影響し、家庭での子育ての役割が十分に果たせないと感じることで、自責の念を抱くことにもつながります。
妻の変化による心理的な負担(夫婦関係の変化)
出産後、妻の心身には大きな変化が起こります。
出産後の妻はホルモンバランスの乱れや産後の疲れから、情緒が不安定になりやすくなります。
すると、父親はこれまでとは違う妻の姿に戸惑ってしまいます。
また、妻が赤ちゃん中心の生活になり、夫婦の会話やスキンシップが減っていきます。
すると、「自分は必要とされていないのでは?」、「自分の気持ちを理解してもらえない」と感じることも出てくるでしょう。
このような変化に適応できず、夫婦間のすれ違いが生じると、ますますストレスが増していきます。
社会的サポートの不足(相談相手がいない孤独感)
父親の産後うつが深刻化しやすい要因の一つに、社会的なサポートの不足があります。
母親の場合、自身の親やママ友仲間など身近に相談しやすい人がいる場合が多いです。
また、地元にある育児中のコミュニティや支援制度も比較的充実しています。
しかし、父親向けの支援はまだ十分とは言えません。
そのため、父親は「悩みを相談できる相手がいない」「周囲に理解されず、孤独を感じる」といった状況に陥りやすくなります。
仕事中心の生活を送ってきた父親にとって、育児の悩みを同僚や友人に打ち明けるのはハードルが高いと感じることもあります。
こうした孤立感がストレスとなり、メンタルヘルスの悪化につながるのです。
睡眠不足・生活習慣の乱れ
出産後、育児中心の生活になると、睡眠不足や生活習慣の乱れが避けられません。
夜泣きへの対応や、早朝からの育児・家事で十分な睡眠が取れず、疲労が蓄積していきます。
さらに、仕事をしている父親の場合、日中は職場での業務に追われ、夜も育児に関わることで、慢性的な疲労状態に陥ることが多くなります。
睡眠不足は精神的な不調を引き起こしやすく、イライラや集中力の低下、気分の落ち込みにつながるため、産後うつのリスクを高めます。
父親の産後うつのサイン
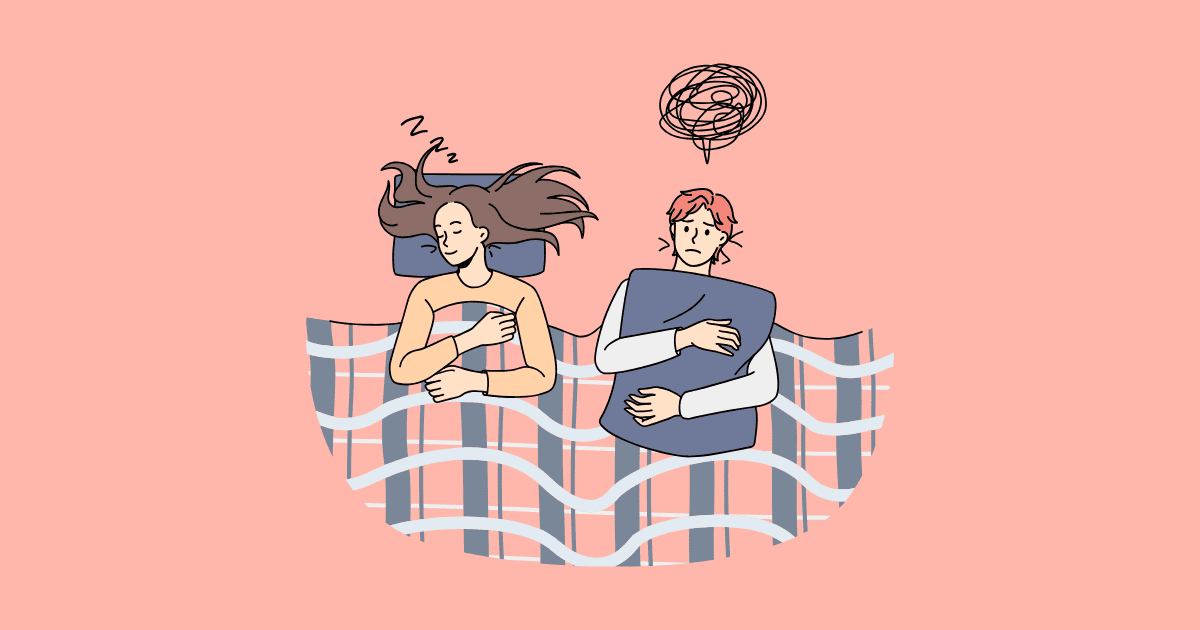
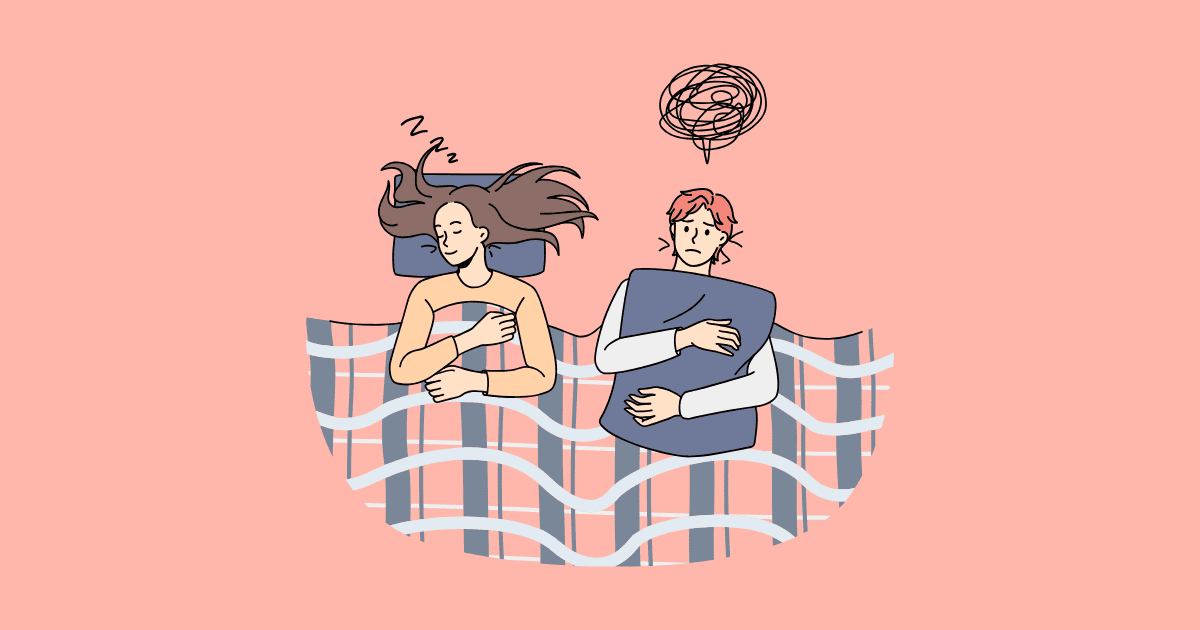
父親の産後うつは、自覚しづらいことが特徴の一つです。
「疲れているだけ」「自分が弱いせいだ」と思い込み、気づかないうちに症状が悪化することも少なくありません。
日常の中で現れる小さな変化に目を向けることで、早めに対処することが可能です。
ここでは、父親の産後うつの主なサインを5つ紹介します。
- 気分が落ち込む・やる気が出ない
- 育児に対する無力感・イライラ
- 仕事のパフォーマンス低下
- 眠れない・食欲がない
- 妻や子どもとのコミュニケーションが減る



自分自身やパートナーの様子を振り返り、当てはまるものがないか確認してみましょう。
気分が落ち込む・やる気が出ない
父親の産後うつの初期症状として、気分の落ち込みや無気力感が挙げられます。
以前は楽しめていたことに興味が持てなくなったり、仕事や趣味に対する意欲が低下したりすることがあります。
「何をしても楽しくない」「何となく気分が晴れない」と感じる日が続く場合は注意が必要です。
特に、理由もなく憂うつな気分が続く場合や、漠然とした不安を感じることが増えた場合は、心の疲れが限界に近づいているサインかもしれません。
育児に対する無力感・イライラ
育児への関わりが増える一方で、「自分は役に立てていない」と感じたり、ささいなことでイライラしたりすることがあります。
赤ちゃんが泣き止まない、思うように育児が進まないといった場面で、無力感を覚える父親は少なくありません。
また、仕事や家事の疲れがたまることで、パートナーや子どもに対してイライラしやすくなることもあります。
こうした感情のコントロールが難しくなったと感じる場合は、心の負担が大きくなっている可能性があります。
仕事のパフォーマンス低下
産後うつは、家庭内だけでなく仕事にも影響を及ぼします。
集中力が続かず、ミスが増えたり、仕事への意欲が低下したりすることがあります。
また、「職場ではふだんどおりに振る舞わなければ」というプレッシャーから、余計に疲労がたまりやすくなることもあります。
上司や同僚に相談できず、一人で抱え込んでしまうことで、症状が悪化することもあります。
以前より仕事に対する意欲が湧かない、効率が落ちたと感じる場合は、心の疲れを疑ってみましょう。
眠れない・食欲がない
産後の生活リズムの変化によって、睡眠や食事に影響が出ることもあります。
「疲れているのに眠れない」「食欲がなく、食事が楽しめない」といった症状は、産後うつのサインの可能性があります。
特に、夜中の授乳や赤ちゃんの夜泣きで生活リズムが乱れ、不眠が続くと、心身ともに疲労がたまりやすくなります。
睡眠不足や栄養不足は、気分の落ち込みやイライラを悪化させる要因にもなるため、意識的に休息を取ることが大切です。
妻や子どもとのコミュニケーションが減る
産後うつが進行すると、妻や子どもとのコミュニケーションが減ることがあります。
「話すのが面倒」「関わるのがしんどい」と感じ、家庭内での会話が減少します。
また、子どもとのふれあいに対しても「どう接していいかわからない」と感じ、距離を置いてしまうこともあります。
こうした変化が続くと、夫婦関係が悪化したり、育児への関わりが減ってしまったります。
父親の産後うつを防ぐためのセルフケア方法
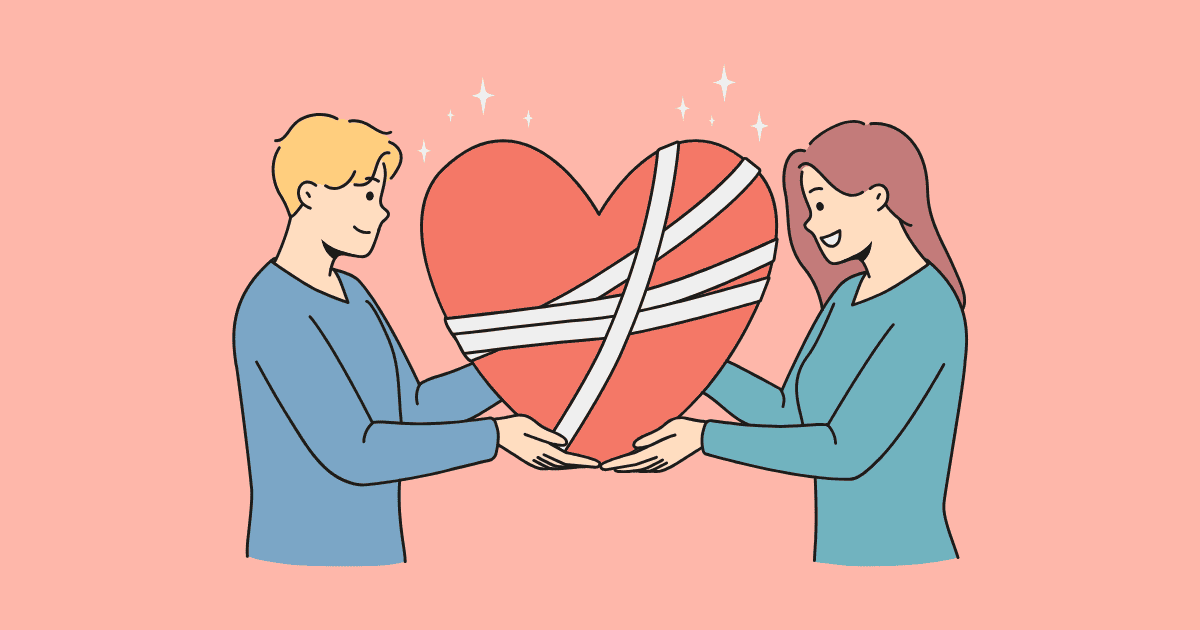
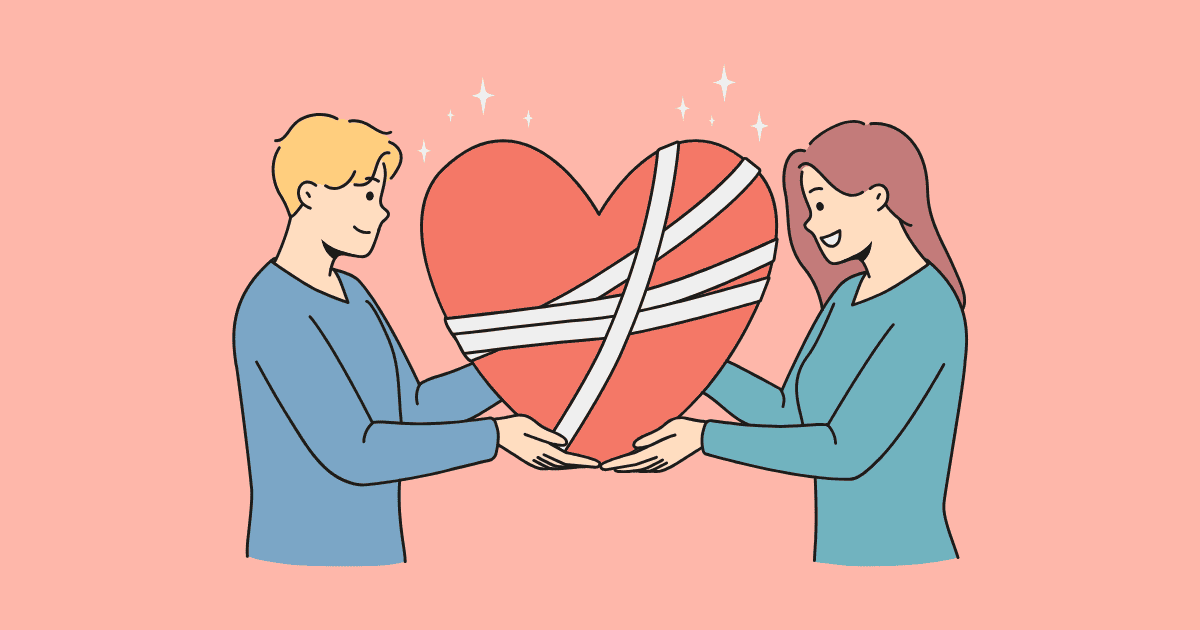
父親の産後うつを防ぐためには、日々のセルフケアが欠かせません。
仕事と育児の両立に追われ、自分のことを後回しにしてしまうと、心身の負担が蓄積し、気づかないうちにストレスが限界に達してしまいます。
大切なのは、「無理をしないこと」と「小さな工夫を積み重ねること」です。
ここでは、次の5つについて紹介します。
- 睡眠の質を上げる工夫
- 仕事と育児のバランスの取り方
- 一人の時間の確保
- 夫婦のコミュニケーションの深め方
- 周囲のサポートの活用
睡眠の質を上げる工夫(短時間でも深く眠る方法)
産後は睡眠時間の確保が難しくなりますが、短時間でも深く眠る工夫をすることで、疲労回復の効果を高めることができます。
例えば、寝る前にスマートフォンの使用を控えたり、照明を暗めにしたりすることがスムーズな入眠につながります。
また、赤ちゃんの生活リズムに合わせて仮眠を取るのも有効です。
パートナーと交代で夜間対応をする、休日は少し長めに眠るなど、夫婦で協力しながら休息の時間を確保することも大切です。
睡眠の質を意識することで、日中のパフォーマンスも向上します。



次の記事でも夜にぐっすり眠る方法について解説しています。
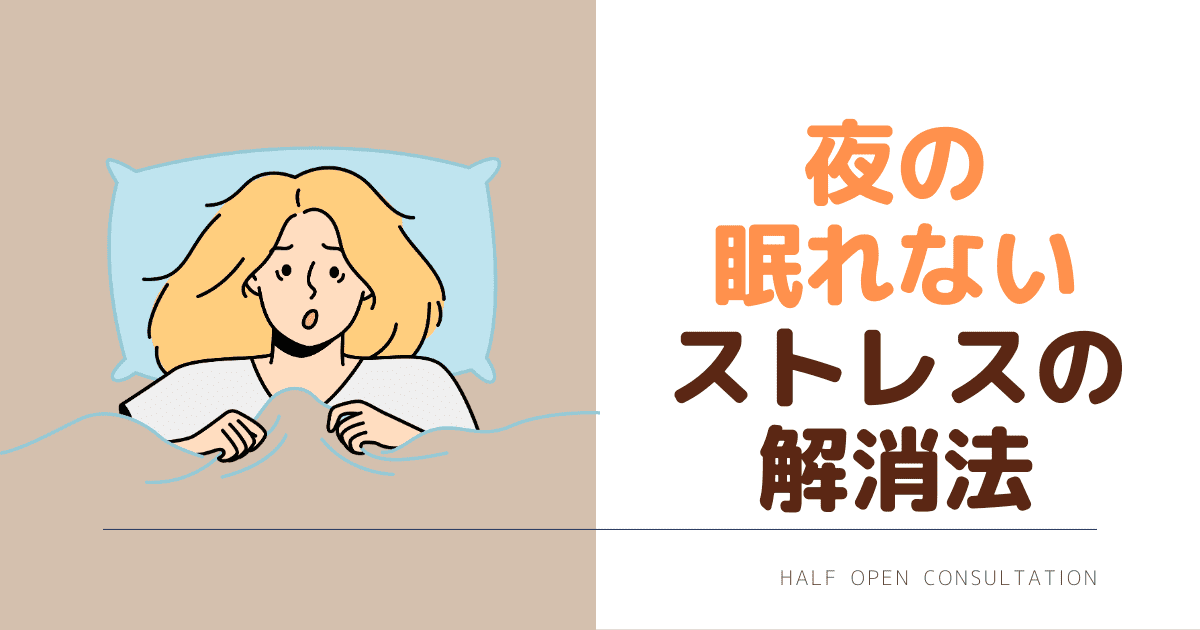
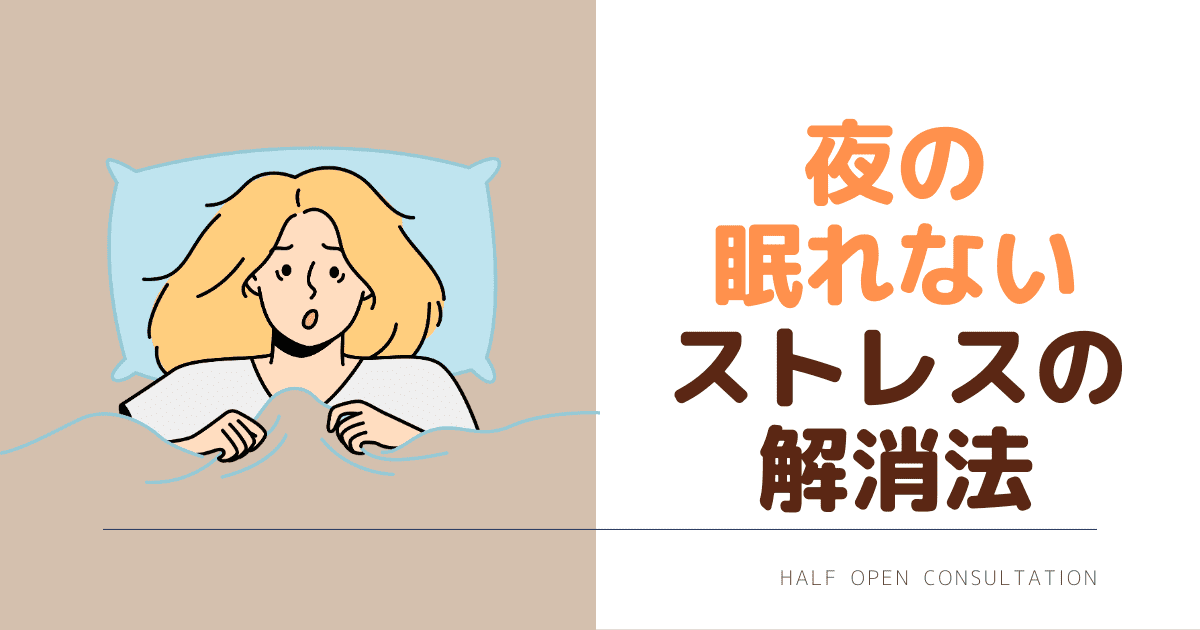
仕事と育児のバランスの取り方(職場との調整)
仕事と育児のバランスを取るためには、職場との調整が欠かせません。
まずは、上司や同僚に家庭の状況を伝え、可能な範囲で業務量や勤務時間の調整を相談してみましょう。
テレワークやフレックスタイム制などの制度を利用できる場合は、積極的に活用するのも一つの手です。
また、仕事の効率を意識し、業務の優先順位を明確にすることで、残業を減らし、育児に関わる時間を増やすこともできるでしょう。
無理をせず、長期的に働き続けるための工夫が重要です。
一人の時間を確保する(リフレッシュの重要性)
育児や仕事に追われると、自分の時間を確保するのが難しくなります。
そのため、心の健康を保つためにもリフレッシュの時間が必要です。
短時間でも、趣味の時間を作る、散歩をする、好きな音楽を聴くなど、気分転換できる時間を意識的に取り入れましょう。
また、パートナーと話し合い、お互いに一人の時間を確保できるように協力することも大切です。
リフレッシュの時間を持つことで、気持ちに余裕が生まれ、育児や仕事に対するストレスが軽減されます。



リフレッシュの一つの方法として「マインドフルネス」が有効です。
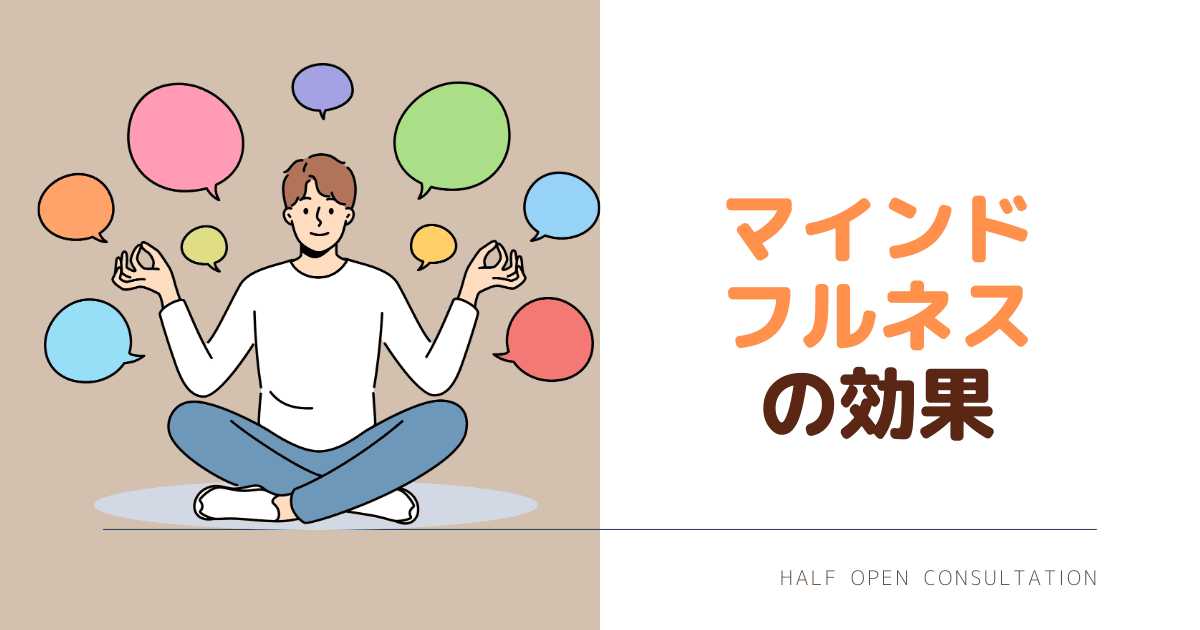
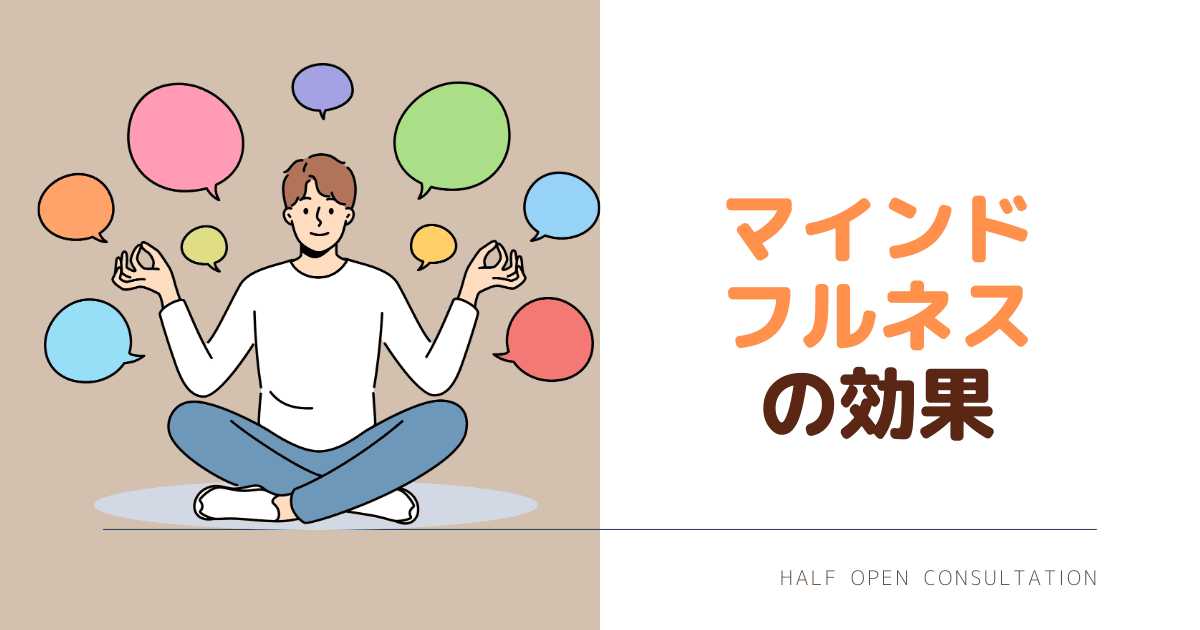
妻とのコミュニケーションを深める(夫婦で支え合うコツ)
産後は育児に追われるあまり、夫婦の会話が減りがちです。
しかし、互いの気持ちを共有し、支え合うことで、産後のストレスを軽減できます。
毎日5分でもよいので、「今日の出来事」や「困っていること」について話す時間を作ると良いでしょう。
また、感謝の気持ちを言葉にして伝えることも、夫婦関係を良好に保つポイントです。
余裕があるときには、一緒にリラックスできる時間を設けるのも効果的です。
小さなコミュニケーションの積み重ねが、夫婦の絆を深めます。



仲良し夫婦について解説した記事があるので参考にしてください。
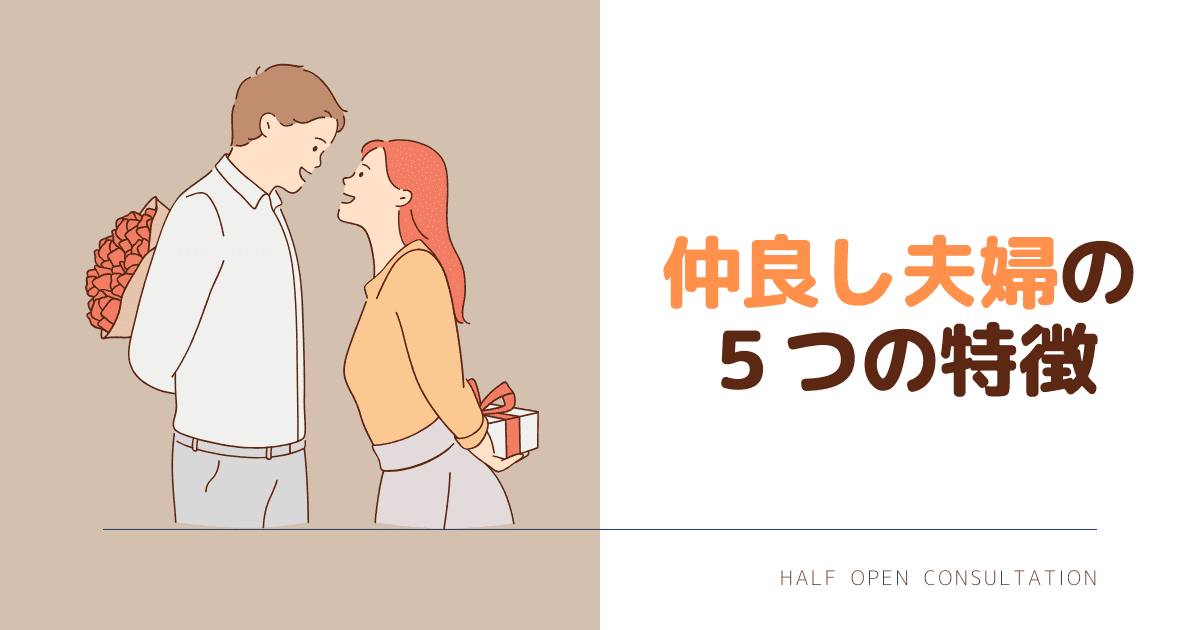
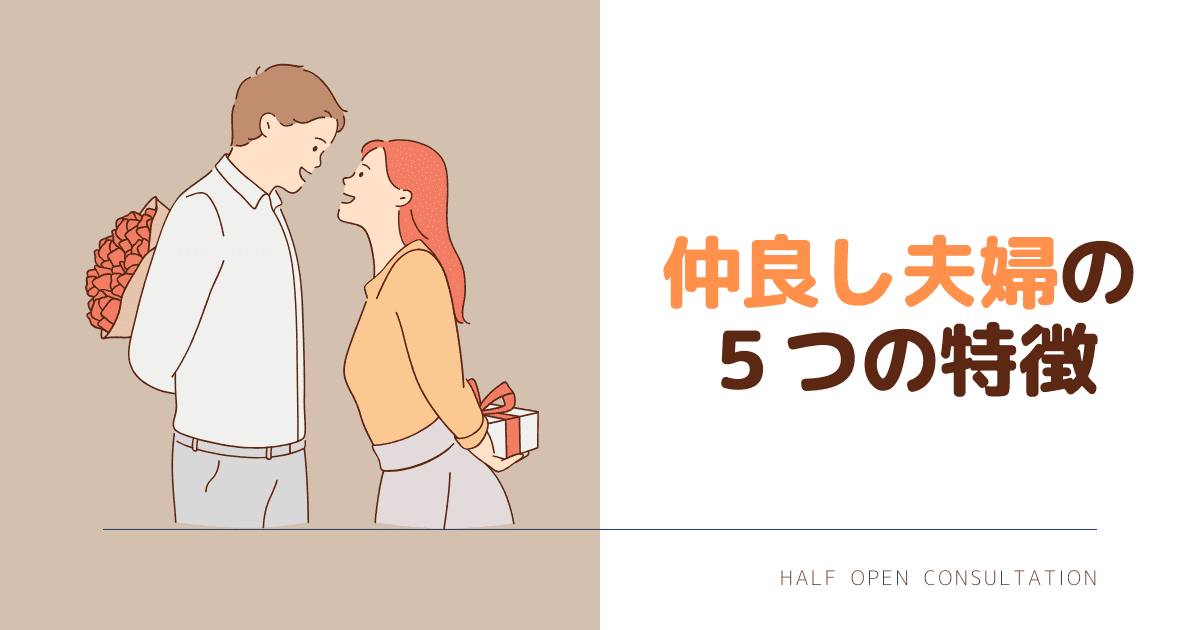
周囲に頼る(家族や自治体のサポートを活用)
育児を一人で抱え込むと、ストレスが増大し、産後うつのリスクが高まります。
周囲に頼ることは決して悪いことではありません。
例えば、実家の両親や親戚に手伝いをお願いする、地域の子育て支援サービスを利用するなど、積極的にサポートを活用しましょう。
自治体の育児相談窓口や父親向けの育児サークルに参加するのも、気持ちを軽くする手助けになります。
「助けを求めることも、家族を守る一つの方法」と考え、適切にサポートを受けることが大切です。



2025年1月には自治体の支援者向けの「父親支援マニュアル」が刊行されました。今後も支援が充実していくと思います。
もし産後うつかも?と思ったときの対処法
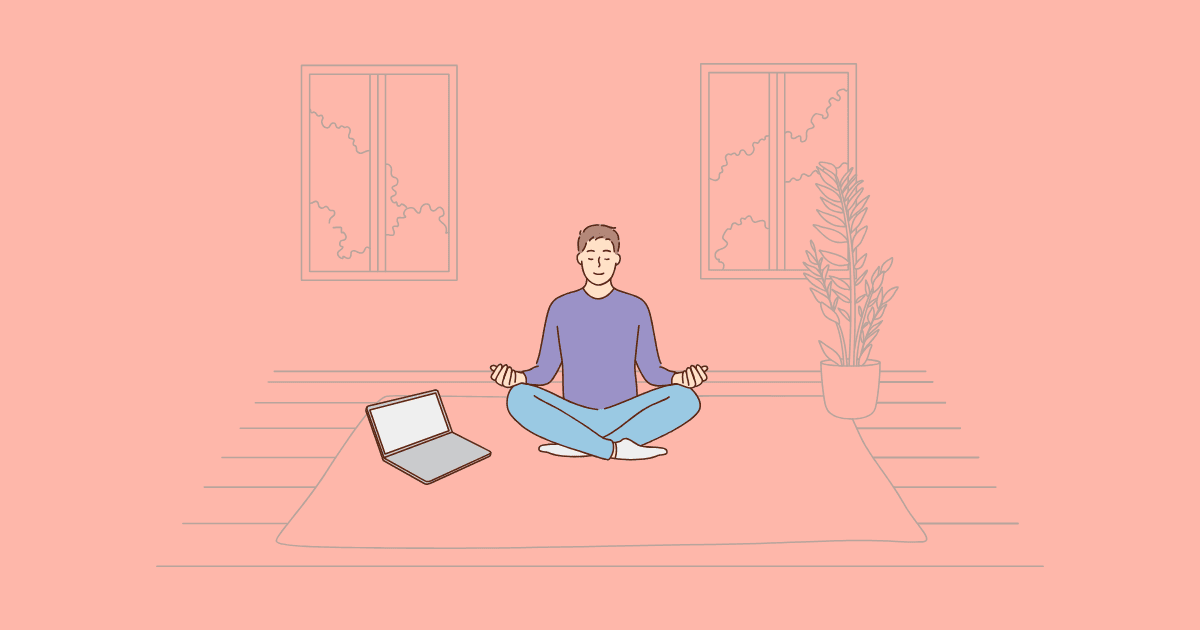
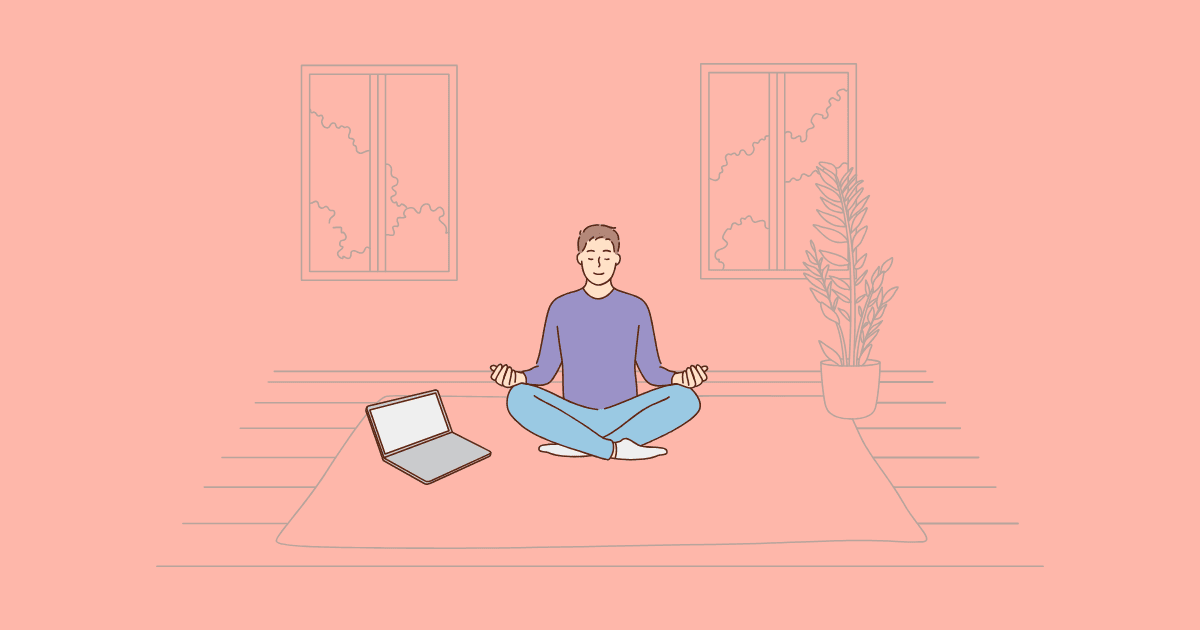
「もしかして自分は産後うつかもしれない」と感じたら、早めに対処することが大切です。
無理に気力で乗り切ろうとすると、症状が悪化し、家庭や仕事にも影響を及ぼすことがあります。
大切なのは、自分の状態を受け入れ、適切な方法で改善を図ることです。
ここでは、次の3つについて解説します。
- 自分の状態を認めることの重要性
- 夫婦で協力しながら改善する方法
- 専門家に相談することの大切さ
自分の状態を認めることの大切さ
父親は、自分自身の産後うつの症状に気づいても、「自分が弱いだけ」「こんなことで悩むのは情けない」と思い込み、無理をしてしまう人は少なくありません。
しかし、産後うつは誰にでも起こる可能性があり、決して特別なことではありません。
まずは、「自分は今、疲れている」「ストレスを感じている」と素直に認めることが大切です。
そのうえで、自分に合った対処法を探していくことで、改善の第一歩を踏み出せます。
心の不調を無視せず、早めに対応することが重要です。



次の記事では、疲れを取るための方法について解説しています。
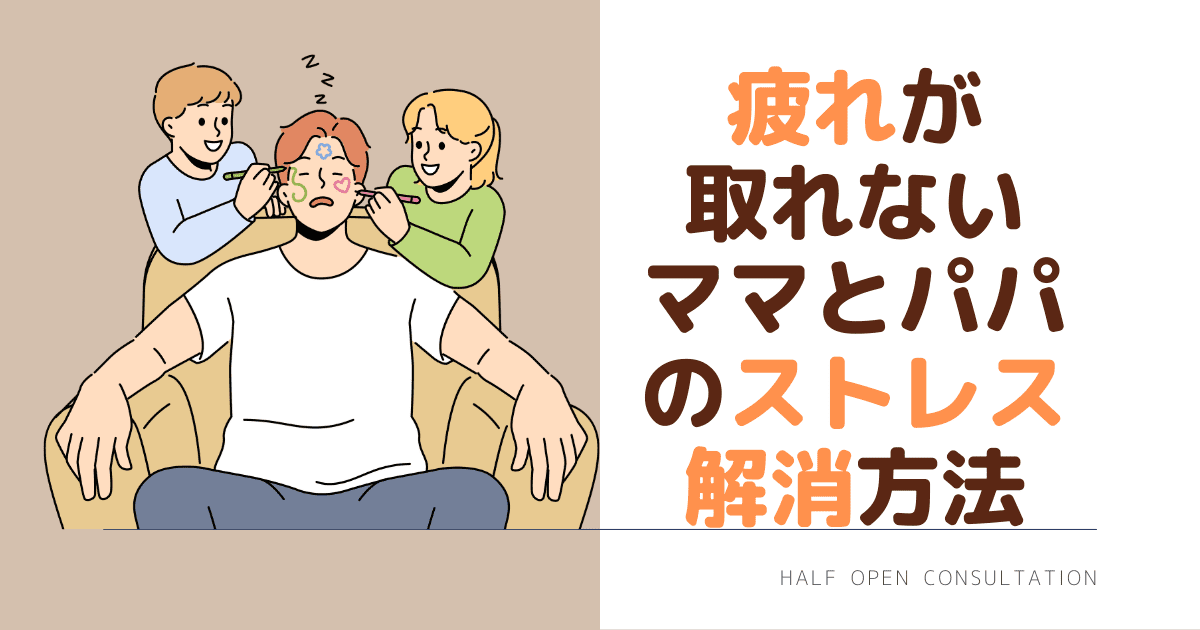
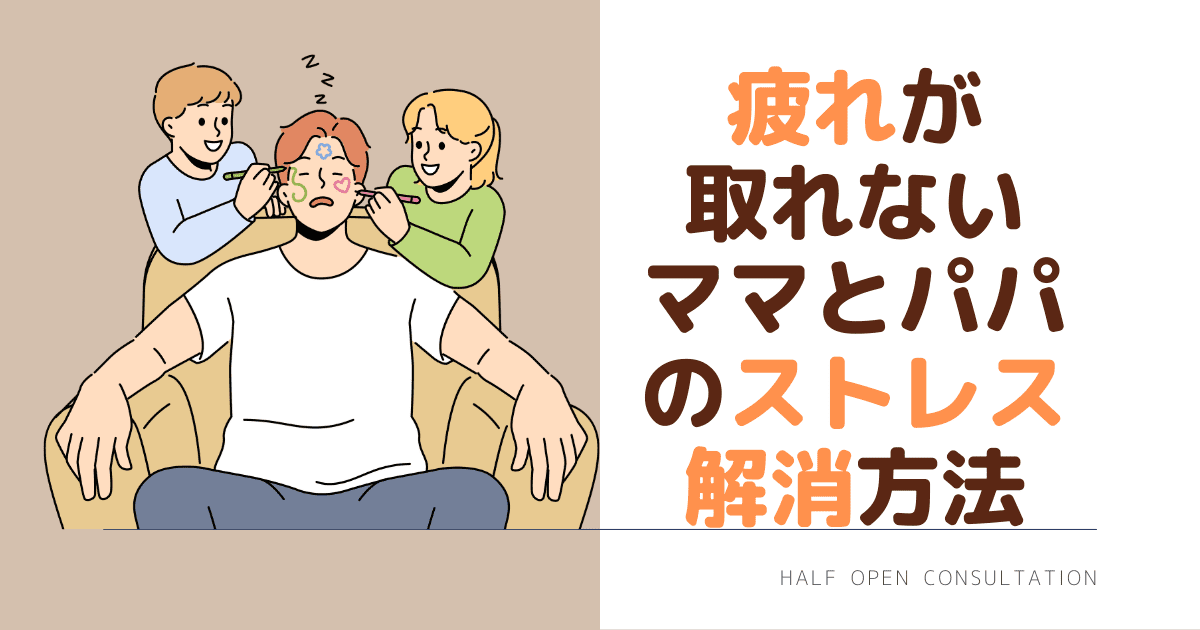
夫婦で協力しながら改善する方法
産後うつの改善には、夫婦の協力が欠かせません。
まずは、素直にパートナーに気持ちを伝えましょう。
「最近、気分が落ち込みやすい」「イライラすることが増えた」など、具体的に話すことで、お互いに理解を深めることができます。
また、育児や家事の負担を見直し、役割分担を調整するのも有効です。
夫婦で定期的に話し合いの時間を持ち、気持ちを共有することが、心の安定につながります。



夫婦間の家事育児の考え方についての記事があるので参考にしてください。
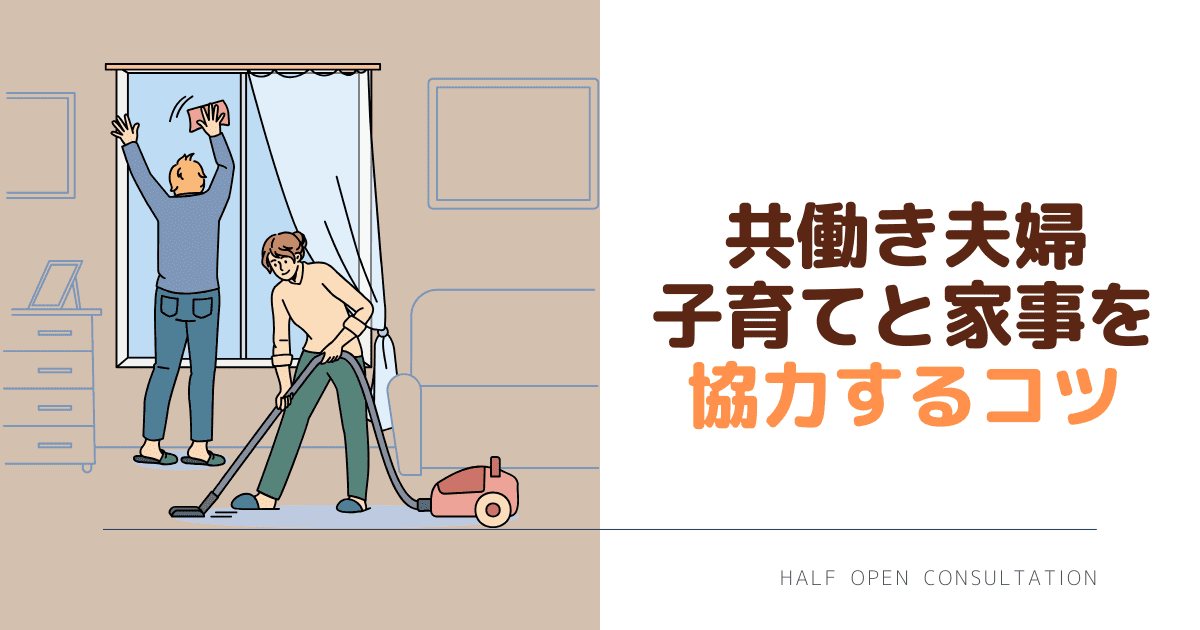
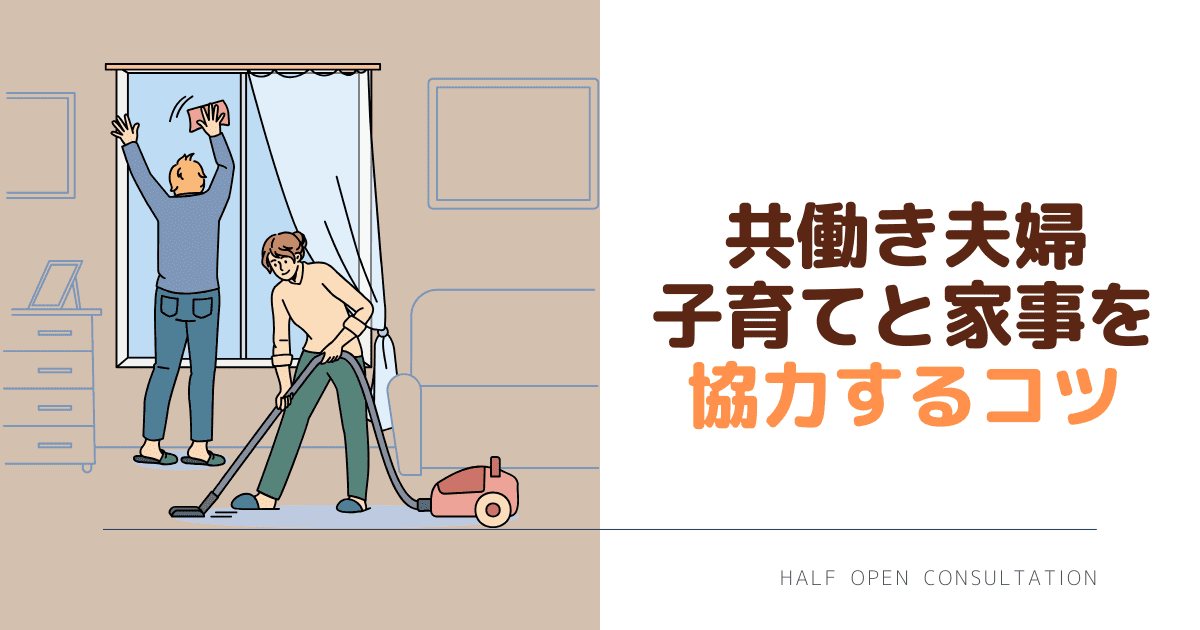
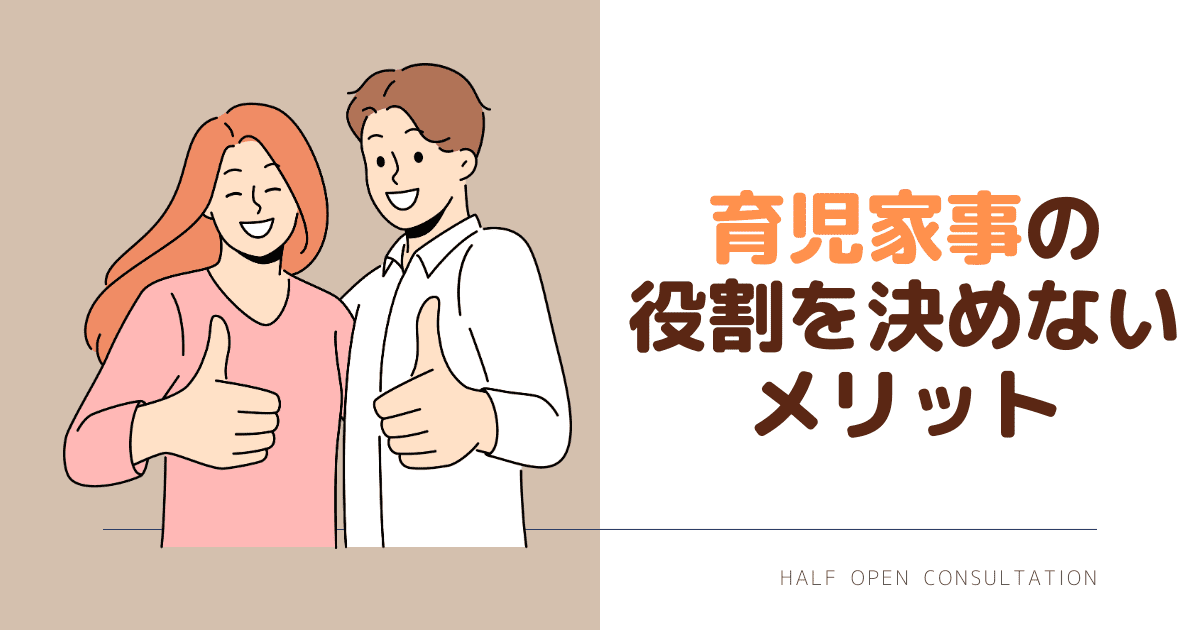
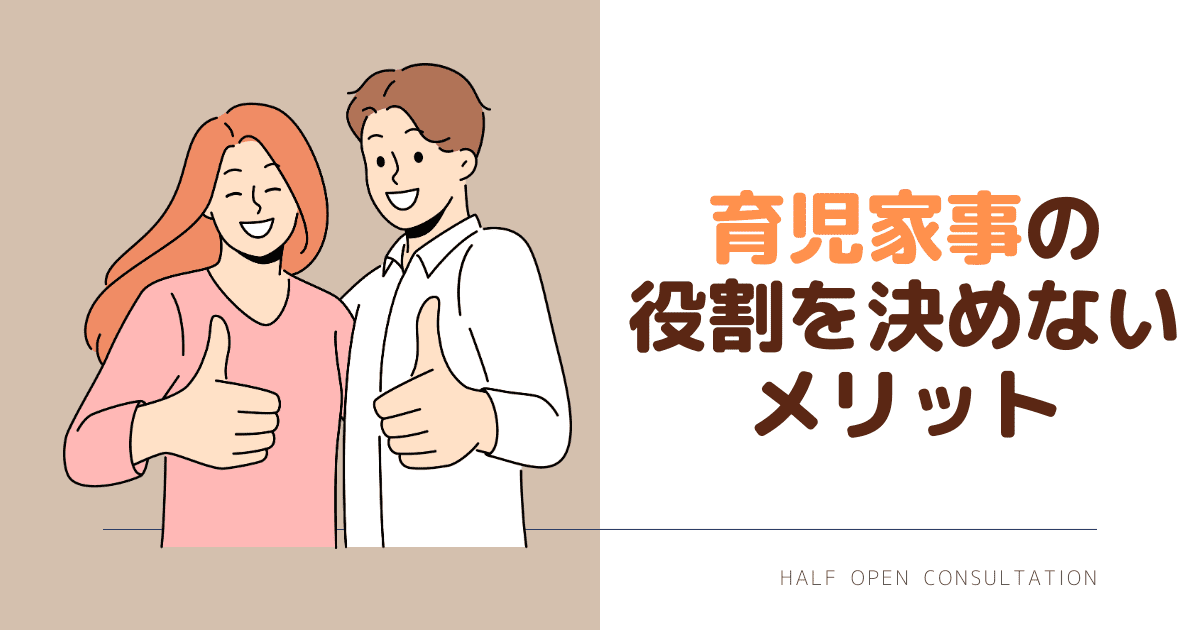
無理せず専門家に相談する(カウンセリング・医療機関の活用)
産後うつの症状が続く場合や、生活に支障を感じるほどつらいときは、専門家に相談することを検討しましょう。
カウンセリングでは、気持ちを整理し、具体的な対処法を学ぶことができます。
また、必要に応じて医療機関での診察や治療を受けることも重要です。
「自分で何とかしなければ」と思い詰めるのではなく、専門的なサポートを活用することで、回復への道が開けます。
心の健康を守るためにも、無理をせず適切な助けを求めましょう。



ココシェルがおすすめしているのが日本最大のオンラインカウンセリングサービス「うららか相談室」です。


- 国内最大のオンラインカウンセリング
- 600名を超える専門家に相談できる
- カウンセリング方法を4種類から選べる
- 誰にも知られず、匿名での相談が可能
\まずは無料会員登録から!/
/満足保証サポート制度\
まとめ
本記事では、父親の産後うつの原因やサインを解説し、働くパパが実践できるセルフケア方法を紹介しました。
父親の産後うつは決して珍しいものではなく、共働き家庭のパパほどリスクが高いと言われています。
大切なのは、症状に早めに気づき、適切なセルフケアを行うことです。
睡眠の質を上げる工夫や、一人の時間を確保すること、そして妻とのコミュニケーションを意識するだけでも負担は軽減されます。
一人で抱え込まず、必要に応じて周囲のサポートを活用することも重要です。
父親が心身ともに健康でいることは、家族全体の安心感にもつながります。
本記事で紹介したセルフケアを実践しながら、パートナーと協力して育児を楽しみましょう。
ご相談や質問がある場合には、こちらまでどうぞ!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
にほんブログ村
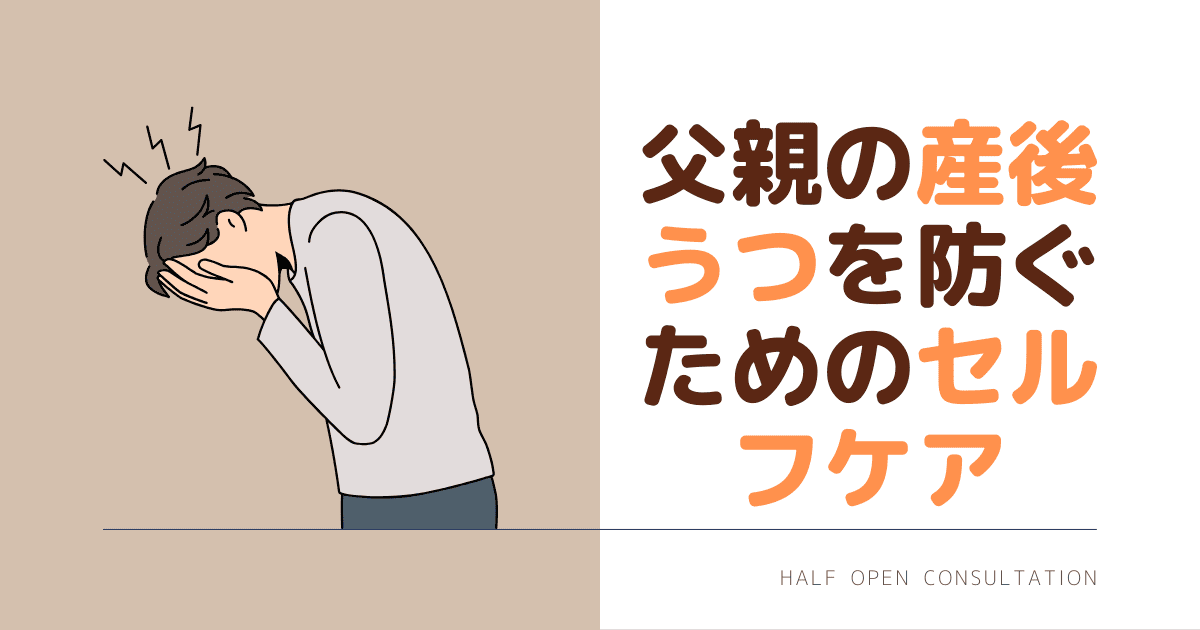
コメント